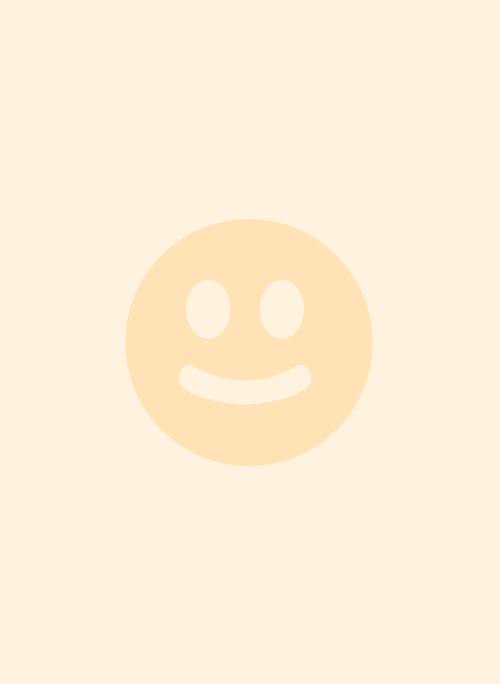「ん?…ほら、いくぞ」
ふと頬を緩めた太一さんは、何気なしにあたしの手を引いてくれた。
あの、5月のお祭りのときみたく。
人ごみを掻き分けて、ようやく商店街まで戻ってきた。
まだ閑散と静けさを保ったままのこの通りは、どこか寂しくも感じさせる。
「今日はどうするんだ?」
いつ勉強するか?ってこと…だよね。
「あ、じゃあ、勉強道具もってきます……」
何故か気合が入らない。
やけにイライラするし、だからといってなにが嫌なのかも分からなかった。
そんな憂鬱に肩を落としていた。
「…チビ助」
「はい……?」
呼ばれたから顔をあげた。
なのに、急に視界は真っ暗で、ごわごわする感触に息苦しくもなった。
あたしは……あの太一さんに抱きしめられていたんだ。
「お前からもらったクッキー、うまかったよ」
頭上で聞こえる小さな声。
それはきっと、照れ屋の太一さんにとってはたくさんの勇気がいるはずだ。
なのに、最も恥ずかしい方法をとったんだ。
「た、太一…さんっ」
触れていいの?
ふと頬を緩めた太一さんは、何気なしにあたしの手を引いてくれた。
あの、5月のお祭りのときみたく。
人ごみを掻き分けて、ようやく商店街まで戻ってきた。
まだ閑散と静けさを保ったままのこの通りは、どこか寂しくも感じさせる。
「今日はどうするんだ?」
いつ勉強するか?ってこと…だよね。
「あ、じゃあ、勉強道具もってきます……」
何故か気合が入らない。
やけにイライラするし、だからといってなにが嫌なのかも分からなかった。
そんな憂鬱に肩を落としていた。
「…チビ助」
「はい……?」
呼ばれたから顔をあげた。
なのに、急に視界は真っ暗で、ごわごわする感触に息苦しくもなった。
あたしは……あの太一さんに抱きしめられていたんだ。
「お前からもらったクッキー、うまかったよ」
頭上で聞こえる小さな声。
それはきっと、照れ屋の太一さんにとってはたくさんの勇気がいるはずだ。
なのに、最も恥ずかしい方法をとったんだ。
「た、太一…さんっ」
触れていいの?