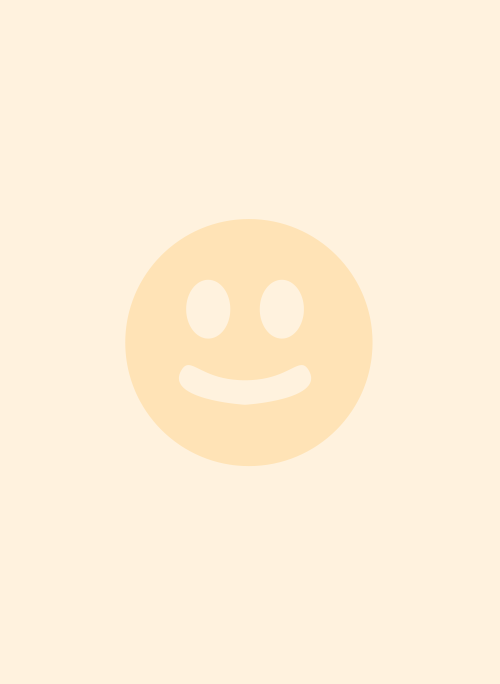「あなたの高校受験のときは、ね。
先生が…―ああ、今はマスターだったわね、ちょうどあたしが仕事でアメリカに行かなくちゃならなくなって、声をかけてくださったわ」
それは知っていた。
なんでも勝手に決めていく母さんがうざったくて、それがどうにもできないオレは勝手にふてくされていた。
説教ばかりするサトじゃなく。
いっつもバカみたいに優しく笑って話を聞いてくれるたマスターが、オレの心の拠り所だった。
「『面倒見ますから、もうしばらくここにいさせてやってください』って……。
もちろん、あなたのためにってことよ?」
あの時、自分のことしか考えてなかった。
サトともうまくいかず、忙しいくらい仕事をこなす母さんに振り回されてる。
正直、もう居場所はないとさえ感じていた。
でも、今。
少し寂しそうに話す母さんを見て、そんなことはなかったんじゃないかと思う。
チビ助も、彼女のおじさんも。
お互いを助け合って、想いあってる。
オレと母さんは、少しだけ言葉足らずの似た者同士だから。
「…あら、ちょっと話がズレちゃったわね」
ぐずっと少しだけ鼻をすすった母さんは、あの頃を思い出したのか、ほんのり涙を浮かべていた。
それを目にしたら、胸がチクンと痛んだ。
「太一、あなたは自分で決められるの。
……だから、きちんと考えて答えてほしいのよ。今まで見たいに『これがイヤだから』とかではなくて」
離れていた距離と時間。
それは、こんなに冷静にも母さんをみれるようにしていた。
オレとしては、チビ助に出逢ったことが大きな要因だと思うけど。
どちらにしても、真正面からぶつかるいい機会なのかもしれない。
オレだって、いつまでもコドモじゃいられないんだ。
大きな深呼吸を一つ置いてから、オレはゆっくり口を開いた。
先生が…―ああ、今はマスターだったわね、ちょうどあたしが仕事でアメリカに行かなくちゃならなくなって、声をかけてくださったわ」
それは知っていた。
なんでも勝手に決めていく母さんがうざったくて、それがどうにもできないオレは勝手にふてくされていた。
説教ばかりするサトじゃなく。
いっつもバカみたいに優しく笑って話を聞いてくれるたマスターが、オレの心の拠り所だった。
「『面倒見ますから、もうしばらくここにいさせてやってください』って……。
もちろん、あなたのためにってことよ?」
あの時、自分のことしか考えてなかった。
サトともうまくいかず、忙しいくらい仕事をこなす母さんに振り回されてる。
正直、もう居場所はないとさえ感じていた。
でも、今。
少し寂しそうに話す母さんを見て、そんなことはなかったんじゃないかと思う。
チビ助も、彼女のおじさんも。
お互いを助け合って、想いあってる。
オレと母さんは、少しだけ言葉足らずの似た者同士だから。
「…あら、ちょっと話がズレちゃったわね」
ぐずっと少しだけ鼻をすすった母さんは、あの頃を思い出したのか、ほんのり涙を浮かべていた。
それを目にしたら、胸がチクンと痛んだ。
「太一、あなたは自分で決められるの。
……だから、きちんと考えて答えてほしいのよ。今まで見たいに『これがイヤだから』とかではなくて」
離れていた距離と時間。
それは、こんなに冷静にも母さんをみれるようにしていた。
オレとしては、チビ助に出逢ったことが大きな要因だと思うけど。
どちらにしても、真正面からぶつかるいい機会なのかもしれない。
オレだって、いつまでもコドモじゃいられないんだ。
大きな深呼吸を一つ置いてから、オレはゆっくり口を開いた。