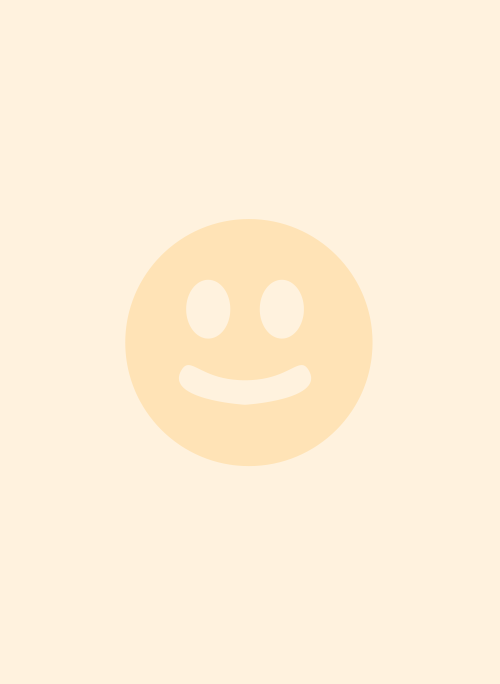「いい加減にしろよっ!
何が気にいらないのか知らないけど、アイツを傷つけることだけはオレが許さないから!」
握った拳が震えていて、コーヒーも波が立っていた。
そんなオレの強い視線にもひるまず、母さんは更に続けた。
「なにを言ってるの?
彼女もそうかもしれないけど、あなたにとっても『今』は人生を選択する大切な時なのよ?」
反論しようとしても、母さんはそれすらも許さないようにゆっくり口を開いた。
律儀な髪がけだるそうに揺れる。
「……あのね、太一。
あたしが言いたいのは、今までみたいにうまくいかないからって逃げてほしくないからよ」
「………っ!!」
ぽつりと、消えそうなほど小さな声でため息と一緒にはいた言葉。
だけど、オレを驚かせるのには十分だった。
顔をあげると、額に手を当てながら母さんは少し自嘲気味で笑っていた。
「サトちゃんのこと、好きだったんでしょう?」
母さんの声は、なぜか悔しいくらい優しく感じて。
恥ずかしいという気持ちもあったけど、どうして知っているのか…。
いや、少しでもオレのことを知っていたことに、どこか嬉しくもあったんだ。
「我が息子ながら情けないなぁ、と呆れてたわ」
当時を懐かしむかのように、クスリと笑いを零しながら母さんは淡々と話を進める。
時計の秒針が進む音しかない我が家。
淡々と母さんの声が響いて、一気に昔に戻ったように感じた。
何が気にいらないのか知らないけど、アイツを傷つけることだけはオレが許さないから!」
握った拳が震えていて、コーヒーも波が立っていた。
そんなオレの強い視線にもひるまず、母さんは更に続けた。
「なにを言ってるの?
彼女もそうかもしれないけど、あなたにとっても『今』は人生を選択する大切な時なのよ?」
反論しようとしても、母さんはそれすらも許さないようにゆっくり口を開いた。
律儀な髪がけだるそうに揺れる。
「……あのね、太一。
あたしが言いたいのは、今までみたいにうまくいかないからって逃げてほしくないからよ」
「………っ!!」
ぽつりと、消えそうなほど小さな声でため息と一緒にはいた言葉。
だけど、オレを驚かせるのには十分だった。
顔をあげると、額に手を当てながら母さんは少し自嘲気味で笑っていた。
「サトちゃんのこと、好きだったんでしょう?」
母さんの声は、なぜか悔しいくらい優しく感じて。
恥ずかしいという気持ちもあったけど、どうして知っているのか…。
いや、少しでもオレのことを知っていたことに、どこか嬉しくもあったんだ。
「我が息子ながら情けないなぁ、と呆れてたわ」
当時を懐かしむかのように、クスリと笑いを零しながら母さんは淡々と話を進める。
時計の秒針が進む音しかない我が家。
淡々と母さんの声が響いて、一気に昔に戻ったように感じた。