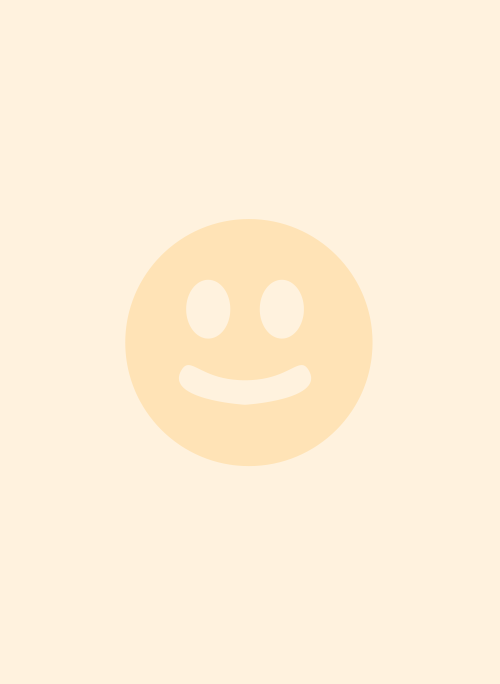本当にこれでよかったのだろうか。
いつまでたっても答えは出ないけど、時間ばかりが過ぎていくのを感じていた。
チビ助の涙が止まる頃、オレはようやく帰路に着いた。
自転車にまたがって振り返れば、寒い風に当たりながら見送るチビ助がいつも以上に寂しそうだった。
「……また、明日」
そういって無理やり笑ったチビ助に、いつものように手を振り返す。
車輪が勢いよく回る音を聞きながら、冷たい風を頬を切る。
そうでもしてないと、オレまで泣いてしまいそうだった。
がむしゃらに足を動かして、家に到着したときには身体がぽかぽかするくらい温まっていた。
足早に扉に手をかけると、案の定、腕を組んで不機嫌そうな人が待ち構えている。
「おかえり、太一」
射抜くような視線はここ最近では毎度のことだ。
「……ただいま」
玄関先にちょこんと座り込み、スニーカーの紐をといていると、これまた例のごとく小言が始まる。
「大体、今、何時だと思ってるの?先方がいくらご両親がいないからって…」
小ばかにしたような物言いに、オレはカチンと来た。
勢いよく振り返って睨みつけたけど、そういわれても仕方のないことをしているのは確かだ。
ちょっと前までのオレなら、ここで喫茶店にでも逃げ込んでいただろう。
オレを守ってくれるところに。
でも、今はオレが守ってやりたいんだ。
…チビ助を。
いつまでたっても答えは出ないけど、時間ばかりが過ぎていくのを感じていた。
チビ助の涙が止まる頃、オレはようやく帰路に着いた。
自転車にまたがって振り返れば、寒い風に当たりながら見送るチビ助がいつも以上に寂しそうだった。
「……また、明日」
そういって無理やり笑ったチビ助に、いつものように手を振り返す。
車輪が勢いよく回る音を聞きながら、冷たい風を頬を切る。
そうでもしてないと、オレまで泣いてしまいそうだった。
がむしゃらに足を動かして、家に到着したときには身体がぽかぽかするくらい温まっていた。
足早に扉に手をかけると、案の定、腕を組んで不機嫌そうな人が待ち構えている。
「おかえり、太一」
射抜くような視線はここ最近では毎度のことだ。
「……ただいま」
玄関先にちょこんと座り込み、スニーカーの紐をといていると、これまた例のごとく小言が始まる。
「大体、今、何時だと思ってるの?先方がいくらご両親がいないからって…」
小ばかにしたような物言いに、オレはカチンと来た。
勢いよく振り返って睨みつけたけど、そういわれても仕方のないことをしているのは確かだ。
ちょっと前までのオレなら、ここで喫茶店にでも逃げ込んでいただろう。
オレを守ってくれるところに。
でも、今はオレが守ってやりたいんだ。
…チビ助を。