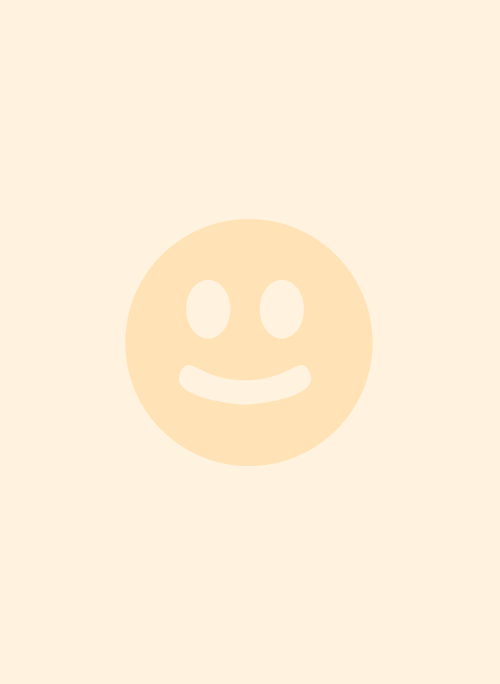「え、あの…?」
戸惑いを隠せていないごもる声に、予感が的中してしまったことを知らせた。
焦る一方、自転車のスタンドがうまくたたなくて、半ば捨てるように降りる。
フラフラなのにオレはひたすら足を動かして、もつれるように錆びた金属の階段を駆け上がる。
「失礼するわよ」
「あ、あの、太一さんなら……」
一歩、図々しくも玄関に踏み入ったその女の肩をようやく掴んで振り向かせる。
半身をねじった女の視線は見事、オレに向いた。
そして向こうも、背後からやってきたオレの姿に驚いていたようだ。
「…はぁ、はぁ…っ…、オレならここだよ…っ!」
肩で息をしながら、映し出されたのは電球の下で困ってる彼女の顔。
十分、怖がってるのが伝わる。
その女は一つため息をついて、腕を組んでオレを見上げてきた。
「学校にも家にもいないんだから」
年のわりには綺麗だけど、オレにはそんなの関係ない。
「なんっ、で…、ここ…っ!いきなり、なんだよ…っ!」
溢れる疑問が、次々に口から零れて日本語になっていなくて。
まだ荒い息で頭の整理がついていないオレに、少し下からの強い視線を浴びせてくる。
「いるはずの場所にいないんだから、探すに決まってるでしょう」
ピシャリと言い放ち、思わず口を紡いでしまったがそれでもオレは続けた。
戸惑いを隠せていないごもる声に、予感が的中してしまったことを知らせた。
焦る一方、自転車のスタンドがうまくたたなくて、半ば捨てるように降りる。
フラフラなのにオレはひたすら足を動かして、もつれるように錆びた金属の階段を駆け上がる。
「失礼するわよ」
「あ、あの、太一さんなら……」
一歩、図々しくも玄関に踏み入ったその女の肩をようやく掴んで振り向かせる。
半身をねじった女の視線は見事、オレに向いた。
そして向こうも、背後からやってきたオレの姿に驚いていたようだ。
「…はぁ、はぁ…っ…、オレならここだよ…っ!」
肩で息をしながら、映し出されたのは電球の下で困ってる彼女の顔。
十分、怖がってるのが伝わる。
その女は一つため息をついて、腕を組んでオレを見上げてきた。
「学校にも家にもいないんだから」
年のわりには綺麗だけど、オレにはそんなの関係ない。
「なんっ、で…、ここ…っ!いきなり、なんだよ…っ!」
溢れる疑問が、次々に口から零れて日本語になっていなくて。
まだ荒い息で頭の整理がついていないオレに、少し下からの強い視線を浴びせてくる。
「いるはずの場所にいないんだから、探すに決まってるでしょう」
ピシャリと言い放ち、思わず口を紡いでしまったがそれでもオレは続けた。