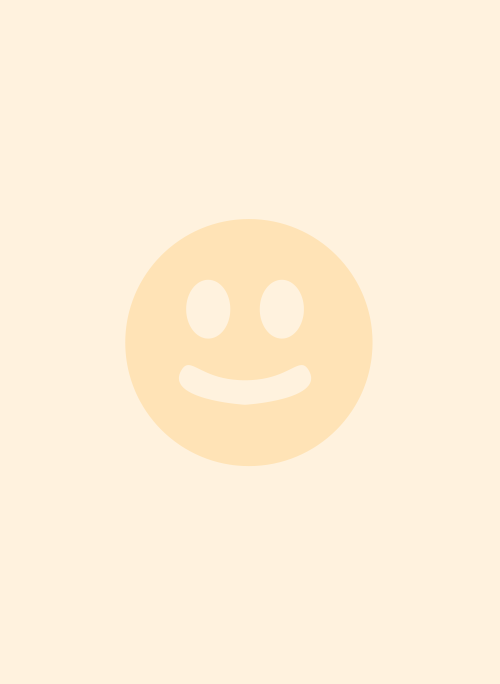教室にあがる階段を通り過ぎて、駅にある小さなコンビニのような購買部。
窓口は空いていなかったけど、向かい側にある自販機は顕在だ。
ポケットに忍ばせていた財布から小銭を抜いて、チャリンと音を鳴らせる。
迷わずオレはアイスコーヒー。
微糖でもないブラックだ。
「どれがいい?」
ランプが点滅してるボタンを食い入るように見つめるチビ助。
どこからか吹いてきた風に揺れるクセ毛。
「じゃあ、これ!」
その声にオレはびくっと手が震える。
オレの右手は、あの黒く二つに束ねられた髪に今にも触れそうな距離だった。
無邪気に拾い上げたチビ助の手には、ロイヤルミルクティーの缶が握られていた。
宙を彷徨った手を、慌ててズボンのポケットにしまいこむ。
一体、なにをしようとしていたんだろう…。
自分でもわからなかった。
特別教室の校舎を一通り案内し終わる頃は、ちょうど腹も減る頃だった。
Tシャツ姿の団体がちらほらオレたちと通りすがる。
おそらく部活も昼休憩を挟むころなんだろう。
そんな中、くぅぅとかわいそうな音が響いた。
後ろを振りかえると真っ赤な顔を隠すように俯いたチビ助。
無駄だと言うのに腹を押さえて必死に音を消そうとしている。
窓口は空いていなかったけど、向かい側にある自販機は顕在だ。
ポケットに忍ばせていた財布から小銭を抜いて、チャリンと音を鳴らせる。
迷わずオレはアイスコーヒー。
微糖でもないブラックだ。
「どれがいい?」
ランプが点滅してるボタンを食い入るように見つめるチビ助。
どこからか吹いてきた風に揺れるクセ毛。
「じゃあ、これ!」
その声にオレはびくっと手が震える。
オレの右手は、あの黒く二つに束ねられた髪に今にも触れそうな距離だった。
無邪気に拾い上げたチビ助の手には、ロイヤルミルクティーの缶が握られていた。
宙を彷徨った手を、慌ててズボンのポケットにしまいこむ。
一体、なにをしようとしていたんだろう…。
自分でもわからなかった。
特別教室の校舎を一通り案内し終わる頃は、ちょうど腹も減る頃だった。
Tシャツ姿の団体がちらほらオレたちと通りすがる。
おそらく部活も昼休憩を挟むころなんだろう。
そんな中、くぅぅとかわいそうな音が響いた。
後ろを振りかえると真っ赤な顔を隠すように俯いたチビ助。
無駄だと言うのに腹を押さえて必死に音を消そうとしている。