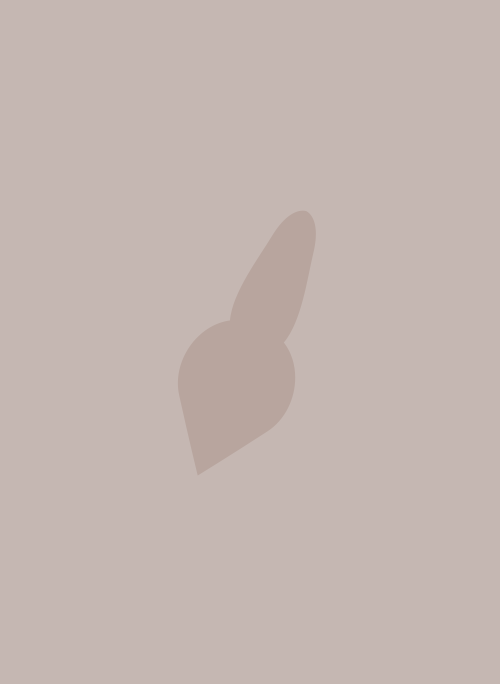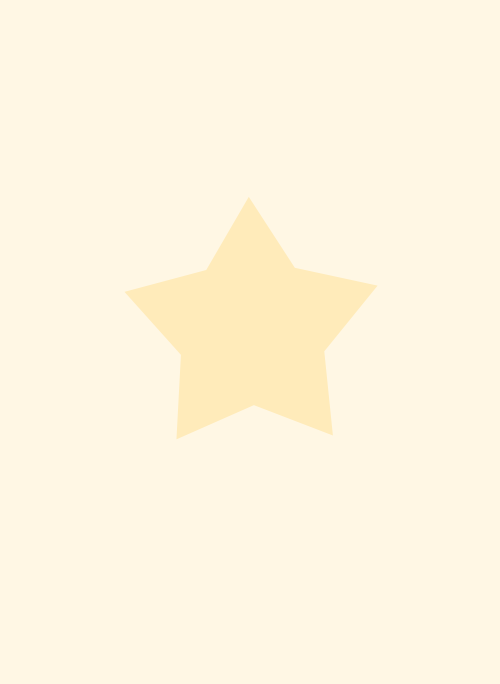「さてと、、、、今日も頑張らなきゃなあ。」 会社に来て予定表を捲ってみる。
「あらあら、吉田君。 今日は気合が入ってるわねえ。」 「そう見えますか?」
「いつもそれくらいだと嬉しいんだけどなあ。」 金沢さんはぼくを見てはニコッと笑う。
「頑張ってますけど。」なんて言おうものなら「あなたの何処が頑張ってるのよ? みんなそれくらいはやってるのよ。」って恐ろしいくらいに言い返されてしまう。
その金沢さんが笑っていたからホッとした。
朝から外勤である。 今日も疲れそうだなあ。
回る地域によっては留守が多いからチラシも多めに持っていかないとね。
おまけに昼飯も考えないとまずいんだよな。 いつだったか、コンビニすら無い地域を回っててフラフラになったことが有る。
あの時は金沢さんに助けてもらったんだ。 あのラーメンは美味かったなあ。
さてと、考えてる間に出発準備も出来たから行こうか。 まずは大野町だ。
この辺りは田んぼが多くて、居るのはほとんどがお年寄り。 心配だ。
ピンポーン。 やっぱり居ないらしい。
やっと出てきたと思ったらおばあちゃん。 「谷川という販売店の者ですが、、、。」
「米ならたくさん有るでな。 帰ってくれ。」 「米じゃなくて、、、。」
「分からんから帰ってくれ。」 問答無用らしい。
しょんぼりしながら歩いていると電話が掛かってきた。 「もしもし、、、。」
「その声は、、、。」 「雅子です。 お仕事中ですか?」
「今、大野町を回っているところですよ。」 「今晩、会えますか?」
「何か?」 「お話ししたいんです。 ぜひ来てください。」
電話は切れた。 どうしたらいいんだろう?
ぼくは車に戻ってきた。
昼飯をコンビニ弁当で済ませると動いている振りをして大竹アパートへ行ってみた。
二階へ上がると扉をノックする。 「来てくれたんですね?」
「暇が出来たから寄っただけです。 内緒ですよ。」 「構いません。 入って。」
雅子さんは愛想のいい顔でぼくを迎えてくれた。 これが不倫の始まりだったとは、、、。
「今日も旦那は帰ってこないんです。」 「いくら何でも帰ってくるでしょう?」
「新しい商談が決まりそうだから予定を延ばすって電話が掛かってきたんです。」 「仕事じゃしょうがないですよ。」
「でもね、それはいつものことなの。」 「え?」
「商談が決まっても仕事が増えたことは無いのよ。」 「それはおかしいな。」
「でしょうでしょう? おかしいんですよ。」 雅子は急にぼくのほうへ身を乗り出してきた。
「吉田さんって彼女は居ないんですよね?」 「居ません。」
「だったら、、、。」 雅子はぼくの腕を開くと覚悟を決めたように飛び込んできた。
「私を可愛がってくださいな。」 「ちょっと待って。 真昼間からこれはやばいよ。」
「いいじゃない。 今は誰も居ないわ。」 「だからって、、、。」
雅子はぼくの上に乗ってきた。 「抱かれたいの。 あの日みたいに。」
感極まったのか、雅子は泣き出してしまった。 ぼくにはどうすることも出来なくてただ抱き締めるしかなかった。
ややあって雅子は気が済んだのか、ぼくから離れた。 でも今度は「ごめんなさい。」って謝ってばかり。
涙目で必死に謝ってくるから許さないわけにもいかない。 「いいんです。 奥さんでもこんな時は有るんでしょうから。」
「分かってくださるんですね? 嬉しいわ。」 言うが早いか雅子はぼくにキスをしてきた。
うっとりした顔で舌を入れてくる雅子を拒めなくなっている。 (このままじゃあ会社に居られないぞ。)
「怖いですか?」 「いや、別に。」
「大丈夫。 ばれないようにするから。」 雅子はニコッと笑ってぼくを見る。
まるで気持ちを鷲掴みされた気分である。 部屋を出ても頭が熱い。
いや、体全部が火照っているようだ。 吹いてくる風がやけに冷たく感じる。
車で走っていても雅子さんのことを思い出してしまう。 営業部から電話が掛かってきても、、、。
「ま、、、いや谷岡さんですか?」 「おいおい、ま、、、、、はないだろう。」
「大野町はどうだった?」 「投げ込みはしましたけど反応は有りません。」
「そうだろうなあ。 あそこは昼間は年寄りしか居ないから。」 「そうですよね。」
「んでこれからどうするんだ?」 「日酒町に行きます。」
「おーおー、頑張れよ。」 電話は切れた。
(やばかったなあ。 ばれそうだったよ。) 冷や汗を拭きながらぼくはアクセルを踏み込んだ。
松田聖子のcdを聞きながら会社へ戻ってきた。 もう5時を過ぎている。
「あらあら、どうだった?」 「投げ込みはしたんですけど売れなくて、、、。」
「そうねえ。 見てもらえたらいつかは電話が掛かってくるわよ。」 金沢さんは書類を整理しながらぼくを見た。
「疲れたでしょう? ゆっくり休んでね。」 「ありがとうございます。 お先に失礼します。」
とはいうが、車に戻ってくると雅子さんのことを思い出してしまう。 「無理に甘えてしまってごめんなさいね。」
寂しく笑うあの笑顔を忘れられないんだ。
ぼくはまた大竹アパートへ車を走らせた。 裏側に回ってみるとベランダに雅子さんが出ていた。
思わず目が合ってしまったから心臓が破裂しそうである。 手招きすると雅子さんは急いで下りてきた。
ニコッと笑いかける雅子さん、、、そしてそれを見逃せなくなっているぼく、、、。
アパートの前に回ると青いワンピースの雅子さんは人目をはばかるように玄関から飛び出してきた。
「自分の車で良かった。」 「そうよね。」
小声で呟いたはずなのに雅子さんにはしっかりと聞かれていた。
「あらあら、吉田君。 今日は気合が入ってるわねえ。」 「そう見えますか?」
「いつもそれくらいだと嬉しいんだけどなあ。」 金沢さんはぼくを見てはニコッと笑う。
「頑張ってますけど。」なんて言おうものなら「あなたの何処が頑張ってるのよ? みんなそれくらいはやってるのよ。」って恐ろしいくらいに言い返されてしまう。
その金沢さんが笑っていたからホッとした。
朝から外勤である。 今日も疲れそうだなあ。
回る地域によっては留守が多いからチラシも多めに持っていかないとね。
おまけに昼飯も考えないとまずいんだよな。 いつだったか、コンビニすら無い地域を回っててフラフラになったことが有る。
あの時は金沢さんに助けてもらったんだ。 あのラーメンは美味かったなあ。
さてと、考えてる間に出発準備も出来たから行こうか。 まずは大野町だ。
この辺りは田んぼが多くて、居るのはほとんどがお年寄り。 心配だ。
ピンポーン。 やっぱり居ないらしい。
やっと出てきたと思ったらおばあちゃん。 「谷川という販売店の者ですが、、、。」
「米ならたくさん有るでな。 帰ってくれ。」 「米じゃなくて、、、。」
「分からんから帰ってくれ。」 問答無用らしい。
しょんぼりしながら歩いていると電話が掛かってきた。 「もしもし、、、。」
「その声は、、、。」 「雅子です。 お仕事中ですか?」
「今、大野町を回っているところですよ。」 「今晩、会えますか?」
「何か?」 「お話ししたいんです。 ぜひ来てください。」
電話は切れた。 どうしたらいいんだろう?
ぼくは車に戻ってきた。
昼飯をコンビニ弁当で済ませると動いている振りをして大竹アパートへ行ってみた。
二階へ上がると扉をノックする。 「来てくれたんですね?」
「暇が出来たから寄っただけです。 内緒ですよ。」 「構いません。 入って。」
雅子さんは愛想のいい顔でぼくを迎えてくれた。 これが不倫の始まりだったとは、、、。
「今日も旦那は帰ってこないんです。」 「いくら何でも帰ってくるでしょう?」
「新しい商談が決まりそうだから予定を延ばすって電話が掛かってきたんです。」 「仕事じゃしょうがないですよ。」
「でもね、それはいつものことなの。」 「え?」
「商談が決まっても仕事が増えたことは無いのよ。」 「それはおかしいな。」
「でしょうでしょう? おかしいんですよ。」 雅子は急にぼくのほうへ身を乗り出してきた。
「吉田さんって彼女は居ないんですよね?」 「居ません。」
「だったら、、、。」 雅子はぼくの腕を開くと覚悟を決めたように飛び込んできた。
「私を可愛がってくださいな。」 「ちょっと待って。 真昼間からこれはやばいよ。」
「いいじゃない。 今は誰も居ないわ。」 「だからって、、、。」
雅子はぼくの上に乗ってきた。 「抱かれたいの。 あの日みたいに。」
感極まったのか、雅子は泣き出してしまった。 ぼくにはどうすることも出来なくてただ抱き締めるしかなかった。
ややあって雅子は気が済んだのか、ぼくから離れた。 でも今度は「ごめんなさい。」って謝ってばかり。
涙目で必死に謝ってくるから許さないわけにもいかない。 「いいんです。 奥さんでもこんな時は有るんでしょうから。」
「分かってくださるんですね? 嬉しいわ。」 言うが早いか雅子はぼくにキスをしてきた。
うっとりした顔で舌を入れてくる雅子を拒めなくなっている。 (このままじゃあ会社に居られないぞ。)
「怖いですか?」 「いや、別に。」
「大丈夫。 ばれないようにするから。」 雅子はニコッと笑ってぼくを見る。
まるで気持ちを鷲掴みされた気分である。 部屋を出ても頭が熱い。
いや、体全部が火照っているようだ。 吹いてくる風がやけに冷たく感じる。
車で走っていても雅子さんのことを思い出してしまう。 営業部から電話が掛かってきても、、、。
「ま、、、いや谷岡さんですか?」 「おいおい、ま、、、、、はないだろう。」
「大野町はどうだった?」 「投げ込みはしましたけど反応は有りません。」
「そうだろうなあ。 あそこは昼間は年寄りしか居ないから。」 「そうですよね。」
「んでこれからどうするんだ?」 「日酒町に行きます。」
「おーおー、頑張れよ。」 電話は切れた。
(やばかったなあ。 ばれそうだったよ。) 冷や汗を拭きながらぼくはアクセルを踏み込んだ。
松田聖子のcdを聞きながら会社へ戻ってきた。 もう5時を過ぎている。
「あらあら、どうだった?」 「投げ込みはしたんですけど売れなくて、、、。」
「そうねえ。 見てもらえたらいつかは電話が掛かってくるわよ。」 金沢さんは書類を整理しながらぼくを見た。
「疲れたでしょう? ゆっくり休んでね。」 「ありがとうございます。 お先に失礼します。」
とはいうが、車に戻ってくると雅子さんのことを思い出してしまう。 「無理に甘えてしまってごめんなさいね。」
寂しく笑うあの笑顔を忘れられないんだ。
ぼくはまた大竹アパートへ車を走らせた。 裏側に回ってみるとベランダに雅子さんが出ていた。
思わず目が合ってしまったから心臓が破裂しそうである。 手招きすると雅子さんは急いで下りてきた。
ニコッと笑いかける雅子さん、、、そしてそれを見逃せなくなっているぼく、、、。
アパートの前に回ると青いワンピースの雅子さんは人目をはばかるように玄関から飛び出してきた。
「自分の車で良かった。」 「そうよね。」
小声で呟いたはずなのに雅子さんにはしっかりと聞かれていた。