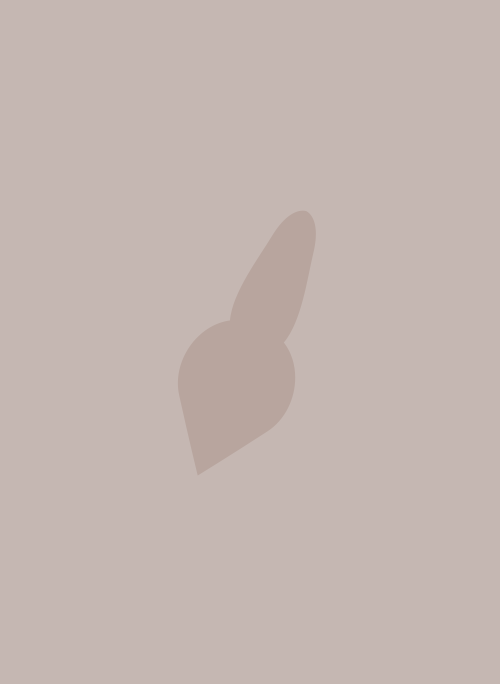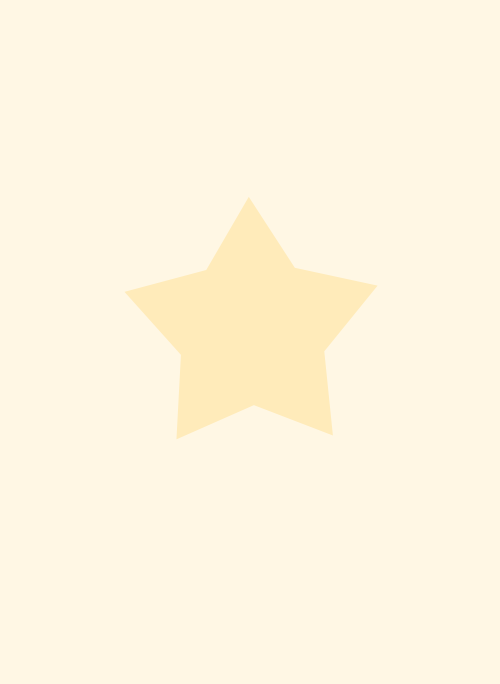「何だって? 礼子さんが倒れた?」 「そうなんだ。 急いで来てくれ。」
キャップ 植山孝彦も気が気ではない。 「宮城君の次は礼子さんか。」
ウェザーステーションに飛び込んでみると礼子は丸くなって黄色い泡を噴き続けている。 「まだ死んでないな。 心肺蘇生を、、、。」
植山が礼子の肋骨を押そうとした瞬間、不思議なくらいに肋骨が粉々になってしまった。 「なぜだ? 毒を飲まされたわけでもないのに骨が砕け散ってしまった。」
騒ぎを聞きつけた川嶋も事務所から飛んできたが、あまりの惨状に言葉が出ない。
「人間じゃないな。 得体の知れない何かが動いている。」 「何かって何です?」
「それが分かれば苦労しないよ。 超常現象なんて生易しい物でもないかもしれない。」 川島は礼子が吐き続ける黄色い泡を見詰めた。
「これは青酸カリなんかじゃないな。 もっと違う何かだ。」 「だから何かって何なんだよ?」
「分からん。 科学捜査をしてみないと、、、。」 彼は持ってきたビーカーにその泡を取り込んでみた。
ところが取り込んだ瞬間に泡が消えてしまった。 「これじゃあ手も足も出せないぞ。」
科学捜査班もこれには目を疑うしかない。 兎にも角にも礼子の死体を運び出さなければ、、、。
しかし誰かが掴んだ所から骨が砕けていく。 搬送すらままならないらしい。
そこへ騒ぎを聞きつけた渚がやってきた。 「どうしたんですか?」
「実は、、、。」 植山の話を一通り聞いた彼女は全員に退室するように求めてから死体と向き合った。
それから数分後、、、。 「蘇生しましたよ。」
何食わぬ顔で渚が出てきたものだから植山も川嶋も呆然として動けないでいる。 「蘇生しただって?」
ウェザーステーションに駆け付けてきた全ての人たちが信じられない顔で渚を見た。 「見てきてください。」
渚はいつもの笑顔で川嶋に伝えるとさっさと行ってしまった。
驚いたのは川嶋である。 部屋に飛び込むと確かに礼子が椅子に座ってぼんやりとしている。
「大丈夫なのか?」 「何が?」
「今まで黄色い泡を噴いて死んでたんだぞ。」 「死んでた? 私が?」
「そうだ。 確かに死んでいた。」 「嘘。 私はこの通り元気よ。」
その姿を見た植山も呆気に取られたように立ち尽くしている。 「確かに死んでいたのに、、、。」
「まあいい。 蘇ったんならそれでいいじゃないか。 なあ、みんな。」 「ま、まあ、、、。」
「それにしてもあの泡はどうなったんだ?」 「そういえばそうだが、、、。」
「しかしまあ礼子さんは元気だって言ってるんだ。 信じようじゃないか。」 笹尾だって気が気ではない。
「この事件は公表しないほうがいい。」 「そうですね。 超常現象とか心霊現象のマニアが騒ぎますから。」
「それだけじゃない。 マスコミ連中はただでさえ私を疑っているんだ。 関係者を殺しているんじゃないかとね。」 「マスコミ対策は何とかしましょう。」
川嶋は何となくやり切れない妙な気持になりながらコースを歩いている。 「次は誰だ?」
「ボス、鹿児島辺りで妙な殺気を感じます。」 「鹿児島?」
ジョーが地図を広げた。 「この島ですよ。」
「そこは俺が走ってたコースが有る島だ。」 「キャシーも何かを感じているかもしれないな。」
「それにしても黒武の動きが読めない。 あいつらは何をしたいんだ?」 「何もしたくはないよ。」
「誰だ?」 「霊キャプター諸君 いつか私と会う日が来るだろう。 それまでしっかり研鑽を積んでおくんだな。」
壁に映った黒い影はニヤッと笑ってから消えていった。 「あいつは?」
「羊怪ではないことは確かだ。 だがそれ以上は分からん。」 「いったい誰が?」
宮城とジョー、それにアーシーの三人が苦悶しているとジャスティーロバートが入ってきた。
「オー、ジャスティーじゃないか。 どうしたんだ?」 「いやいや、カリフォルニアで事務員の仕事をしていたんだが、妙な殺気を感じたから飛んできたんだ。」
「宮城、ジャスティーを紹介しよう。 彼は人の意識に入り込むことが出来る。 そして感情を思うままに動かせる男だ。 君の最大の仲間になるだろう。」 「ボス、よろしく。 ロバートって呼んでくれよ。」
「ありがとう。」 その時、ジョーが顔を歪めて苦しみ始めた。
「これはニューヨークの連中だな。 大事な時に何をしてくれるんだ!」 ロバートが念導力を込める。
「宮城、空間が歪んでいる。 気を付けるんだぞ!」 「分かってる。 少しだけ我慢してくれ!」
ロバートのバリアに宮城が力を加える。 「グァーーーーーーー!」
ジョーが床を転げ回っている。 「もう少しだ!」
ビル最上階の天井が敗れた。 「ジョー、大丈夫か?」
呻き続けていたジョーは死んだようにおとなしくなった。 「これはまだまだ序の口だな。 本気でやられたらこんなもんじゃない。」
「そういえばキャシーは何処に?」 「あいつならロンドンの協会と交信中だよ。」 「そうか。」
「それにしてもボス、鹿児島が大変なことになりそうだ。」 「それは分かっている。 しかしこれでは、、、。」
「行ってやってくれ。 羊怪が動いているようなんだ。」 「羊怪が? 分かった。」
それから三日後。 宮城は笹尾のコースに戻ってきた。
「すいません。 二度も三度も事故を起こしちゃって、、、。」 「それはいいんだが、体は大丈夫なのか?」
「精神的にやられてたみたいです。」 「そうか。 君もしばらくは休んだほうがいいな。」
「でも十分に休んだから大丈夫ですよ。」 と、通路で職員を罵る声が聞こえてきた。
「あれは?」 「マスコミの連中だよ。 君の事故以来、引っ付いて離れてくれないんだ。」
「行ってきましょうか。」 「君は出ないほうがいい。 騒ぎを大きくするだけだ。」
「しかしあれでは、、、。」 「最近では総務省が火消しに動いてくれている。 前よりはおとなしくなったんだ。」
そこへスプリンターフラッシュのメンテナンスをしていた渚が入ってきた。 「宮城さん、無事だったのね?」
「何とか助かったみたいだよ。 心配させちゃったね。」 「いいんです。 戻ってくれただけで、、、。」
そう言うと渚は部屋を出ていったが、何となく宮城は違和感を感じていた。 (いつもの渚じゃないな。)
何処か腑に落ちない顔をしている宮城に笹尾が笑いかけてきた。 「久しぶりに会ったんだろう? 吉田さんも緊張してるんだよ。」
「そうかな?」 「まだ若いんだ。 いいねえ、若いって。」
しかし宮城は気付いていた。 渚が当たらず触らずで自分を避けていることに。
(何か有るぞ。) 彼はまたコースに出てみた。
メンテナンスブースにはスプリンターフラッシュの3号車が用意されていた。 こいつにはドライブレコーダーや赤外線探知機が備え付けられている。
エンジンもこれまでにはない強力な物が載せられている。 パワーライトもかなり強力らしい。
「ずいぶんと拘ったね。」 「そりゃそうですよ。 二度と事故を起こさないためにも、、、。」
「乗ってみたいな。」 「乗るんですか? エンジンは三弾起動ですからね。」
ブース管理者の吉村文博がキーを渡す。 f1並みだ。
「こいつはレーシングカーをモデルに作ってもらってたんです。 3年前から研究してたやつですよ。」 「話には聞いてたんだ。 渚も自信作だって言ってたくらいだから。」
宮城がエンジンを起動する。 コース中に爆音が轟き渡る。
ブースからコースへ出ていく。 慌てたように監視ヘリが飛び立った。
「今度は何も起きないでくれよ。」 川嶋も管理センターから見守っている。
「速度は順調。 現在150キロ。」 「了解。」
笹尾は展望台からコースを見下ろしている。 あの絶壁が真正面に見える場所だ。
「今回は何も起きなければいいんだが、、、、。」 「大丈夫ですよ。 笹尾さん。」
「吉田さん。 なぜ言い切れるんだ? これまで事故が続いているのに。」 「私にも分かりません。 でも大丈夫です。」
その自信が何処から来るのか笹尾には分らなかった。
キャップ 植山孝彦も気が気ではない。 「宮城君の次は礼子さんか。」
ウェザーステーションに飛び込んでみると礼子は丸くなって黄色い泡を噴き続けている。 「まだ死んでないな。 心肺蘇生を、、、。」
植山が礼子の肋骨を押そうとした瞬間、不思議なくらいに肋骨が粉々になってしまった。 「なぜだ? 毒を飲まされたわけでもないのに骨が砕け散ってしまった。」
騒ぎを聞きつけた川嶋も事務所から飛んできたが、あまりの惨状に言葉が出ない。
「人間じゃないな。 得体の知れない何かが動いている。」 「何かって何です?」
「それが分かれば苦労しないよ。 超常現象なんて生易しい物でもないかもしれない。」 川島は礼子が吐き続ける黄色い泡を見詰めた。
「これは青酸カリなんかじゃないな。 もっと違う何かだ。」 「だから何かって何なんだよ?」
「分からん。 科学捜査をしてみないと、、、。」 彼は持ってきたビーカーにその泡を取り込んでみた。
ところが取り込んだ瞬間に泡が消えてしまった。 「これじゃあ手も足も出せないぞ。」
科学捜査班もこれには目を疑うしかない。 兎にも角にも礼子の死体を運び出さなければ、、、。
しかし誰かが掴んだ所から骨が砕けていく。 搬送すらままならないらしい。
そこへ騒ぎを聞きつけた渚がやってきた。 「どうしたんですか?」
「実は、、、。」 植山の話を一通り聞いた彼女は全員に退室するように求めてから死体と向き合った。
それから数分後、、、。 「蘇生しましたよ。」
何食わぬ顔で渚が出てきたものだから植山も川嶋も呆然として動けないでいる。 「蘇生しただって?」
ウェザーステーションに駆け付けてきた全ての人たちが信じられない顔で渚を見た。 「見てきてください。」
渚はいつもの笑顔で川嶋に伝えるとさっさと行ってしまった。
驚いたのは川嶋である。 部屋に飛び込むと確かに礼子が椅子に座ってぼんやりとしている。
「大丈夫なのか?」 「何が?」
「今まで黄色い泡を噴いて死んでたんだぞ。」 「死んでた? 私が?」
「そうだ。 確かに死んでいた。」 「嘘。 私はこの通り元気よ。」
その姿を見た植山も呆気に取られたように立ち尽くしている。 「確かに死んでいたのに、、、。」
「まあいい。 蘇ったんならそれでいいじゃないか。 なあ、みんな。」 「ま、まあ、、、。」
「それにしてもあの泡はどうなったんだ?」 「そういえばそうだが、、、。」
「しかしまあ礼子さんは元気だって言ってるんだ。 信じようじゃないか。」 笹尾だって気が気ではない。
「この事件は公表しないほうがいい。」 「そうですね。 超常現象とか心霊現象のマニアが騒ぎますから。」
「それだけじゃない。 マスコミ連中はただでさえ私を疑っているんだ。 関係者を殺しているんじゃないかとね。」 「マスコミ対策は何とかしましょう。」
川嶋は何となくやり切れない妙な気持になりながらコースを歩いている。 「次は誰だ?」
「ボス、鹿児島辺りで妙な殺気を感じます。」 「鹿児島?」
ジョーが地図を広げた。 「この島ですよ。」
「そこは俺が走ってたコースが有る島だ。」 「キャシーも何かを感じているかもしれないな。」
「それにしても黒武の動きが読めない。 あいつらは何をしたいんだ?」 「何もしたくはないよ。」
「誰だ?」 「霊キャプター諸君 いつか私と会う日が来るだろう。 それまでしっかり研鑽を積んでおくんだな。」
壁に映った黒い影はニヤッと笑ってから消えていった。 「あいつは?」
「羊怪ではないことは確かだ。 だがそれ以上は分からん。」 「いったい誰が?」
宮城とジョー、それにアーシーの三人が苦悶しているとジャスティーロバートが入ってきた。
「オー、ジャスティーじゃないか。 どうしたんだ?」 「いやいや、カリフォルニアで事務員の仕事をしていたんだが、妙な殺気を感じたから飛んできたんだ。」
「宮城、ジャスティーを紹介しよう。 彼は人の意識に入り込むことが出来る。 そして感情を思うままに動かせる男だ。 君の最大の仲間になるだろう。」 「ボス、よろしく。 ロバートって呼んでくれよ。」
「ありがとう。」 その時、ジョーが顔を歪めて苦しみ始めた。
「これはニューヨークの連中だな。 大事な時に何をしてくれるんだ!」 ロバートが念導力を込める。
「宮城、空間が歪んでいる。 気を付けるんだぞ!」 「分かってる。 少しだけ我慢してくれ!」
ロバートのバリアに宮城が力を加える。 「グァーーーーーーー!」
ジョーが床を転げ回っている。 「もう少しだ!」
ビル最上階の天井が敗れた。 「ジョー、大丈夫か?」
呻き続けていたジョーは死んだようにおとなしくなった。 「これはまだまだ序の口だな。 本気でやられたらこんなもんじゃない。」
「そういえばキャシーは何処に?」 「あいつならロンドンの協会と交信中だよ。」 「そうか。」
「それにしてもボス、鹿児島が大変なことになりそうだ。」 「それは分かっている。 しかしこれでは、、、。」
「行ってやってくれ。 羊怪が動いているようなんだ。」 「羊怪が? 分かった。」
それから三日後。 宮城は笹尾のコースに戻ってきた。
「すいません。 二度も三度も事故を起こしちゃって、、、。」 「それはいいんだが、体は大丈夫なのか?」
「精神的にやられてたみたいです。」 「そうか。 君もしばらくは休んだほうがいいな。」
「でも十分に休んだから大丈夫ですよ。」 と、通路で職員を罵る声が聞こえてきた。
「あれは?」 「マスコミの連中だよ。 君の事故以来、引っ付いて離れてくれないんだ。」
「行ってきましょうか。」 「君は出ないほうがいい。 騒ぎを大きくするだけだ。」
「しかしあれでは、、、。」 「最近では総務省が火消しに動いてくれている。 前よりはおとなしくなったんだ。」
そこへスプリンターフラッシュのメンテナンスをしていた渚が入ってきた。 「宮城さん、無事だったのね?」
「何とか助かったみたいだよ。 心配させちゃったね。」 「いいんです。 戻ってくれただけで、、、。」
そう言うと渚は部屋を出ていったが、何となく宮城は違和感を感じていた。 (いつもの渚じゃないな。)
何処か腑に落ちない顔をしている宮城に笹尾が笑いかけてきた。 「久しぶりに会ったんだろう? 吉田さんも緊張してるんだよ。」
「そうかな?」 「まだ若いんだ。 いいねえ、若いって。」
しかし宮城は気付いていた。 渚が当たらず触らずで自分を避けていることに。
(何か有るぞ。) 彼はまたコースに出てみた。
メンテナンスブースにはスプリンターフラッシュの3号車が用意されていた。 こいつにはドライブレコーダーや赤外線探知機が備え付けられている。
エンジンもこれまでにはない強力な物が載せられている。 パワーライトもかなり強力らしい。
「ずいぶんと拘ったね。」 「そりゃそうですよ。 二度と事故を起こさないためにも、、、。」
「乗ってみたいな。」 「乗るんですか? エンジンは三弾起動ですからね。」
ブース管理者の吉村文博がキーを渡す。 f1並みだ。
「こいつはレーシングカーをモデルに作ってもらってたんです。 3年前から研究してたやつですよ。」 「話には聞いてたんだ。 渚も自信作だって言ってたくらいだから。」
宮城がエンジンを起動する。 コース中に爆音が轟き渡る。
ブースからコースへ出ていく。 慌てたように監視ヘリが飛び立った。
「今度は何も起きないでくれよ。」 川嶋も管理センターから見守っている。
「速度は順調。 現在150キロ。」 「了解。」
笹尾は展望台からコースを見下ろしている。 あの絶壁が真正面に見える場所だ。
「今回は何も起きなければいいんだが、、、、。」 「大丈夫ですよ。 笹尾さん。」
「吉田さん。 なぜ言い切れるんだ? これまで事故が続いているのに。」 「私にも分かりません。 でも大丈夫です。」
その自信が何処から来るのか笹尾には分らなかった。