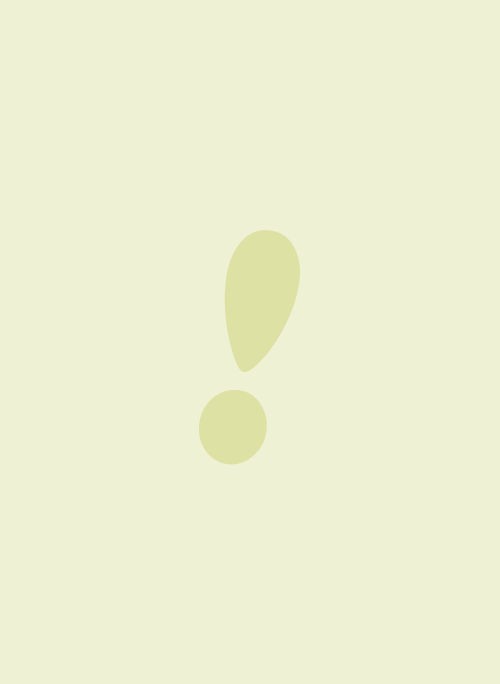相変わらずの眼鏡女子だ。 それに読んでいるのは小説。
「私ね、小説だけじゃなくて童話とか詩集も読んでるのよ。」 「そうなんだ?」
折原さんはニコッと笑うと一冊の本を机から取り出した。 それは金子みすゞの童謡集だった。
「へえ、こんなのも読んでるんだ。」 「金子みすゞってすごいと思うんだ。 あの表現力は、、、。」
「読んでみてもいいかな?」 「いいわよ。 貸してあげる。」
そこへ勉たちがドヤドヤット戻ってきた。 「あーーーら、お二人さん 邪魔しちゃったわねえ。」
つかさがいつものようにケラケラと笑っている。 「それは無いだろう? ボケ。」
「うわ、女子に向かってボケだってーーーー。 ひどーーーーーーい。」 「騒ぎ過ぎだよ。 ひょっとこ女。」
「何ヨ! 金太郎飴。」
「おいおい、訳の分からん喧嘩をするんじゃねえよ。」
「勉君が悪いのよ。」 「お前が余計なことを言うからだろう?」
「まあまあ、静かにしてよ。 灰原君だって本を読んでるんだから。」 「図書委員のお前は読まないのにか?」
いつ見ても仲良しで仲が悪い同級生たちだ。 卒業したらどうなるんだろうなあ?
「よし。 今日は全て終わった。 寄り道なんかしないで真っ直ぐに帰るんだぞ。」 担任も今日は噴火しないらしい。
ぼくらは昇降口へ出てきた。 「さあて、電車組の皆さん 駅まで競争だあ。」
「勝手にやってろ。」 「優しくないなあ。 たまには付き合ってよ。」
「お前に付き合ってる暇は無いんだよ。 タコ。」 いつもいつもこんな感じ。
寮へ帰る人たちはいつの間にかグループになって話しながら行ってしまった。 ぼくはというと、校門の裏に植えてある木が気になって見惚れている。
「これ、桜だね。」 そこへ折原さんがやってきた。
「ここの校長先生が好きな木を植えたんだって。」 「何で知ってるの?」
「ホームページを読んだのよ。 そこに書いてあったわ。」 「そうか。 ホームページか。」
「灰原君はネットなんて見ないの?」 「見ないことは無いんだ。 でもさ、学校のホームページなんて、、、。」
「そうだよねえ。 やっぱり私って変わってるのかな?」 「どうだろう? 学校のホームページまで見る人は居るのかな?」
花が散った後の桜は何となく寂しく見えるものだ。 ぼくはまた入学式の時を思い出した。
あの日、折原さんはぼくの隣に座っていた。 前を向いたままで身動き一つしない。
咳すらしない。 それでよく耐えられるな、、、。
ぼくは不思議だった。 そんな折原さんと話してるんだ。
「そろそろ行きましょうか。」 時計を見ながら折原さんが歩き始めた。
静かな校舎を出て通りを歩いていく。 数歩先を折原さんが歩いていく。
車が引っ切り無しに走って行く。 そんなに急いで何処へ行くんだろう?
ふと父さんの会社の車が横切って行った。 (父さんも働いてるんだなあ。)
駅までの道を何も話さずに折原さんと並んで歩く。 電車組の他の人たちはもう駅に行っている。
空が暗くなってきた。 「雨 降るんだなあ。」
折原さんはカバンから折り畳み傘を取り出した。 ぼくは、、、。
「灰原君って友達は居るの?」 「ああ、つかさとか勉たちはみんな小学校からの友達だよ。」
「そっか。 私さあ、中学までみんなとは別だったから誰も知らないんだよね。 友達になってくれる?」 「いいよ。」
「ありがとう。 やっと話せた。」 なんか嬉しそう。
駅のほうでは通学組が先を争って改札を抜けようとしている。 ぼくらはそれを見ながらゆっくり歩いてきた。
「雨、降らなかったね。」 「そうでもないかも。 降りたら振ってるかもよ。」
「そりゃ大変だ。 傘を持ってないんだから。」 「じゃあ、これを貸してあげる。」
「いいよいいよ。 駅を降りればすぐだから。」 ぼくはなぜか恥ずかしくて改札を走り抜けた。 ホームに出て額の汗を拭っていると向かい側で折原さんが笑っているのが見えた。
「明日も元気に会おうねえ!」 「あいよ!」
互いに電車が入ってきて姿が見えなくなると窓際に駆け寄ってみた。 折原さんも同じことを考えていたらしい。
乗客が少なかったからぼくらは窓に顔を押し当てて発車するまで互いに顔を見合わせていたんだ。
電車が動き出して離れてしまうとなぜかぼくは寂しくなって座席に座り込んだ。 遠くで誰かが言い合いをしている。
スマホを開いて何かを見ている人も居る。 ぼくは流れていく景色をぼんやりと見詰めている。
線路の向こう側には大きな通りが有って特急バスなんかも走っている。 観光地に繋がっているからか、外人を乗せた観光バスもよく見掛ける。
その道路沿いには【プレーランド大島】っていうゲーセンが有って、今でもなぜか人気のスポットになっている。
何でもスマホを使ってアプリ連動型のゲームを楽しめるらしい。 相沢とか馬宮たちが入り浸っているって聞いたことが有るね。
電車は走っている。 とスマホが鳴った。
(誰だろう?)と思ったらメールだ。 開いてみたら彩葉からだった。
『健太君、国語で分からないことが有るから教えてほしいんだ。』
簡単なメールだけどやっぱりドキドキする。 そりゃあずっと一緒に居たんだからさ。
『分かった。 今は電車の中だから家に帰ったら寄るよ。』
そう返して家に帰ってきた。 「お帰り無さーーーーーーい。」
小学生の妹がお菓子を食べながらテレビを見ている。 「ちょっと出掛けてくるよ。」
「何処に行くの?」 「彩葉んちだよ。」
「そっか。 お土産買ってきてね。」 「何でだよ?」
「えーーーー? こんな可愛い妹にお土産も買ってこないなんてずるーーーーーい。」
ぼくはその声を聴きながら再び玄関を出て行った。
ポツリポツリと雨が降り始めていた。 そんなに激しくは無さそうだけど、、、。
(折原さんが言ったとおりだな。) ぼくは苦笑しながら傘を持った。 そして途中に在るコンビニに寄るとアイスを買った。
「こんにちはーーーー!」 「はーい。 ああ、健太君ね。」
お母さんはいつものようにドアを開けると階段下から彩葉に声を掛ける。 「はーい。」
いつものように元気そうな返事が返ってきた。 「今日もよろしくね。」
お母さんはそれだけ言うとお店のほうに行ってしまった。
部屋に入ってみると彩葉は国語の教科書を開いて苦しんでいる所だった。
「あれ? まだまだゆっくりしてもいいんじゃないの?」 「そうは思ったけどさ、自分でやってかないといけないから早めにやってしまおうと思って。」
「焦り過ぎだよ。 ぼくらだってまだまだ授業は始まってないんだから。」 「そうだろうなとは思ったけどさ、、、。」
ぼくは話しながらコンビニで買ったアイスをテーブルに置いた。 「一緒に食べよう。」
「いいの?」 「いいよ。 久しぶりだしさ、ゆっくり話したいなと思ってたから。」
それからぼくらは高校の様子とか担任の話とか、つかさたちのこととか話し合ったんだ。 「つかさちゃん、やっぱり変わってないなあ。」
「そうなんだ。 相変わらずうるさくてさあ。」 「いろんなことをやってもらったなあ。」
「そうだよね。 あいつ、大人に成ったらどんな女になるんだろう?」 「さあねえ。 キャリアウーマンかもよ。」
「彩葉は?」 「そうだなあ。 グラフィックデザイナーにでもなれたらいいなあ。」
「やれるんじゃないの? 彩葉は子供の頃から絵が好きだったし。」 「でもさあ、、、。」
雨は激しくなってきた。 「帰りは大丈夫なの?」
「傘は持ってきたから大丈夫だよ。」 「お父さんに送ってもらおうか?」
「大丈夫。 また来るから。」 傘をさすとぼくは家を出て行った。
「私ね、小説だけじゃなくて童話とか詩集も読んでるのよ。」 「そうなんだ?」
折原さんはニコッと笑うと一冊の本を机から取り出した。 それは金子みすゞの童謡集だった。
「へえ、こんなのも読んでるんだ。」 「金子みすゞってすごいと思うんだ。 あの表現力は、、、。」
「読んでみてもいいかな?」 「いいわよ。 貸してあげる。」
そこへ勉たちがドヤドヤット戻ってきた。 「あーーーら、お二人さん 邪魔しちゃったわねえ。」
つかさがいつものようにケラケラと笑っている。 「それは無いだろう? ボケ。」
「うわ、女子に向かってボケだってーーーー。 ひどーーーーーーい。」 「騒ぎ過ぎだよ。 ひょっとこ女。」
「何ヨ! 金太郎飴。」
「おいおい、訳の分からん喧嘩をするんじゃねえよ。」
「勉君が悪いのよ。」 「お前が余計なことを言うからだろう?」
「まあまあ、静かにしてよ。 灰原君だって本を読んでるんだから。」 「図書委員のお前は読まないのにか?」
いつ見ても仲良しで仲が悪い同級生たちだ。 卒業したらどうなるんだろうなあ?
「よし。 今日は全て終わった。 寄り道なんかしないで真っ直ぐに帰るんだぞ。」 担任も今日は噴火しないらしい。
ぼくらは昇降口へ出てきた。 「さあて、電車組の皆さん 駅まで競争だあ。」
「勝手にやってろ。」 「優しくないなあ。 たまには付き合ってよ。」
「お前に付き合ってる暇は無いんだよ。 タコ。」 いつもいつもこんな感じ。
寮へ帰る人たちはいつの間にかグループになって話しながら行ってしまった。 ぼくはというと、校門の裏に植えてある木が気になって見惚れている。
「これ、桜だね。」 そこへ折原さんがやってきた。
「ここの校長先生が好きな木を植えたんだって。」 「何で知ってるの?」
「ホームページを読んだのよ。 そこに書いてあったわ。」 「そうか。 ホームページか。」
「灰原君はネットなんて見ないの?」 「見ないことは無いんだ。 でもさ、学校のホームページなんて、、、。」
「そうだよねえ。 やっぱり私って変わってるのかな?」 「どうだろう? 学校のホームページまで見る人は居るのかな?」
花が散った後の桜は何となく寂しく見えるものだ。 ぼくはまた入学式の時を思い出した。
あの日、折原さんはぼくの隣に座っていた。 前を向いたままで身動き一つしない。
咳すらしない。 それでよく耐えられるな、、、。
ぼくは不思議だった。 そんな折原さんと話してるんだ。
「そろそろ行きましょうか。」 時計を見ながら折原さんが歩き始めた。
静かな校舎を出て通りを歩いていく。 数歩先を折原さんが歩いていく。
車が引っ切り無しに走って行く。 そんなに急いで何処へ行くんだろう?
ふと父さんの会社の車が横切って行った。 (父さんも働いてるんだなあ。)
駅までの道を何も話さずに折原さんと並んで歩く。 電車組の他の人たちはもう駅に行っている。
空が暗くなってきた。 「雨 降るんだなあ。」
折原さんはカバンから折り畳み傘を取り出した。 ぼくは、、、。
「灰原君って友達は居るの?」 「ああ、つかさとか勉たちはみんな小学校からの友達だよ。」
「そっか。 私さあ、中学までみんなとは別だったから誰も知らないんだよね。 友達になってくれる?」 「いいよ。」
「ありがとう。 やっと話せた。」 なんか嬉しそう。
駅のほうでは通学組が先を争って改札を抜けようとしている。 ぼくらはそれを見ながらゆっくり歩いてきた。
「雨、降らなかったね。」 「そうでもないかも。 降りたら振ってるかもよ。」
「そりゃ大変だ。 傘を持ってないんだから。」 「じゃあ、これを貸してあげる。」
「いいよいいよ。 駅を降りればすぐだから。」 ぼくはなぜか恥ずかしくて改札を走り抜けた。 ホームに出て額の汗を拭っていると向かい側で折原さんが笑っているのが見えた。
「明日も元気に会おうねえ!」 「あいよ!」
互いに電車が入ってきて姿が見えなくなると窓際に駆け寄ってみた。 折原さんも同じことを考えていたらしい。
乗客が少なかったからぼくらは窓に顔を押し当てて発車するまで互いに顔を見合わせていたんだ。
電車が動き出して離れてしまうとなぜかぼくは寂しくなって座席に座り込んだ。 遠くで誰かが言い合いをしている。
スマホを開いて何かを見ている人も居る。 ぼくは流れていく景色をぼんやりと見詰めている。
線路の向こう側には大きな通りが有って特急バスなんかも走っている。 観光地に繋がっているからか、外人を乗せた観光バスもよく見掛ける。
その道路沿いには【プレーランド大島】っていうゲーセンが有って、今でもなぜか人気のスポットになっている。
何でもスマホを使ってアプリ連動型のゲームを楽しめるらしい。 相沢とか馬宮たちが入り浸っているって聞いたことが有るね。
電車は走っている。 とスマホが鳴った。
(誰だろう?)と思ったらメールだ。 開いてみたら彩葉からだった。
『健太君、国語で分からないことが有るから教えてほしいんだ。』
簡単なメールだけどやっぱりドキドキする。 そりゃあずっと一緒に居たんだからさ。
『分かった。 今は電車の中だから家に帰ったら寄るよ。』
そう返して家に帰ってきた。 「お帰り無さーーーーーーい。」
小学生の妹がお菓子を食べながらテレビを見ている。 「ちょっと出掛けてくるよ。」
「何処に行くの?」 「彩葉んちだよ。」
「そっか。 お土産買ってきてね。」 「何でだよ?」
「えーーーー? こんな可愛い妹にお土産も買ってこないなんてずるーーーーーい。」
ぼくはその声を聴きながら再び玄関を出て行った。
ポツリポツリと雨が降り始めていた。 そんなに激しくは無さそうだけど、、、。
(折原さんが言ったとおりだな。) ぼくは苦笑しながら傘を持った。 そして途中に在るコンビニに寄るとアイスを買った。
「こんにちはーーーー!」 「はーい。 ああ、健太君ね。」
お母さんはいつものようにドアを開けると階段下から彩葉に声を掛ける。 「はーい。」
いつものように元気そうな返事が返ってきた。 「今日もよろしくね。」
お母さんはそれだけ言うとお店のほうに行ってしまった。
部屋に入ってみると彩葉は国語の教科書を開いて苦しんでいる所だった。
「あれ? まだまだゆっくりしてもいいんじゃないの?」 「そうは思ったけどさ、自分でやってかないといけないから早めにやってしまおうと思って。」
「焦り過ぎだよ。 ぼくらだってまだまだ授業は始まってないんだから。」 「そうだろうなとは思ったけどさ、、、。」
ぼくは話しながらコンビニで買ったアイスをテーブルに置いた。 「一緒に食べよう。」
「いいの?」 「いいよ。 久しぶりだしさ、ゆっくり話したいなと思ってたから。」
それからぼくらは高校の様子とか担任の話とか、つかさたちのこととか話し合ったんだ。 「つかさちゃん、やっぱり変わってないなあ。」
「そうなんだ。 相変わらずうるさくてさあ。」 「いろんなことをやってもらったなあ。」
「そうだよね。 あいつ、大人に成ったらどんな女になるんだろう?」 「さあねえ。 キャリアウーマンかもよ。」
「彩葉は?」 「そうだなあ。 グラフィックデザイナーにでもなれたらいいなあ。」
「やれるんじゃないの? 彩葉は子供の頃から絵が好きだったし。」 「でもさあ、、、。」
雨は激しくなってきた。 「帰りは大丈夫なの?」
「傘は持ってきたから大丈夫だよ。」 「お父さんに送ってもらおうか?」
「大丈夫。 また来るから。」 傘をさすとぼくは家を出て行った。