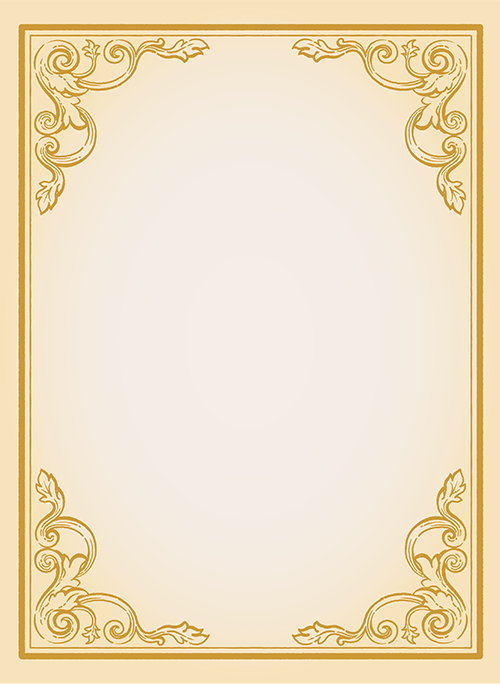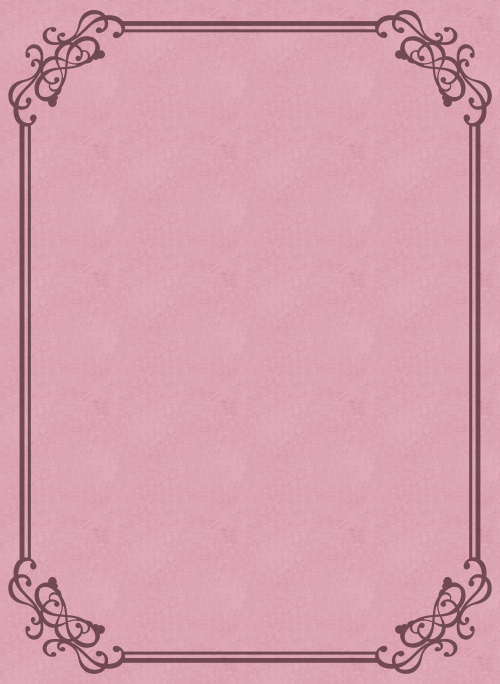ティアリーゼの浮かべる表情は寂しげで、満たされた日々の中にある令嬢とはとても思えない程。
(彼女のことを知らない僕が、憶測するべきではないけれど……)
様子を窺っていると、更に誰かの気配がし、ユリウスは更に身を潜めた。
「ティアリーゼ様っ」
「あっ……」
「お茶のご用意をしていましたら、お姿が見えなくなったので、驚いてしまいましたわ」
侍女の一人がティアリーゼを迎えに来たらしい。
「ごめんなさい、あまりにも薔薇が綺麗に咲いていて、つい奥まで来てしまいました」
「今度からは一声掛けて下さいませ」
「申し訳ありません」
その時、ティアリーゼと侍女の斜め後ろの植え込みから、がさりと音がした。
こっそり場を離れようとしたが意に反し、つい音を立ててしまったユリウスへ、二人の視線が注がれる。
「あら、リドリス殿下?」
「リドリス殿下、ごきげんよう」
突然のリドリスの登場に虚を突かれていたが、二人はすぐに淑女の礼をした。
(しまった、気になって物陰から見ていたとは言えないな……)
「偶然通りかかって」
「そうだったのですね、今からお茶の時間なのですが、リドリス殿下もご一緒にいかがですか?」
無下には断れず、そのままユリウスはティアリーゼと庭園でお茶をする運びとなった。
鮮やかな花々に囲まれ、白の丸テーブルを挟んでユリウスは、ティアリーゼと向かい合う。テーブルと揃いの、優雅な曲線を描く白の椅子に二人は腰掛ける。
お茶を淹れる侍女の手元を終始じっと見つめているティアリーゼを、ユリウスは不躾にならない程度に観察していた。
(侍女がお茶を淹れる場面なんて、珍しくもないと思うけど……?)
「天気もいいし、花もとても綺麗だね」
ユリウスは当たり障りのない言葉を紡いだ。
「はい、流石王宮の庭師のお仕事は大変素晴らしいですわ」
「ティアリーゼは職人や仕事をしている人を気にしているようだね。さっきも侍女の手元を注視していたし」
「はい、お茶を淹れる所作がとても綺麗で……わたしもあんな風に……」
言い掛け、ティアリーゼは慌てて顔を上げる。
「すみません、なんでもございません」
「謝らなくていいよ。ただ少し気になっただけだから」
ユリウスの優しげな眼差しに、ティアリーゼも落ち着きを取り戻す。
「興味があると言いますか、働いている方々のことを尊敬しております。わたしなど、何も出来ることがなくて……」
王都の令嬢と言えば、流行のドレスや宝飾品の事ばかりを気にするものだと思っていた。
ティアリーゼのように熱心に使用人に目を向けたりもする令嬢もいるのかと、意外な発見だった。
お陰でユリウスの中に誤算が生じてしまう。
ティアリーゼが気になって仕方がない。
いくら髪や瞳の色を似せた所で、リドリスと多くの時間を共に過ごした筈の彼女には、偽物だと気付かれてしまもしれない。
不必要にティアリーゼとの接触はしない筈だったのに。
数日後──
(参った、また会えるかもしれないと思って足を運んでしまったものの……)
ユリウスはティアリーゼが王宮に来る予定の日に、庭園に足を運ぶと、その姿を探した。
すると、密やかに涙を溢すティアリーゼを見つけてしまった。
「リドリス様……」
うっかり見つかってしまった前回とは違い、この時は堪らず姿を現してしまった。
涙を流しながら振り返ったティアリーゼが、慌てて頬を伝う雫を拭う。しかしまた本人の意思に反し、すぐに一筋の雫が溢れる。
「も、申し訳……ありま……っ」
「何か、あったの?」
「……」
「言い辛いよね」
呟きながら、ユリウスの指がティアリーゼの涙を拭った。
「!?」
頬を赤らめ狼狽するティアリーゼに、柔らかな声が落ちてくる。
「立場上気持ちを口にするのは憚られるかもしれないけれど、今だけ吐き出してみない?」
「えっと……」
「それじゃあこうしよう、今聞くことは今日限りで忘れて、以降は話題に出さないと約束する。どうかな?」
ユリウスの言葉に、不思議とティアリーゼの涙は止まる。そして恐る恐る、これまでの公爵家でのことを話し始めた。
途中何度も言葉を詰まらせるも、ユリウスは黙って真摯に話を聞いてくれる。
話を聞き終えたユリウスは、真っ直ぐ彼女の瞳を見て言葉を紡ぐ。
「ティアリーゼ、忘れないで。僕は何があっても君の味方だから」
「リドリス殿下……」
「誰が敵に回っても、世界中を敵にしてでも僕は君の味方で有り続けるから」
ユリウスの染み入るような優しい声音が、ティアリーゼの胸底にある澱を溶かしたような気がした。
以降リドリスは約束通り、今聞いたティアリーゼの話を決して話はしなかった。それもその筈、彼の正体はユリウスなのだから。
妃教育に向かったティアリーゼと一旦別れ、二時間後。ユリウスは、王宮の廊下を歩いている途中、ピンクブロンドの髪の後ろ姿を見つけた。
再び目にしたティアリーゼは、掃除婦たちの仕事ぶりを柱の影から眺めている。
あまりにも熱心なその様子に、ユリウスは声を掛けるのは断念した。
翌日。
リドリスの私室にてユリウスは呪文を紡ぐ。
しばらくすると、目の前の鏡台に映し出されていた自身の姿が、見知らぬ風景へと変わる。
こぢんまりとした佇まいの、白い外観の建物。
(ティアリーゼが言っていた公爵家の別棟か)
あまり広範囲で使える魔法ではないが、王宮から公爵邸までの距離なら問題なく見通すことが出来る。
公爵家の庭先から、建物の窓ごしに内部を覗けば、廊下を生き生きと掃除するティアリーゼの姿があった。
自分を何も出来ないと言っていたティアリーゼが、一生懸命掃除をしている。
ミルディンの城も使用人が少なく、他の貴族に比べてユリウスは身の回りを自身でこなせるが、流石に掃除までは経験がない。
公爵令嬢が掃除をしようが、誰もティアリーゼを止めないどころか、周りに使用人の姿が見当たらない。
沢山の侍女に囲まれた、王宮で見せていた煌びやかな姿とは一変していた。
その夜、ランベール王と二人きりの晩餐でユリウスは尋ねた。
「ティアリーゼとリドリスは、父上から見てどう思われますか?」
ユリウスは国王と二人きりの時、父と呼ぶことを許されている。
「仲良くやっていると思うよ」
「そうですか、微笑ましい限りですね」
何気ないやり取りは、親子のありふれた食事風景といえる。
ランベールの風習に従い、忌子として遠くの地で暮らす、王のもう一人の息子ユリウス。
ランベール王は、聡明で快活に育ったユリウスを見て、安堵していた。
不自由な身の上に追いやっている第一王子に、出来る範囲で要望を叶えてやりたい。
そう思っていた矢先──
「……もし、何らかの原因で婚約が解消になった場合、ティアリーゼを僕の婚約者にして頂くことは可能でしょうか?」
ユリウスから父へ、初めての要望だった。
予想だにしていなかった申し出に、ランベール王は虚を衝かれてユリウスを見る。
「いえ、でも二人が仲睦まじいことに越したことはありません。僕も二人の幸せを、ミルディンの地で祈っております」
それを告げると、ユリウスは直ぐに別の話題に切り替えた。
(彼女のことを知らない僕が、憶測するべきではないけれど……)
様子を窺っていると、更に誰かの気配がし、ユリウスは更に身を潜めた。
「ティアリーゼ様っ」
「あっ……」
「お茶のご用意をしていましたら、お姿が見えなくなったので、驚いてしまいましたわ」
侍女の一人がティアリーゼを迎えに来たらしい。
「ごめんなさい、あまりにも薔薇が綺麗に咲いていて、つい奥まで来てしまいました」
「今度からは一声掛けて下さいませ」
「申し訳ありません」
その時、ティアリーゼと侍女の斜め後ろの植え込みから、がさりと音がした。
こっそり場を離れようとしたが意に反し、つい音を立ててしまったユリウスへ、二人の視線が注がれる。
「あら、リドリス殿下?」
「リドリス殿下、ごきげんよう」
突然のリドリスの登場に虚を突かれていたが、二人はすぐに淑女の礼をした。
(しまった、気になって物陰から見ていたとは言えないな……)
「偶然通りかかって」
「そうだったのですね、今からお茶の時間なのですが、リドリス殿下もご一緒にいかがですか?」
無下には断れず、そのままユリウスはティアリーゼと庭園でお茶をする運びとなった。
鮮やかな花々に囲まれ、白の丸テーブルを挟んでユリウスは、ティアリーゼと向かい合う。テーブルと揃いの、優雅な曲線を描く白の椅子に二人は腰掛ける。
お茶を淹れる侍女の手元を終始じっと見つめているティアリーゼを、ユリウスは不躾にならない程度に観察していた。
(侍女がお茶を淹れる場面なんて、珍しくもないと思うけど……?)
「天気もいいし、花もとても綺麗だね」
ユリウスは当たり障りのない言葉を紡いだ。
「はい、流石王宮の庭師のお仕事は大変素晴らしいですわ」
「ティアリーゼは職人や仕事をしている人を気にしているようだね。さっきも侍女の手元を注視していたし」
「はい、お茶を淹れる所作がとても綺麗で……わたしもあんな風に……」
言い掛け、ティアリーゼは慌てて顔を上げる。
「すみません、なんでもございません」
「謝らなくていいよ。ただ少し気になっただけだから」
ユリウスの優しげな眼差しに、ティアリーゼも落ち着きを取り戻す。
「興味があると言いますか、働いている方々のことを尊敬しております。わたしなど、何も出来ることがなくて……」
王都の令嬢と言えば、流行のドレスや宝飾品の事ばかりを気にするものだと思っていた。
ティアリーゼのように熱心に使用人に目を向けたりもする令嬢もいるのかと、意外な発見だった。
お陰でユリウスの中に誤算が生じてしまう。
ティアリーゼが気になって仕方がない。
いくら髪や瞳の色を似せた所で、リドリスと多くの時間を共に過ごした筈の彼女には、偽物だと気付かれてしまもしれない。
不必要にティアリーゼとの接触はしない筈だったのに。
数日後──
(参った、また会えるかもしれないと思って足を運んでしまったものの……)
ユリウスはティアリーゼが王宮に来る予定の日に、庭園に足を運ぶと、その姿を探した。
すると、密やかに涙を溢すティアリーゼを見つけてしまった。
「リドリス様……」
うっかり見つかってしまった前回とは違い、この時は堪らず姿を現してしまった。
涙を流しながら振り返ったティアリーゼが、慌てて頬を伝う雫を拭う。しかしまた本人の意思に反し、すぐに一筋の雫が溢れる。
「も、申し訳……ありま……っ」
「何か、あったの?」
「……」
「言い辛いよね」
呟きながら、ユリウスの指がティアリーゼの涙を拭った。
「!?」
頬を赤らめ狼狽するティアリーゼに、柔らかな声が落ちてくる。
「立場上気持ちを口にするのは憚られるかもしれないけれど、今だけ吐き出してみない?」
「えっと……」
「それじゃあこうしよう、今聞くことは今日限りで忘れて、以降は話題に出さないと約束する。どうかな?」
ユリウスの言葉に、不思議とティアリーゼの涙は止まる。そして恐る恐る、これまでの公爵家でのことを話し始めた。
途中何度も言葉を詰まらせるも、ユリウスは黙って真摯に話を聞いてくれる。
話を聞き終えたユリウスは、真っ直ぐ彼女の瞳を見て言葉を紡ぐ。
「ティアリーゼ、忘れないで。僕は何があっても君の味方だから」
「リドリス殿下……」
「誰が敵に回っても、世界中を敵にしてでも僕は君の味方で有り続けるから」
ユリウスの染み入るような優しい声音が、ティアリーゼの胸底にある澱を溶かしたような気がした。
以降リドリスは約束通り、今聞いたティアリーゼの話を決して話はしなかった。それもその筈、彼の正体はユリウスなのだから。
妃教育に向かったティアリーゼと一旦別れ、二時間後。ユリウスは、王宮の廊下を歩いている途中、ピンクブロンドの髪の後ろ姿を見つけた。
再び目にしたティアリーゼは、掃除婦たちの仕事ぶりを柱の影から眺めている。
あまりにも熱心なその様子に、ユリウスは声を掛けるのは断念した。
翌日。
リドリスの私室にてユリウスは呪文を紡ぐ。
しばらくすると、目の前の鏡台に映し出されていた自身の姿が、見知らぬ風景へと変わる。
こぢんまりとした佇まいの、白い外観の建物。
(ティアリーゼが言っていた公爵家の別棟か)
あまり広範囲で使える魔法ではないが、王宮から公爵邸までの距離なら問題なく見通すことが出来る。
公爵家の庭先から、建物の窓ごしに内部を覗けば、廊下を生き生きと掃除するティアリーゼの姿があった。
自分を何も出来ないと言っていたティアリーゼが、一生懸命掃除をしている。
ミルディンの城も使用人が少なく、他の貴族に比べてユリウスは身の回りを自身でこなせるが、流石に掃除までは経験がない。
公爵令嬢が掃除をしようが、誰もティアリーゼを止めないどころか、周りに使用人の姿が見当たらない。
沢山の侍女に囲まれた、王宮で見せていた煌びやかな姿とは一変していた。
その夜、ランベール王と二人きりの晩餐でユリウスは尋ねた。
「ティアリーゼとリドリスは、父上から見てどう思われますか?」
ユリウスは国王と二人きりの時、父と呼ぶことを許されている。
「仲良くやっていると思うよ」
「そうですか、微笑ましい限りですね」
何気ないやり取りは、親子のありふれた食事風景といえる。
ランベールの風習に従い、忌子として遠くの地で暮らす、王のもう一人の息子ユリウス。
ランベール王は、聡明で快活に育ったユリウスを見て、安堵していた。
不自由な身の上に追いやっている第一王子に、出来る範囲で要望を叶えてやりたい。
そう思っていた矢先──
「……もし、何らかの原因で婚約が解消になった場合、ティアリーゼを僕の婚約者にして頂くことは可能でしょうか?」
ユリウスから父へ、初めての要望だった。
予想だにしていなかった申し出に、ランベール王は虚を衝かれてユリウスを見る。
「いえ、でも二人が仲睦まじいことに越したことはありません。僕も二人の幸せを、ミルディンの地で祈っております」
それを告げると、ユリウスは直ぐに別の話題に切り替えた。