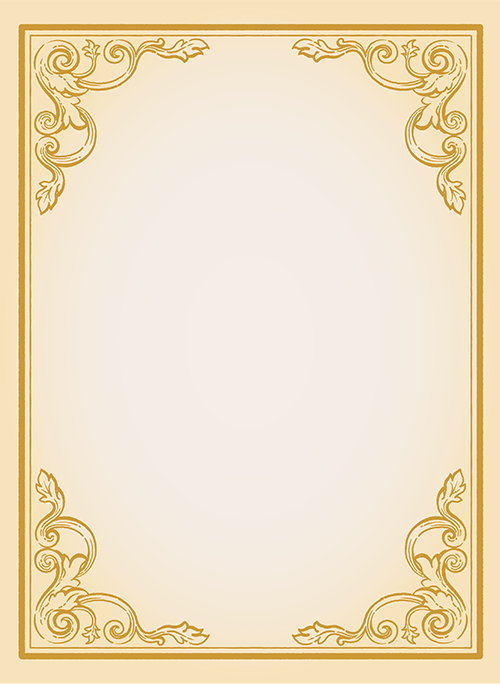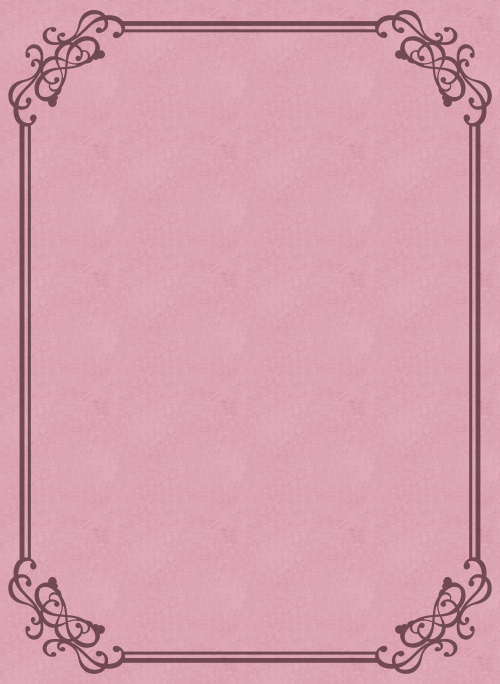──時は遡って、ティアリーゼ達がミルディンにいた頃。
マリータはリドリスの新たな妃候補として、定期的に王宮へと登城し、妃教育を受けていた。
しかしながら、勉学全般を好まないマリータが根を上げるのに時間は掛からなかった。
元々リドリスの婚約者であり、長年妃教育を受けて来た異母姉ティアリーゼに教えを請おうと思ったが、彼女は公爵家の屋敷を既に出た後。
──何故必要な時に居てくれないのか。
ティアリーゼは本館ではなく、公爵家敷地内で暮らしていたため、誰も出て行ったことをすぐに気付けなかった。
マリータも姉がそのような突飛な行動に出るとは思わず、妃教育に苦戦する自分への嫌がらせだったのではと邪推してしまいそうになる。
何故か最近何も上手くいかず、焦燥感を抱いていた。
いくら勉強が好きになれなくとも、リドリスを諦めた訳ではない。
にも関わらず、王宮にいてもリドリスには会えず、挙句彼が長年続けていた公爵家への訪れもなくなってしまった。
婚約も正式には決まっていない。
一体いつになったらリドリスの婚約者になれるのか。
焦りばかりが募る中、妃教育で王宮に訪れたある日。マリータは妃教育のために用意された一室には向かわず、リドリスの私室へと向かった。
部屋の前には衛兵が立ちはだかっている。マリータは衛兵におずおずと声を掛けた。
「あの……」
「いかがなさいましたか?」
「妃教育のためにうかがった、クルステア家のマリータです。リドリス様がお呼びになられていると聞いて……」
マリータの適当な嘘だったが、リドリスは公務の合間の休憩時間であり、折よく私室にいるようだ。お陰でそのまま、隣接する応接室へと通されることとなった。
リドリスの幼少時から仕えている侍女に案内され、足を踏み入れるとすぐにリドリスが視界に入った。
侍女がリドリスに声を掛ける。
「リドリス殿下、クルステア嬢がお目見えになられております」
リドリスは項垂れるように長椅子に腰掛けており、マリータは声を掛けるのに僅かばかり窮した。
「リドリス様……」
「ティアリーゼ……?」
顔を上げたリドリスは、虚な瞳を向けて呟いた。
(どうしてお姉様の名を……っ!?)
マリータはリドリスに近づき、必死に訴える。
「リドリス様、わたしはマリー……」
「ティアリーゼじゃないっ!」
声を荒げ、リドリスが立ち上がる。
リドリスが腕を振り回した先には、テーブルの上に用意されていたティーセット。手が当たってしまい、ティーカップはガチャンと音を立てて床に落下した。
「ひっ!?」
「ティアリーゼは何処だっ!」
錯乱し、声を荒げる姿はどうみても正常には見えず、恐ろしさのあまりマリータは青ざめ恐怖に震える。
侍女が急いで衛兵を呼び、部屋に何人もの人が入って来る。辺りは騒がしい筈なのに、その間マリータには一切音が聞こえなくなっていた。
◇
顔を真っ赤にさせながら、夜会の会場から退場したマリータは、一人王宮の廊下を足早に進んでいた。
少し前に顔を合わせた際のリドリスはあんなにも不安定だったのに、今夜はいつも以上に貴公子然としていた。
それなのに、隣にいるのは自分ではなく姉ティアリーゼ。
(どうして?)
──どうしてお姉様ばかりっ……!
そう口にした途端、周りの令嬢達が口々に溢した言葉。
『まぁ、はしたない』
『これだから庶子は』
『異母妹とはいえ、高貴なティアリーゼ様にあんな態度を取るだなんて……身の程を弁えない庶子だこと』
クルステア公爵の実の娘でありながら『庶子』と呼ばれるのは、両親の婚姻前に自分が生まれたから。
ティアリーゼの母より先に、父と出会っていたのは、マリータの母ミランダの方なのに。
姉さえいなければ自分は庶子とは呼ばれず、姉妹で比べられずにすんだのに。
上手くいかないのは全て姉のせいに思えてしまっていた。
マリータはリドリスの新たな妃候補として、定期的に王宮へと登城し、妃教育を受けていた。
しかしながら、勉学全般を好まないマリータが根を上げるのに時間は掛からなかった。
元々リドリスの婚約者であり、長年妃教育を受けて来た異母姉ティアリーゼに教えを請おうと思ったが、彼女は公爵家の屋敷を既に出た後。
──何故必要な時に居てくれないのか。
ティアリーゼは本館ではなく、公爵家敷地内で暮らしていたため、誰も出て行ったことをすぐに気付けなかった。
マリータも姉がそのような突飛な行動に出るとは思わず、妃教育に苦戦する自分への嫌がらせだったのではと邪推してしまいそうになる。
何故か最近何も上手くいかず、焦燥感を抱いていた。
いくら勉強が好きになれなくとも、リドリスを諦めた訳ではない。
にも関わらず、王宮にいてもリドリスには会えず、挙句彼が長年続けていた公爵家への訪れもなくなってしまった。
婚約も正式には決まっていない。
一体いつになったらリドリスの婚約者になれるのか。
焦りばかりが募る中、妃教育で王宮に訪れたある日。マリータは妃教育のために用意された一室には向かわず、リドリスの私室へと向かった。
部屋の前には衛兵が立ちはだかっている。マリータは衛兵におずおずと声を掛けた。
「あの……」
「いかがなさいましたか?」
「妃教育のためにうかがった、クルステア家のマリータです。リドリス様がお呼びになられていると聞いて……」
マリータの適当な嘘だったが、リドリスは公務の合間の休憩時間であり、折よく私室にいるようだ。お陰でそのまま、隣接する応接室へと通されることとなった。
リドリスの幼少時から仕えている侍女に案内され、足を踏み入れるとすぐにリドリスが視界に入った。
侍女がリドリスに声を掛ける。
「リドリス殿下、クルステア嬢がお目見えになられております」
リドリスは項垂れるように長椅子に腰掛けており、マリータは声を掛けるのに僅かばかり窮した。
「リドリス様……」
「ティアリーゼ……?」
顔を上げたリドリスは、虚な瞳を向けて呟いた。
(どうしてお姉様の名を……っ!?)
マリータはリドリスに近づき、必死に訴える。
「リドリス様、わたしはマリー……」
「ティアリーゼじゃないっ!」
声を荒げ、リドリスが立ち上がる。
リドリスが腕を振り回した先には、テーブルの上に用意されていたティーセット。手が当たってしまい、ティーカップはガチャンと音を立てて床に落下した。
「ひっ!?」
「ティアリーゼは何処だっ!」
錯乱し、声を荒げる姿はどうみても正常には見えず、恐ろしさのあまりマリータは青ざめ恐怖に震える。
侍女が急いで衛兵を呼び、部屋に何人もの人が入って来る。辺りは騒がしい筈なのに、その間マリータには一切音が聞こえなくなっていた。
◇
顔を真っ赤にさせながら、夜会の会場から退場したマリータは、一人王宮の廊下を足早に進んでいた。
少し前に顔を合わせた際のリドリスはあんなにも不安定だったのに、今夜はいつも以上に貴公子然としていた。
それなのに、隣にいるのは自分ではなく姉ティアリーゼ。
(どうして?)
──どうしてお姉様ばかりっ……!
そう口にした途端、周りの令嬢達が口々に溢した言葉。
『まぁ、はしたない』
『これだから庶子は』
『異母妹とはいえ、高貴なティアリーゼ様にあんな態度を取るだなんて……身の程を弁えない庶子だこと』
クルステア公爵の実の娘でありながら『庶子』と呼ばれるのは、両親の婚姻前に自分が生まれたから。
ティアリーゼの母より先に、父と出会っていたのは、マリータの母ミランダの方なのに。
姉さえいなければ自分は庶子とは呼ばれず、姉妹で比べられずにすんだのに。
上手くいかないのは全て姉のせいに思えてしまっていた。