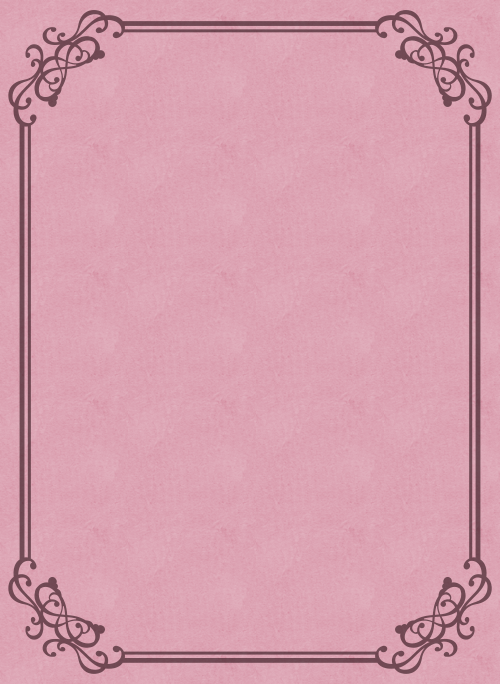ティアリーゼが私室に戻ろうと廊下を歩いているとミハエル、そして彼の肩に腰を下ろすユーノと鉢合わせになった。
「ティアリーゼ嬢」
「ミハエル殿下、ユーノさん。どうか致しましたか?」
どうやらティアリーゼが部屋に戻るのを、二人して待っていたらしい。
「ティアリーゼ嬢は王都に里帰りした際に、公爵家の者と対面するのだろうか?」
「出来ればあまり関わりたくはないのですが」
「そうだよな。では代わりと言っは何だが、ティアリーゼ嬢とスウェナ殿の遠縁の者として、私が彼らに一言物申しても良いだろうか」
「俺も参戦するぜ」
意気込むミハエルとユーノに、ティアリーゼは一瞬思考が停止した。そして押され気味になりつつも、申し出を拒否する。
「ええっ、いいえっ!大丈夫ですからっ」
(掻き乱そうとなさってる!?)
正義感ゆえの行動とは理解しているが、いかんせん破天荒なこの二人である。
ミハエルは特に、一国の王子でありながら本当にリドリスやティアリーゼの家族へ、物申しに行きそうで恐ろしい。
狼狽するティアリーゼの耳に、その場にはそぐわ無い落ち着いた声音が響き渡った。
「人様のご家庭の事情に、首を突っ込むべきではありませんよ」
イルが二人の暴走を止めに来てくれたようだ。
「う……そうか、悪かった」
「いえ」
ミハエルとユーノの動きがぴたりと止まった。
(イル様のお陰で、ミハエル殿下とユーノさんが思いとどまって下さって良かった……。でもお二人がお優しい方だということは、凄く伝わります……)
肩を落として反省する二人に、ティアリーゼは礼を述べる。
「お気持ち、とても嬉しかったです。わたしなどを気に掛けて下さって、本当にありがとうございます」
:.:*:.:*:.:*:.:*:.:*:.:*:.:*:.:*:.:*:.:*:.:*:.:*:.:*:.:*:
月が夜空に浮かんでいる。
夜が深まっていく中、手燭の灯りを消さないまま、ティアリーゼはぼんやりと物思いに耽っていた。
ミルディンでの日々の暮らしで心がいっぱいで、王都の様子をあまり気に掛けないようにしていた。公爵家の人々の存在を思い出すと、やはり心が落ち着かない。
──そしてリドリスの体調不良。
(リドリス殿下のお体は、大丈夫かしら?)
互いに心が遠く分かり合えず、そして別れを言えないまま、ティアリーゼはユリウスの元へ来た。
それでも幼馴染として、彼の幸せを願っていることには変わらない。
そのような中、体調を悪くしているリドリスに変装して、ユリウスが建国祭に出席するといった事態に困惑せざるを得ない。
(ならどうしてパートナーがマリータではなく、わたしなのかしら……?現在のリドリス殿下の婚約者はマリータの筈なのに……)
そう思った瞬間、再び頭の中にはユリウスがマリータの手を取ってエスコートする姿が映し出された。夜会で手を取り合い、踊ったりする二人の姿を想像してしまい、思わず頭を振った。
(胸が苦しい……)
国王の考えは、ティアリーゼには見当もつかない。
王都での記憶と同時に、自分の人生が何かを得ても、突如失うことばかりだったことを思い出す。
また失うのだろうか?
今の日々を大切に思うほど、失った時の喪失感は計り知れないものとなるだろう。
──やっと心穏やかに過ごせる場所が出来たと思っていたのに。
王都に行くことで、何かが変わってしまうかもしれない恐怖に心が翳る。
その日の夜、ティアリーゼは中々眠りにつくことが叶わなかった。
「ティアリーゼ嬢」
「ミハエル殿下、ユーノさん。どうか致しましたか?」
どうやらティアリーゼが部屋に戻るのを、二人して待っていたらしい。
「ティアリーゼ嬢は王都に里帰りした際に、公爵家の者と対面するのだろうか?」
「出来ればあまり関わりたくはないのですが」
「そうだよな。では代わりと言っは何だが、ティアリーゼ嬢とスウェナ殿の遠縁の者として、私が彼らに一言物申しても良いだろうか」
「俺も参戦するぜ」
意気込むミハエルとユーノに、ティアリーゼは一瞬思考が停止した。そして押され気味になりつつも、申し出を拒否する。
「ええっ、いいえっ!大丈夫ですからっ」
(掻き乱そうとなさってる!?)
正義感ゆえの行動とは理解しているが、いかんせん破天荒なこの二人である。
ミハエルは特に、一国の王子でありながら本当にリドリスやティアリーゼの家族へ、物申しに行きそうで恐ろしい。
狼狽するティアリーゼの耳に、その場にはそぐわ無い落ち着いた声音が響き渡った。
「人様のご家庭の事情に、首を突っ込むべきではありませんよ」
イルが二人の暴走を止めに来てくれたようだ。
「う……そうか、悪かった」
「いえ」
ミハエルとユーノの動きがぴたりと止まった。
(イル様のお陰で、ミハエル殿下とユーノさんが思いとどまって下さって良かった……。でもお二人がお優しい方だということは、凄く伝わります……)
肩を落として反省する二人に、ティアリーゼは礼を述べる。
「お気持ち、とても嬉しかったです。わたしなどを気に掛けて下さって、本当にありがとうございます」
:.:*:.:*:.:*:.:*:.:*:.:*:.:*:.:*:.:*:.:*:.:*:.:*:.:*:.:*:
月が夜空に浮かんでいる。
夜が深まっていく中、手燭の灯りを消さないまま、ティアリーゼはぼんやりと物思いに耽っていた。
ミルディンでの日々の暮らしで心がいっぱいで、王都の様子をあまり気に掛けないようにしていた。公爵家の人々の存在を思い出すと、やはり心が落ち着かない。
──そしてリドリスの体調不良。
(リドリス殿下のお体は、大丈夫かしら?)
互いに心が遠く分かり合えず、そして別れを言えないまま、ティアリーゼはユリウスの元へ来た。
それでも幼馴染として、彼の幸せを願っていることには変わらない。
そのような中、体調を悪くしているリドリスに変装して、ユリウスが建国祭に出席するといった事態に困惑せざるを得ない。
(ならどうしてパートナーがマリータではなく、わたしなのかしら……?現在のリドリス殿下の婚約者はマリータの筈なのに……)
そう思った瞬間、再び頭の中にはユリウスがマリータの手を取ってエスコートする姿が映し出された。夜会で手を取り合い、踊ったりする二人の姿を想像してしまい、思わず頭を振った。
(胸が苦しい……)
国王の考えは、ティアリーゼには見当もつかない。
王都での記憶と同時に、自分の人生が何かを得ても、突如失うことばかりだったことを思い出す。
また失うのだろうか?
今の日々を大切に思うほど、失った時の喪失感は計り知れないものとなるだろう。
──やっと心穏やかに過ごせる場所が出来たと思っていたのに。
王都に行くことで、何かが変わってしまうかもしれない恐怖に心が翳る。
その日の夜、ティアリーゼは中々眠りにつくことが叶わなかった。