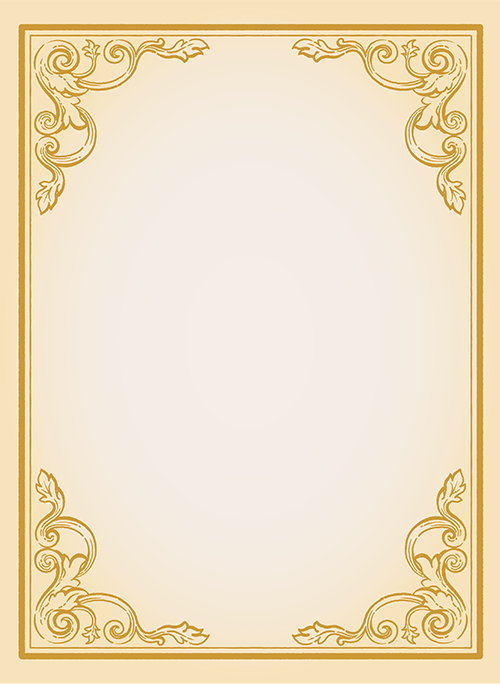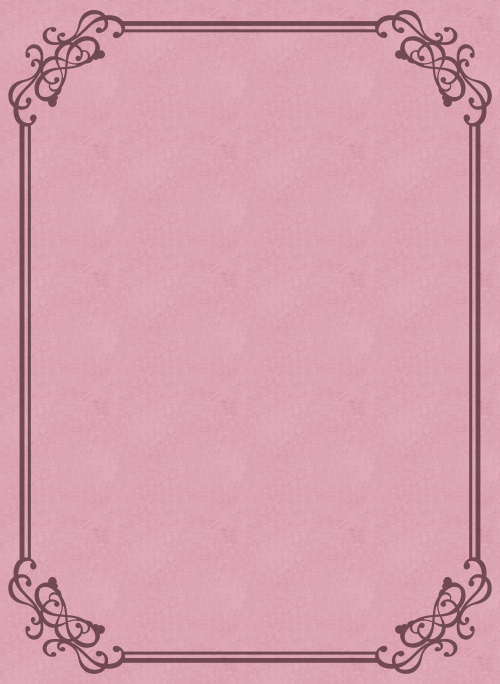支度を終えたティアリーゼは庭園を経由して、本館の玄関前へと向かう。
しばらくして王室の馬車がこの屋敷を訪れた。
馬車から降りてきたのは、薄茶色の髪に整った面立ちの少年。ティアリーゼの婚約者であり、この国の王子リドリスだ。
ティアリーゼは淑女の礼をする。
「御機嫌ようリドリス様、我が公爵家にようこそいらっしゃいました」
「こんにちは、ティアリーゼ」
「庭園までご案内致します」
「ありがとう、お願いするよ」
ティアリーゼがリドリスを案内した四阿には既にお茶の用意が整えられている。二人が席に着くと、カップに温かいお茶が注がれた。
お茶を飲み、菓子を摘みながら他愛の無い話やお互いの近況報告をし合うのが恒例だ。
リドリスと過ごす穏やかな時間は、ティアリーゼにとって大切なものとなっている。
「ティアリーゼ、今日は何をしていたの?」
「孤児院に寄付するための、編み物をしておりました」
「編み物か、今度は何を作っていたのかな」
「こちらです」
問われてティアリーゼは、身に付けているブレスレット、そしてドレスの胸元に飾っているブローチをリドリスへと見せた。
タティングレースの腕輪とブローチだ。
それらは糸でレースを編んでいく技法を用いて作った物。白と青の二色で編んだレースで作った腕輪。そしてレースで花を描き、パールビーズを組み合わせたブローチだ。
今身につけているような装飾品意外にも、クロスやタンブラーといった日用品など、小物製作も行っている。
「凄い……これがリーゼの手から作り出されたなんて、魔法のようだよ。本当に凄いし素敵だね」
ティアリーゼは心中で胸を撫で下ろす。
実はつい先程編んでいたのはタティングレースではなく、羊毛の手袋。
冬までに手袋を完成させて、リドリスに贈る予定だからまだ内緒にしておきたい。
タティングレースの装飾品を身に付けていることで上手く話を反らせたと、内心安堵で胸を撫で下ろした。
その年の初秋、完成した手袋をリドリスへ贈ると、この屋敷に訪れる度に手袋をつけてくれるようになった。
しばらくして王室の馬車がこの屋敷を訪れた。
馬車から降りてきたのは、薄茶色の髪に整った面立ちの少年。ティアリーゼの婚約者であり、この国の王子リドリスだ。
ティアリーゼは淑女の礼をする。
「御機嫌ようリドリス様、我が公爵家にようこそいらっしゃいました」
「こんにちは、ティアリーゼ」
「庭園までご案内致します」
「ありがとう、お願いするよ」
ティアリーゼがリドリスを案内した四阿には既にお茶の用意が整えられている。二人が席に着くと、カップに温かいお茶が注がれた。
お茶を飲み、菓子を摘みながら他愛の無い話やお互いの近況報告をし合うのが恒例だ。
リドリスと過ごす穏やかな時間は、ティアリーゼにとって大切なものとなっている。
「ティアリーゼ、今日は何をしていたの?」
「孤児院に寄付するための、編み物をしておりました」
「編み物か、今度は何を作っていたのかな」
「こちらです」
問われてティアリーゼは、身に付けているブレスレット、そしてドレスの胸元に飾っているブローチをリドリスへと見せた。
タティングレースの腕輪とブローチだ。
それらは糸でレースを編んでいく技法を用いて作った物。白と青の二色で編んだレースで作った腕輪。そしてレースで花を描き、パールビーズを組み合わせたブローチだ。
今身につけているような装飾品意外にも、クロスやタンブラーといった日用品など、小物製作も行っている。
「凄い……これがリーゼの手から作り出されたなんて、魔法のようだよ。本当に凄いし素敵だね」
ティアリーゼは心中で胸を撫で下ろす。
実はつい先程編んでいたのはタティングレースではなく、羊毛の手袋。
冬までに手袋を完成させて、リドリスに贈る予定だからまだ内緒にしておきたい。
タティングレースの装飾品を身に付けていることで上手く話を反らせたと、内心安堵で胸を撫で下ろした。
その年の初秋、完成した手袋をリドリスへ贈ると、この屋敷に訪れる度に手袋をつけてくれるようになった。