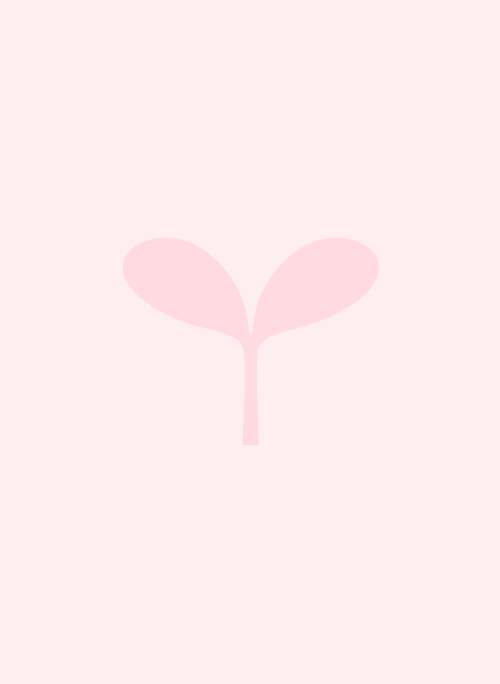畑に深く掘った穴の中に、枯葉と枯草をどっさり放り込んで火をつけた焚火は、遠くからだと煙しか見えなかったが、ちゃんとオレンジ色の炎が燃えていた。
「お前も軍手はめぇ」
じいちゃんがすすけた大人用の軍手を柚樹に手渡す。自分は腰に引っかけていた煤で真っ黒の軍手をはめて、長いトングを使って焚火の中をぐりぐりいじりだした。
ぱちぱちっと、火の粉が宙に舞っている。
「ほれ、熱いから気ぃつけてな」
軍手をはめた柚樹の手に、トングで掴んだ茶色く焦げたアルミホイルを、じいちゃんがぽいと乗せる。
「あっち!」
熱されたアルミホイルは想像以上に熱い!! 柚樹は右手と左手で交互にキャッチしながら、なんとか冷ましていく。
「おお、こりゃ大変だ」
見ると、隣でじいちゃんも同じようにしながら、わっはっはと笑っている。
いつものじいちゃん、に、見える。でも、内心は違うかもしれない。
大人は本心を隠して取り繕うのが上手いから。
むしゃくしゃする気持ちをぶつけるように、柚樹はアルミホイルをビリビリ破る。中から出てきたのは、赤茶色の皮。その皮もテキトーに向いてかぶりついた。
「どうじゃ?」
「……すげぇ、ウマい」
黄金色のサツマイモは、蜂蜜をかけたみたいにねっとり甘くて、想像以上のウマさだった。柚樹の知っている焼き芋とは別次元、まるでスイーツだ。
じいちゃんのサツマイモはいつも甘くて好きだけど、これは別格だった。
「じゃろ? 今年は種芋を奮発して、肥料もいろいろ研究したからなぁ。ほんで、焼き芋は焚火でじっくり焼くのが一番ウマいんじゃ。めちゃんこ甘くなる。焚火イモは、お前の母さんが作るオーブンで焼いたお上品な焼き芋より旨いじゃろ~」と、じいちゃんがニヤリと笑った。
「まあ……」
いつもは何とも思わない、じいちゃんの「お前の母さん」という言葉が、胸にささる。もうすぐ、「お前の母さん」じゃなくなると、言われているような気がしてしまう。
いつもと変わらないじいちゃんの言葉が、いつもと違う風に聞こえてくる。
モヤモヤしながら、柚樹はサツマイモをかじり続けた。ねっとり、ねっとり、ものすごく甘い。
舌に絡まって、溶けて、喉をゆっくりと通り過ぎていく。
「焚火はいい。あったかいし、枯葉や藁の焼ける匂いも乙じゃろ? この火の粉が爆ぜる音も、何とも言えん。男のロマンがこう、ぎゅっと詰まっとる。ずっとお前に見せよう、ほんで、めちゃんこ旨い焚火イモ食わせてやろう思っとったんだが、お前の母さんもばあちゃんも危ないからやめろ~やら、火傷したらどうする~やら、もう~うるさくてな」
それでさっき「ばあちゃんがいないからチャンス」みたいなことを言ってたのか。
ばあちゃんと母さんが意気投合して、じいちゃんに説教する姿は容易に想像できた。
昔から、じいちゃんが柚樹と何かしようとする度に、母さんかばあちゃん、もしくは二人一緒になって「ユズに変な事教えないで」とか「ユズにはまだ早い」とか言いながら、全力で止めに入っていたから。ついでに「まあまあ」と、二対一の間でオロオロする父さんの姿も浮かぶ。
その平穏で楽しかった思い出も、きっとこれからは違ってくるんだ。
暗い気持ちをかき消すように、オレンジ色の焚火にあたりながら、夢中でサツマイモを食べ進めていると「妹が生まれるのが嫌か?」とじいちゃんが核心をついてきた。
ぎょっとして、目だけ動かして柚樹はじいちゃんを見た。
じいちゃんは既に一本目を食べ終え、焚火の中から新しいサツマイモを取り出そうとしているところだった。
「実はじいちゃんな、お前の母さんと父さんが結婚するのが嫌じゃった」
「お前も軍手はめぇ」
じいちゃんがすすけた大人用の軍手を柚樹に手渡す。自分は腰に引っかけていた煤で真っ黒の軍手をはめて、長いトングを使って焚火の中をぐりぐりいじりだした。
ぱちぱちっと、火の粉が宙に舞っている。
「ほれ、熱いから気ぃつけてな」
軍手をはめた柚樹の手に、トングで掴んだ茶色く焦げたアルミホイルを、じいちゃんがぽいと乗せる。
「あっち!」
熱されたアルミホイルは想像以上に熱い!! 柚樹は右手と左手で交互にキャッチしながら、なんとか冷ましていく。
「おお、こりゃ大変だ」
見ると、隣でじいちゃんも同じようにしながら、わっはっはと笑っている。
いつものじいちゃん、に、見える。でも、内心は違うかもしれない。
大人は本心を隠して取り繕うのが上手いから。
むしゃくしゃする気持ちをぶつけるように、柚樹はアルミホイルをビリビリ破る。中から出てきたのは、赤茶色の皮。その皮もテキトーに向いてかぶりついた。
「どうじゃ?」
「……すげぇ、ウマい」
黄金色のサツマイモは、蜂蜜をかけたみたいにねっとり甘くて、想像以上のウマさだった。柚樹の知っている焼き芋とは別次元、まるでスイーツだ。
じいちゃんのサツマイモはいつも甘くて好きだけど、これは別格だった。
「じゃろ? 今年は種芋を奮発して、肥料もいろいろ研究したからなぁ。ほんで、焼き芋は焚火でじっくり焼くのが一番ウマいんじゃ。めちゃんこ甘くなる。焚火イモは、お前の母さんが作るオーブンで焼いたお上品な焼き芋より旨いじゃろ~」と、じいちゃんがニヤリと笑った。
「まあ……」
いつもは何とも思わない、じいちゃんの「お前の母さん」という言葉が、胸にささる。もうすぐ、「お前の母さん」じゃなくなると、言われているような気がしてしまう。
いつもと変わらないじいちゃんの言葉が、いつもと違う風に聞こえてくる。
モヤモヤしながら、柚樹はサツマイモをかじり続けた。ねっとり、ねっとり、ものすごく甘い。
舌に絡まって、溶けて、喉をゆっくりと通り過ぎていく。
「焚火はいい。あったかいし、枯葉や藁の焼ける匂いも乙じゃろ? この火の粉が爆ぜる音も、何とも言えん。男のロマンがこう、ぎゅっと詰まっとる。ずっとお前に見せよう、ほんで、めちゃんこ旨い焚火イモ食わせてやろう思っとったんだが、お前の母さんもばあちゃんも危ないからやめろ~やら、火傷したらどうする~やら、もう~うるさくてな」
それでさっき「ばあちゃんがいないからチャンス」みたいなことを言ってたのか。
ばあちゃんと母さんが意気投合して、じいちゃんに説教する姿は容易に想像できた。
昔から、じいちゃんが柚樹と何かしようとする度に、母さんかばあちゃん、もしくは二人一緒になって「ユズに変な事教えないで」とか「ユズにはまだ早い」とか言いながら、全力で止めに入っていたから。ついでに「まあまあ」と、二対一の間でオロオロする父さんの姿も浮かぶ。
その平穏で楽しかった思い出も、きっとこれからは違ってくるんだ。
暗い気持ちをかき消すように、オレンジ色の焚火にあたりながら、夢中でサツマイモを食べ進めていると「妹が生まれるのが嫌か?」とじいちゃんが核心をついてきた。
ぎょっとして、目だけ動かして柚樹はじいちゃんを見た。
じいちゃんは既に一本目を食べ終え、焚火の中から新しいサツマイモを取り出そうとしているところだった。
「実はじいちゃんな、お前の母さんと父さんが結婚するのが嫌じゃった」