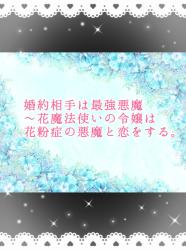気がつくと俺は、芽依の足にくっついて寄り添っていた。
「心配してくれているのかな? パピちゃん、ありがとね」
お礼を言いながら、頭を撫でてくれた。
撫でると言うより、これは『頭ぽんぽん』ってやつだ。
されるよりも、俺が芽依にしたいやつ。
「涼真が今、他の女の子とふたりきりで花火を見ているのかもってことを想像していたら、悲しくなっちゃって……この前も涼真の……似た理由で泣いていたよね。いつも話を聞いてくれて、ありがとう」
――俺は、ここにいるのに……。
というか、パピちゃんはいつも話を聞かされていたのか……いつも……。
いつも?
泣いているのは俺が原因で……。
――もしかして、芽依は俺のことを?
ものすごく自分の気持ちを伝えたくなってきた。
もう逃げることなんて、したくない。
今すぐ伝えたい――。
こんな近くにいるのに伝えられないなんて、なんてもどかしい。
伝えたい!
伝えたい気持ちが抑えきれなくなってきて、俺は叫んだ。
全力で伝えようとした。
好きな気持ちを。
「いっぱい吠えて、どうしたの? 帰りたいのかな? 帰ろっか!」
違う、そうじゃない。
くそっ。通じない。
「心配してくれているのかな? パピちゃん、ありがとね」
お礼を言いながら、頭を撫でてくれた。
撫でると言うより、これは『頭ぽんぽん』ってやつだ。
されるよりも、俺が芽依にしたいやつ。
「涼真が今、他の女の子とふたりきりで花火を見ているのかもってことを想像していたら、悲しくなっちゃって……この前も涼真の……似た理由で泣いていたよね。いつも話を聞いてくれて、ありがとう」
――俺は、ここにいるのに……。
というか、パピちゃんはいつも話を聞かされていたのか……いつも……。
いつも?
泣いているのは俺が原因で……。
――もしかして、芽依は俺のことを?
ものすごく自分の気持ちを伝えたくなってきた。
もう逃げることなんて、したくない。
今すぐ伝えたい――。
こんな近くにいるのに伝えられないなんて、なんてもどかしい。
伝えたい!
伝えたい気持ちが抑えきれなくなってきて、俺は叫んだ。
全力で伝えようとした。
好きな気持ちを。
「いっぱい吠えて、どうしたの? 帰りたいのかな? 帰ろっか!」
違う、そうじゃない。
くそっ。通じない。