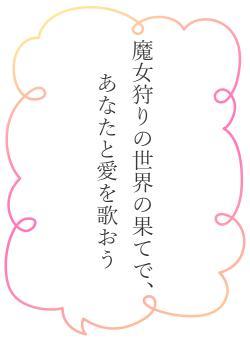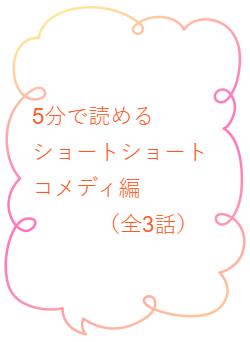「あいかわらず、おまえ、大事なところの話がぶっとんでんだよ。
なんでそんな考えにいたったのか、説明しろ」
うん、ごもっとも。ヴァンの言う通りだね。
「つまりだな、おまえがエートの血を飲むことを、儀式化するんだ」
「……まだわかんねーな」
ヴァンがわたしの方をふりむいたので、
わたしも肩をすくめて「わからない」と同意してみせる。
「マオ、いきなり儀式なんていわれても……。
ちゃんとした理由があるんだよね」
「ああ。理性をたもちつつ、
ヴァン自身の意思で魔王化したいんだろう?
そういうのは、魔王化する時に、
本能にある種の条件をすりこませるのが一番なんだ。
いわゆる条件付けだな」
「うーん……」
聞いてみたはいいものの、まだよくわかんない……。
ヴァンも、そんな顔をしている。
マオはそんなわたしたちを見て、
「どういったものか……」とつぶやいた。
「ヴァン、おまえがおれの血を『食事』として飲むときは、
必ず正面から抱きついてきて、
おれの首筋に牙を立てるだろう?」
「うえっ!?」
「……!」
ヴァンがすごい声を出し、わたしは驚きで固まった。
なんか、ものすごいことを聞いたような気がする。
マオはいつもの通りに表情が変わらないが、
ヴァンの顔がかあああっと赤くなっていく。
「な、なんで今そんな話をエートの前でわざわざ言って……!
エート、別におれ、好きでマオに抱きついてんじゃないからな!
ただ、ガキのころからそうしてたっていうか、
赤ん坊のころからそうやってマオの血を飲んでたから、
それがそのまま……」
めちゃくちゃ早口でまくしたてるヴァン。
なんだか、貴重だ。