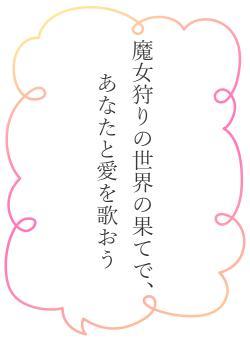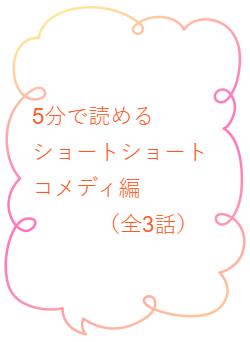わたしこと、エートは混乱していた。
「ひざまずいてエートの手の甲に、
口づけるというのはどうだろう?」
「は?」
天然な管理人長マオが
何様、おれ様、魔王様なヴァンに
そんな提案を言ってのけたからだ。
時間はしばし、さかのぼる。
***
ヴァンの暴走事件の次の日。
わたしとヴァン、そしてマオはダンジョンの地下五階。
土のエリアにいた。
「ヴァンパイアの本性をコントロールしたい。
やり方、教えろ。
あと、練習の監督もしてくれ」
そう、ヴァンがマオに頼んだからだ。
なんていうか、頼むにしては上から目線だよね。
でも、マオは、
「おまえからの頼み事は、めずらしいな……」と、
ちょっとうれしそうな顔になって、
「いいぞ」とこころよく承諾してくれた。
マンションで魔王化してコントロールの練習をすると、ものを壊すといけない。
ってことで、このダンジョンまでやってきたのだ。
「さて、ヴァン。
ヴァンパイアの本性をコントロールしたいと言っていたが……。
具体的には、どうなりたいんだ?」
「血を飲んで、魔王化しても正気をたもっていたい」
「ふむ。だれの血を飲むんだ」
「そりゃ、エートのだろ。
召喚の契約もしたし、いざって時におれが魔王化できた方がいい」
「ほう。つまり、戦闘時の魔王化だな」
マオはあごに手をあて、ちょっとの間考えこみ……、口を開いた。
「ひざまずいてエートの手の甲に、
口づけるというのはどうだろう?」
「は?」
わたしとヴァンの声が重なった。
マオってば、何言ってるの?
今って、魔王化をどうコントロールするかっていう話だったよね?
なぜに、令嬢への正式な挨拶みたいな話になってんの?
想像するだけで、かーっと顔が熱くなる。
ヴァンひざまずき、優しくわたしの手をとって、甲にキス。
まるで、王子様みたいじゃん!
ちら、とヴァンを見ると、眉の間にシワをよせて、
困惑ともあきれともとれる表情をしていた。