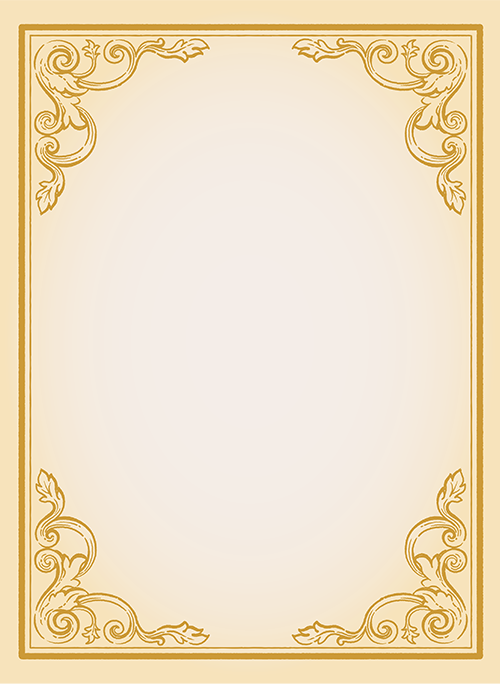「たった一度、交際っぽい関係を持った女性がいます。高校の時のことです。その女性にとてもよく似た人をこのビルの近くで見つけたのです」
「…………」
「彼女のことが気になるのは確かです。態度が変わったとおっしゃるなら、それはその女性を見たからだと思います。ですが、それだけです。知佳さんを傷つけるような行動はしていないし、そんな状況でもありません」
知佳は拓斗の言葉にあいまいな微笑みを浮かべた。とはいえ拓斗はその微笑みが否定的であることを理解した。彼女は受け入れる気はないのだと。
「その方かどうか、確かめないのですか?」
「……確かめてどうするんです? 十年も経ったのに、今更」
言いながら、高校時代、少しの間だけつきあっていたクラスメートの顔が蘇った。
十七歳の時の顔だ。大学に入ると、次第に疎遠になり、自然消滅してしまった女性。
(茜)
自分に自信がなくて、いつもはにかんだように微笑む少女。
勉強に忙しくていつの間にか離れてしまったけれど、愛しいと求めた人。
拓斗の中で色褪せ、心の奥底に沈んでしまっていた記憶が鮮やかに蘇った。
「先生、その方のことがまだお好きなんですね」
「……え」
「もしかして、初恋、とか?」
心臓がドキンと跳ねた。
――初恋。
「失礼しました。高校生ですものね。ごめんなさい」
「……いいえ。否定しません。僕はずっと勉強ばかりしてきたから」
拓斗は茫然と答えた。
初恋、初めての恋。
確かにそうだ、あの時、自覚していた――自らの声が胸の中に響く。
「その方を近くで見つけた……なるほど。それは気になりますね」
「正確には、近くで働いている、です」
知佳は口を噤んだ。なるほど、それで最近、態度が変わったのか、そう思った。ただ会っただけなら、きっと拓斗の変化など気づかなかっただろう。
「声をかけるべきです」
知佳がキッパリと言った。その力強い断言に驚き、拓斗はまっすぐ知佳の顔を見つめた。
「その方であろうがなかろうが、声をかけて確かめるべきです。でなければ、ずっと引きずりますよ」
「……でも」
「先生はすでにフリーの身です。その方が初恋の人でなくても、すでに先生は好意を寄せられている。あとは、その女性に特別な人がいないことを祈るだけです。先生の恋、応援しますので頑張ってほしいです」
「恋って、知佳さん」
「私も素敵な人を見つけたいと思います。負けませんから」
「…………」
知佳は微笑むと立ち上がった。
「明日からは一スタッフでお願いします。ご馳走様でした」
軽く会釈をすると、振り返ることなく店から出ていった。
拓斗は彼女の後ろ姿を茫然と見送ったが、姿が消えると視線を天井にやった。
婚約者が去っていったこと、
フラれたこと、
次期所長の座を失ったこと、
まったく、つらいとも悔しいとも思わなかった。
脳裏に浮かぶのは、十年も昔の出来事だ。
高校の時のことが蘇っていた。
「…………」
「彼女のことが気になるのは確かです。態度が変わったとおっしゃるなら、それはその女性を見たからだと思います。ですが、それだけです。知佳さんを傷つけるような行動はしていないし、そんな状況でもありません」
知佳は拓斗の言葉にあいまいな微笑みを浮かべた。とはいえ拓斗はその微笑みが否定的であることを理解した。彼女は受け入れる気はないのだと。
「その方かどうか、確かめないのですか?」
「……確かめてどうするんです? 十年も経ったのに、今更」
言いながら、高校時代、少しの間だけつきあっていたクラスメートの顔が蘇った。
十七歳の時の顔だ。大学に入ると、次第に疎遠になり、自然消滅してしまった女性。
(茜)
自分に自信がなくて、いつもはにかんだように微笑む少女。
勉強に忙しくていつの間にか離れてしまったけれど、愛しいと求めた人。
拓斗の中で色褪せ、心の奥底に沈んでしまっていた記憶が鮮やかに蘇った。
「先生、その方のことがまだお好きなんですね」
「……え」
「もしかして、初恋、とか?」
心臓がドキンと跳ねた。
――初恋。
「失礼しました。高校生ですものね。ごめんなさい」
「……いいえ。否定しません。僕はずっと勉強ばかりしてきたから」
拓斗は茫然と答えた。
初恋、初めての恋。
確かにそうだ、あの時、自覚していた――自らの声が胸の中に響く。
「その方を近くで見つけた……なるほど。それは気になりますね」
「正確には、近くで働いている、です」
知佳は口を噤んだ。なるほど、それで最近、態度が変わったのか、そう思った。ただ会っただけなら、きっと拓斗の変化など気づかなかっただろう。
「声をかけるべきです」
知佳がキッパリと言った。その力強い断言に驚き、拓斗はまっすぐ知佳の顔を見つめた。
「その方であろうがなかろうが、声をかけて確かめるべきです。でなければ、ずっと引きずりますよ」
「……でも」
「先生はすでにフリーの身です。その方が初恋の人でなくても、すでに先生は好意を寄せられている。あとは、その女性に特別な人がいないことを祈るだけです。先生の恋、応援しますので頑張ってほしいです」
「恋って、知佳さん」
「私も素敵な人を見つけたいと思います。負けませんから」
「…………」
知佳は微笑むと立ち上がった。
「明日からは一スタッフでお願いします。ご馳走様でした」
軽く会釈をすると、振り返ることなく店から出ていった。
拓斗は彼女の後ろ姿を茫然と見送ったが、姿が消えると視線を天井にやった。
婚約者が去っていったこと、
フラれたこと、
次期所長の座を失ったこと、
まったく、つらいとも悔しいとも思わなかった。
脳裏に浮かぶのは、十年も昔の出来事だ。
高校の時のことが蘇っていた。