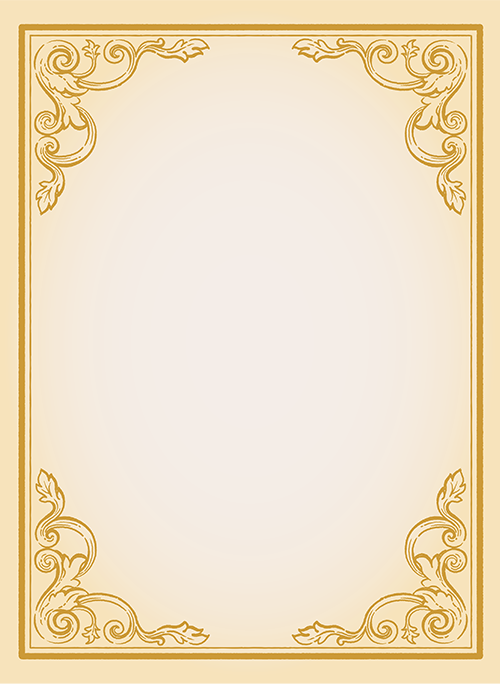「島津君?」
その証拠がこれだ。島津君――茜が名字で呼んでいる。
はにかみながら、想いを込めて『拓斗君』と呼んでくれた茜はもういない。
(どこにもいない――)
「どうしたの?」
「なんでもないよ。時間、いいの? 俺はこれを食ってから帰るけど、夕食の支度とかしなきゃいけないんじゃない?」
途端に茜の顔が曇った。
「……そうだね」
キュッと唇を噛みしめる。拓斗をチラリと見ると、呼出しベルを押した。
「茜?」
店員がすぐにやってきた。茜は拓斗の前に置かれているすっかり冷めてしまったパスタを指差した。
「同じものをお願いします」
「かしこまりました」
店員が去っていくのを見送ってから、拓斗は驚いたように茜の名を呼んだ。
「なに?」
「なにって……食事は家でって言ったじゃないか」
「いいのよ。どうせ残業とかで遅くにしか帰ってこないんだから」
「…………」
「いいのよ、どうせ、どうせ……」
テーブルにぽたりと一滴、悲しみが落ちた。
「ごめん。でも、今日は島津君と食事して帰るわ」
彼女が毎日一人で食事をしていることを感じて胸が苦しくなる。
「島津君がずっと一人で食事してるって話を思い出しちゃった。お父さんが出張三昧で、あまり帰ってこないからって、ウチに呼んだもんね」
「今は早期退職して、田舎でのんびりやってるよ」
茜のパスタが運ばれてきた。二人はそれらを食べながら、高校時代の話を続けた。
十七歳から十八歳にかけての、青春時代の懐かしい話。二人の関係が一歩進んだ時のことを。
その証拠がこれだ。島津君――茜が名字で呼んでいる。
はにかみながら、想いを込めて『拓斗君』と呼んでくれた茜はもういない。
(どこにもいない――)
「どうしたの?」
「なんでもないよ。時間、いいの? 俺はこれを食ってから帰るけど、夕食の支度とかしなきゃいけないんじゃない?」
途端に茜の顔が曇った。
「……そうだね」
キュッと唇を噛みしめる。拓斗をチラリと見ると、呼出しベルを押した。
「茜?」
店員がすぐにやってきた。茜は拓斗の前に置かれているすっかり冷めてしまったパスタを指差した。
「同じものをお願いします」
「かしこまりました」
店員が去っていくのを見送ってから、拓斗は驚いたように茜の名を呼んだ。
「なに?」
「なにって……食事は家でって言ったじゃないか」
「いいのよ。どうせ残業とかで遅くにしか帰ってこないんだから」
「…………」
「いいのよ、どうせ、どうせ……」
テーブルにぽたりと一滴、悲しみが落ちた。
「ごめん。でも、今日は島津君と食事して帰るわ」
彼女が毎日一人で食事をしていることを感じて胸が苦しくなる。
「島津君がずっと一人で食事してるって話を思い出しちゃった。お父さんが出張三昧で、あまり帰ってこないからって、ウチに呼んだもんね」
「今は早期退職して、田舎でのんびりやってるよ」
茜のパスタが運ばれてきた。二人はそれらを食べながら、高校時代の話を続けた。
十七歳から十八歳にかけての、青春時代の懐かしい話。二人の関係が一歩進んだ時のことを。