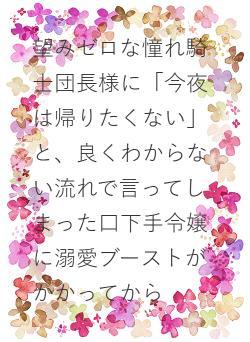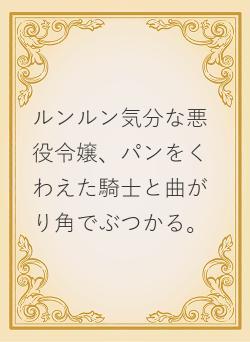「ううん。良いの……私がしたことに比べれば……本当にごめんなさい。フィオナがどれだけ傷ついたかを思えば、私には何の言い訳も出来ないわ」
「……ジャスティナ」
ジャスティナは常に凛として堂々としていた彼女らしくなく、憔悴(しょうすい)した様子で肩をふるわせて泣いていた。
あのエミリオ・ヴェルデが長い時間や多くの手間を掛けて、私のことを自分の思い通りになる存在にしようとしていたことを、今では知っている。
彼がそれをするためには、まず最初に上手く言って取り込まなければならないのは、私の幼馴染みで親友のジャスティナだった。
私も彼を気に入っている様子だしと両思いの二人を橋渡しするのならと、彼からの頼みを軽く引き受けたジャスティナには、一年の間に何度か違和感を感じていたはずだ。
けれど、自分を心から信頼している私には、それを言えなかった。
あまりにも私が彼女のことを褒めていたから、これではガッカリさせてしまうかもしれないと思い怖かったのかもしれない。
「……ジャスティナ」
ジャスティナは常に凛として堂々としていた彼女らしくなく、憔悴(しょうすい)した様子で肩をふるわせて泣いていた。
あのエミリオ・ヴェルデが長い時間や多くの手間を掛けて、私のことを自分の思い通りになる存在にしようとしていたことを、今では知っている。
彼がそれをするためには、まず最初に上手く言って取り込まなければならないのは、私の幼馴染みで親友のジャスティナだった。
私も彼を気に入っている様子だしと両思いの二人を橋渡しするのならと、彼からの頼みを軽く引き受けたジャスティナには、一年の間に何度か違和感を感じていたはずだ。
けれど、自分を心から信頼している私には、それを言えなかった。
あまりにも私が彼女のことを褒めていたから、これではガッカリさせてしまうかもしれないと思い怖かったのかもしれない。