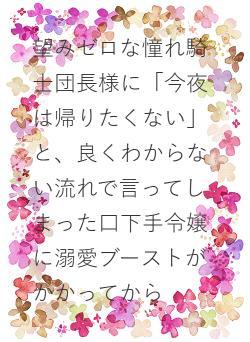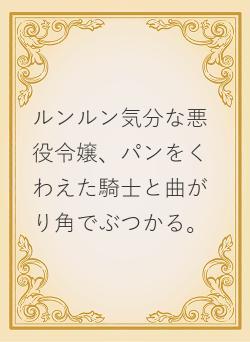絶対に私にとって悪いことだとわかっているのに、これを聞かなければ前に進めない。
近くに居た三人の護衛騎士は、おそらく彼の手の者に何かされている。もしかしたら、買収されているのかも知れない。私の行き先も、彼らの中の誰かがもらしたのかもしれない。
主人の私がこんな状態にあるのに出てこないなんて、おかしいもの。
覚悟を決めた私は、近くに居るエミリオ・ヴェルデを見つめ聞いた。
「何かしら。貴方と私は、何の関係もないはずだけど」
「っ……よくも。いいや。もしかして、ロッソ公爵夫人の知人が、行方不明になっていないかと思ってね。彼の情報は、欲しくないか?」
一瞬笑顔がくずれ怒りの表情を見せた彼は、その言葉を言った後の私の様子を見て満足げな顔になった。
ああ……ルーンさん。貴方が居なくなったのも、私のせいだったのね。
「……なぜ、ルーンさんのことを知っているの?」
答えはわかっていたとしても、どうしても聞いてしまった。だって、これって、全部私の。
近くに居た三人の護衛騎士は、おそらく彼の手の者に何かされている。もしかしたら、買収されているのかも知れない。私の行き先も、彼らの中の誰かがもらしたのかもしれない。
主人の私がこんな状態にあるのに出てこないなんて、おかしいもの。
覚悟を決めた私は、近くに居るエミリオ・ヴェルデを見つめ聞いた。
「何かしら。貴方と私は、何の関係もないはずだけど」
「っ……よくも。いいや。もしかして、ロッソ公爵夫人の知人が、行方不明になっていないかと思ってね。彼の情報は、欲しくないか?」
一瞬笑顔がくずれ怒りの表情を見せた彼は、その言葉を言った後の私の様子を見て満足げな顔になった。
ああ……ルーンさん。貴方が居なくなったのも、私のせいだったのね。
「……なぜ、ルーンさんのことを知っているの?」
答えはわかっていたとしても、どうしても聞いてしまった。だって、これって、全部私の。