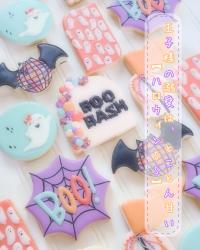「まぁわかるけどね。紫呉って見てくれだけはいいもんなぁ〜」
「はい!…って、中身もカッコイイですよ?」
勢いよく頷いちゃったけど、すぐに否定した。
紫呉さんが優しいのは、もう知っちゃったもん。
斗真さんは私の意見に「やれやれ」と呆れたように首を横に振った。
コソッと耳打ちするように顔を近づけて、手を口元に添える。
「あれは猫かぶるのが上手いだけ。翠ちゃんも、もしかしたら騙されてるかもよ?」
「斗真、聞こえてますよ」
そんな斗真さんを振り返りながらギロリと睨む紫呉さんは、お盆に3つのティーカップを乗せていた。
紅茶のいい香りが部屋いっぱいに広がる。
わぁ…すごい、ティーバッグとは思えないなぁ。
くんくん…と嗅ぐと、喫茶店の匂いがする気がしてきた。