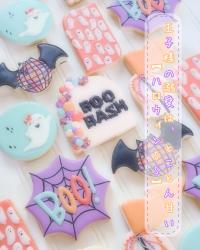それに、紫呉さん私のことを「彼女」って言ってなかった…?
もしかして、私はもう既に紫呉さんの彼女って言う設定になってる?
そういう話は後でするものだと思っていたから、こちらも狼狽えてしまう。
「…ま、愛しの兄ちゃんの彼女を取るほど飢えてないから安心してよ」
ピリついていた空気を先に破ったのは斗真さんの方。
息苦しいこの雰囲気に耐えられなかったため、よかった…と息をつこうとしたんだけど。
「でも…紫呉に飽きたら、俺んとこ来てもいいからね?」
「…っ!?」
私に向かって、キランと効果音がつきそうなウインクを決めた斗真さん。
「斗真、ここでその口を塞いでもいいんですよ…?」
そんな斗真さんに対して、うっすら笑みを浮かべる紫呉さんの目は、まったくもって笑っていない。
「やだなぁ紫呉、冗談じゃん?何珍しくマジになってんの。らしくないよー?」
「笑えない冗談は冗談じゃありません」