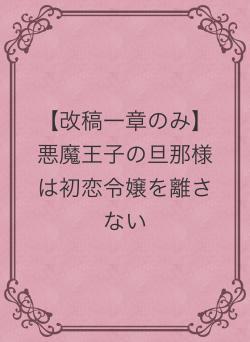男が私が置いていた、びしょ濡れのノートを砂浜から拾い上げた。そしてパラパラと海水に濡れたノートをつまみながら捲っていく。
「ふーん、恋愛小説?」
「ちょっと……返してよっ」
「何?要らないもんなんだろ?だから海に捨てようとしてたんじゃねぇの?」
私は濡れたワンピースの裾を握りしめた。
「……そうよ。私の心からでた要らないモノなのっ!私と一緒よっ、誰からも必要とされてない!」
「要らないモノね……じゃあ燃やしていい?」
「え?」
男はズボンのポケットからライターを取り出しノートに近づける。
嘘は吐いてない。
要らないモノだ。
でも海に捨てても最悪取りに行けるが、燃やしてしまえば跡形もなくなってしまう。
「じゃあ燃やすから」
「やめてっ!」
私は思わず男からノートを取り上げた。男がライターを振りながら、クククッと笑った。
「これオモチャだし、大体びしゃびしゃなのに燃えるわけねーじゃん。てゆうかアンタ小説家なんだ」
「……違うっ、そんなんじゃないっ!ただの物書きだからっ」
「ふーん、恋愛小説?」
「ちょっと……返してよっ」
「何?要らないもんなんだろ?だから海に捨てようとしてたんじゃねぇの?」
私は濡れたワンピースの裾を握りしめた。
「……そうよ。私の心からでた要らないモノなのっ!私と一緒よっ、誰からも必要とされてない!」
「要らないモノね……じゃあ燃やしていい?」
「え?」
男はズボンのポケットからライターを取り出しノートに近づける。
嘘は吐いてない。
要らないモノだ。
でも海に捨てても最悪取りに行けるが、燃やしてしまえば跡形もなくなってしまう。
「じゃあ燃やすから」
「やめてっ!」
私は思わず男からノートを取り上げた。男がライターを振りながら、クククッと笑った。
「これオモチャだし、大体びしゃびしゃなのに燃えるわけねーじゃん。てゆうかアンタ小説家なんだ」
「……違うっ、そんなんじゃないっ!ただの物書きだからっ」