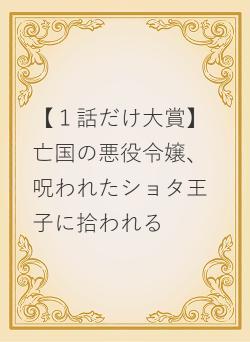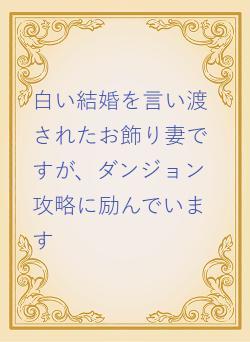テオは、自分がいつ起き上がったのかさえもよく覚えていないほど夢中になってステーキを食べ続けた。
捕食される側だとか、逃げようだとかいうことも忘れて無心でステーキを咀嚼しては胃袋へと流し込み、リリアナと競うかのように「おかわり!」とハリスに空の皿を差し出す。
体が内側からじんわり温かくなっていく。
不思議なことに、食べれば食べるほど体の痛みが取れて元気になり、さらに食欲が増すのだ。
肉質は柔らかく、いくら食べてもあごが疲れない。
味は牛肉に近い気もするが、これまでこんな分厚いステーキを食べた経験のないテオには、なんの肉か相変わらずわからないままだ。
ハリスが1皿ごとに香辛料や付け合わせのハーブを替えて味に変化をつける細やかな気遣いをしてくれるため、単調な味に飽きるということもなく、どんどん食べられる。
ハリスは相変わらず黙々と肉を焼き続けていたが、テオの様子に満足しているのか口元には笑みを浮かべていた。
生肉が残り1枚となった時、リリアナがテオを睨んだ。
「最後の1枚はハリス先生の分だから。ずうずうしくまだ食べたいとか言っちゃダメよ」
「おまえがそれを言うか? いったい何枚食ったんだよ」
テオが呆れながら言い返す。
リリアナは恐ろしい魔物だ。
普段は鍛え上げた腹筋で引き締まっているテオの下っ腹がぽっこり出て少々苦しいというのに、リリアナの腰は薄っぺらいままだ。
あの大量の肉はどこへ消えたのか。
コイツに食べられたらその答えがわかるんだろうか。
そんなことを考えていたらいつの間にかテオの真ん前にリリアナの顔があって、驚いてのけぞった。
「うわっ」
「ずいぶん元気になったじゃないの。さすがは魔牛のステーキね」
「魔牛の肉だったのか……」
魔牛は黒毛の牛型の魔物で、頭部には2本の太いツノがある。普通の牛よりも体がかなり大きく獰猛だ。
まさかあの巨体1頭分の肉をこの食事で食べ尽くしたってことだろうかと考えて、テオはゾッとした。
捕食される側だとか、逃げようだとかいうことも忘れて無心でステーキを咀嚼しては胃袋へと流し込み、リリアナと競うかのように「おかわり!」とハリスに空の皿を差し出す。
体が内側からじんわり温かくなっていく。
不思議なことに、食べれば食べるほど体の痛みが取れて元気になり、さらに食欲が増すのだ。
肉質は柔らかく、いくら食べてもあごが疲れない。
味は牛肉に近い気もするが、これまでこんな分厚いステーキを食べた経験のないテオには、なんの肉か相変わらずわからないままだ。
ハリスが1皿ごとに香辛料や付け合わせのハーブを替えて味に変化をつける細やかな気遣いをしてくれるため、単調な味に飽きるということもなく、どんどん食べられる。
ハリスは相変わらず黙々と肉を焼き続けていたが、テオの様子に満足しているのか口元には笑みを浮かべていた。
生肉が残り1枚となった時、リリアナがテオを睨んだ。
「最後の1枚はハリス先生の分だから。ずうずうしくまだ食べたいとか言っちゃダメよ」
「おまえがそれを言うか? いったい何枚食ったんだよ」
テオが呆れながら言い返す。
リリアナは恐ろしい魔物だ。
普段は鍛え上げた腹筋で引き締まっているテオの下っ腹がぽっこり出て少々苦しいというのに、リリアナの腰は薄っぺらいままだ。
あの大量の肉はどこへ消えたのか。
コイツに食べられたらその答えがわかるんだろうか。
そんなことを考えていたらいつの間にかテオの真ん前にリリアナの顔があって、驚いてのけぞった。
「うわっ」
「ずいぶん元気になったじゃないの。さすがは魔牛のステーキね」
「魔牛の肉だったのか……」
魔牛は黒毛の牛型の魔物で、頭部には2本の太いツノがある。普通の牛よりも体がかなり大きく獰猛だ。
まさかあの巨体1頭分の肉をこの食事で食べ尽くしたってことだろうかと考えて、テオはゾッとした。