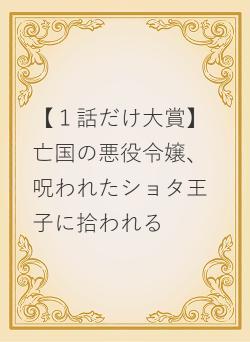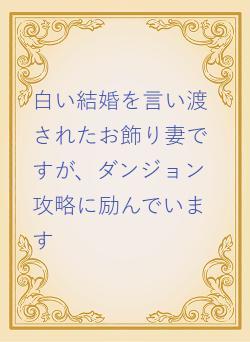ようやく鍋がおとなしくなって蓋を押し上げる感覚もなくなったようだ。
アルノーがおそるおそる手を放しても、蓋は飛ばなかった。
リリアナが蓋を開けてみると、ブワッと香り豊かな湯気が立ち上ったものの中身が吹きこぼれることはなく、スープが完成している。
「「あ~、よかった~~っ!」」
ふたり同時に力が抜けたように尻もちをついた。
洞穴の入り口に喚起のための隙間を少しあけてレジャーシートを張り、さっそくアルミラージの圧力スープを食べてみることにした。
アカニンジンはフォークを刺すとなんの抵抗もなくスッと通るほどやわらかくなっている。口に入れると、とろりと崩れた。しかも驚いたことに、辛さよりも甘みを強く感じる。
大きめに切ったアルミラージの肉も、フォークの背で押すと繊維に沿って簡単にほろりと崩れた。
しっとりやわらかい上に味もよくしみこんでいて、アルミラージの旨味を強く感じる。噛むたびに口の中で深みのある味わいの肉汁が広がり、リリアナは口から大量の湯気を吐き出しながら、遭難中であることを忘れて夢中で食べた。
ハリスが作ったスープと具材と味付けは同じだが、こちらはまるでとろ火でゆっくり時間をかけて煮込んだような出来栄えだ。
ハリスの言っていたことは本当だったと頷きながら食べるリリアナの正面では、アルノーもスープにありついている。
「すっげー美味いのはいいとしてリリアナちゃんってさ、いつもあんな危険な方法で料理してんのか?」
「してないわよ、怒られるもの。これは初めて試してみた方法だったの」
あっけらかんと言ってみせると、アルノーはスープの皿を落としそうになっていた。
「はあっ!? さんざん大丈夫って言ってたのに、初めてってなんだよ。いまさらゾッとしてきたんだけど」
「結果オーライってやつよ。だいたいねえ、わたしのことを雪崩に巻き込んでおきながら、これぐらいでビビらないでくれる?」
これであおいこだと胸を張るリリアナの横に、アルミラージの生肉を食べ終えたコハクが寄り添ってきた。
食事を終えて体が温まり、モフモフのやわらかい毛を撫でているうちに眠気に襲われるリリアナだ。
外はもう真っ暗だから、ここで夜を明かすことになるだろう。
今日は色々なことがありすぎた。魔力もたくさん使ってしまった。あと2日このまま過ごす可能性を考えると、体力も魔力も無駄遣いしてはならない。
アルノーがおそるおそる手を放しても、蓋は飛ばなかった。
リリアナが蓋を開けてみると、ブワッと香り豊かな湯気が立ち上ったものの中身が吹きこぼれることはなく、スープが完成している。
「「あ~、よかった~~っ!」」
ふたり同時に力が抜けたように尻もちをついた。
洞穴の入り口に喚起のための隙間を少しあけてレジャーシートを張り、さっそくアルミラージの圧力スープを食べてみることにした。
アカニンジンはフォークを刺すとなんの抵抗もなくスッと通るほどやわらかくなっている。口に入れると、とろりと崩れた。しかも驚いたことに、辛さよりも甘みを強く感じる。
大きめに切ったアルミラージの肉も、フォークの背で押すと繊維に沿って簡単にほろりと崩れた。
しっとりやわらかい上に味もよくしみこんでいて、アルミラージの旨味を強く感じる。噛むたびに口の中で深みのある味わいの肉汁が広がり、リリアナは口から大量の湯気を吐き出しながら、遭難中であることを忘れて夢中で食べた。
ハリスが作ったスープと具材と味付けは同じだが、こちらはまるでとろ火でゆっくり時間をかけて煮込んだような出来栄えだ。
ハリスの言っていたことは本当だったと頷きながら食べるリリアナの正面では、アルノーもスープにありついている。
「すっげー美味いのはいいとしてリリアナちゃんってさ、いつもあんな危険な方法で料理してんのか?」
「してないわよ、怒られるもの。これは初めて試してみた方法だったの」
あっけらかんと言ってみせると、アルノーはスープの皿を落としそうになっていた。
「はあっ!? さんざん大丈夫って言ってたのに、初めてってなんだよ。いまさらゾッとしてきたんだけど」
「結果オーライってやつよ。だいたいねえ、わたしのことを雪崩に巻き込んでおきながら、これぐらいでビビらないでくれる?」
これであおいこだと胸を張るリリアナの横に、アルミラージの生肉を食べ終えたコハクが寄り添ってきた。
食事を終えて体が温まり、モフモフのやわらかい毛を撫でているうちに眠気に襲われるリリアナだ。
外はもう真っ暗だから、ここで夜を明かすことになるだろう。
今日は色々なことがありすぎた。魔力もたくさん使ってしまった。あと2日このまま過ごす可能性を考えると、体力も魔力も無駄遣いしてはならない。