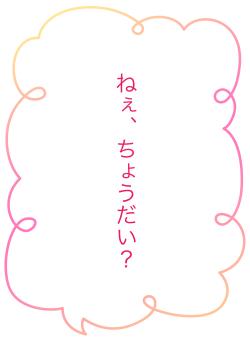「マネージャー、水筒入れてくれ!」
「っはい!」
私、鈴宮リコ。高校1年生。
サッカー部のマネージャーをしてる。
私が2年生の先輩から頼まれて水筒にスポーツドリンクを入れていると、
「鈴宮っ」
「ひゃあ…!」
急に首元が冷たさに襲われ、大きな声をだしてしまった。
後ろを振り向くと、そこにはこのサッカー部のエース兼キャプテンである3年生の相田先輩が水筒と少しの氷を持って立っていた。
「あ、相田先輩…!」
私は恥ずかしさから、顔を赤く染めた。
さっきの冷たさは、たぶん先輩の氷のせいだろう。
「鈴宮、これもよろしくな」
と、相田先輩は手に持っていた水筒を私に手渡して、その手を私の頭にポンッと置いて去っていった。
キラキラと太陽よりも輝く笑顔と共に。
私は先輩に触れられた頭を片手で押さえたまま、先輩の後ろ姿を見送った。
…先輩は、いつも私をからかってくる。
普通はそれを嫌だと思うんだろうけど、私はそうじゃない。
それは先輩のことがずっと好きだから。
先輩に声をかけられるだけで、私の名前を呼ばれるだけで、私の心臓は言うことを聞かなくなる。
ましてや触れられると、そこの部分は途端に熱を持つ。
こんな日常が、これからずっと続くんだ。
…そう思っていた。