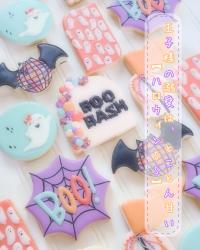「…ほんと、ももは可愛いの塊だよね」
「…っ、そんなこと…」
「あるんだよ」
瑞樹くんは私の言葉を否定するように優しく、でも力強く抱きしめた。
「僕のために頑張って可愛くしてくれようとするのも、チョコレート作ってくれるのも…ももがすること何もかもが、可愛くて仕方ない」
低く甘い声が耳のすぐ近くで響いて、離れない。
頭の中が瑞樹くんで埋め尽くされていく。
これがきっと、「溺れる」ってやつなんだと思う。
「どうしようもなく、もものことが好きでたまらないって…ちゃんと伝わってる?」
「っ、うん…伝わってるよ」