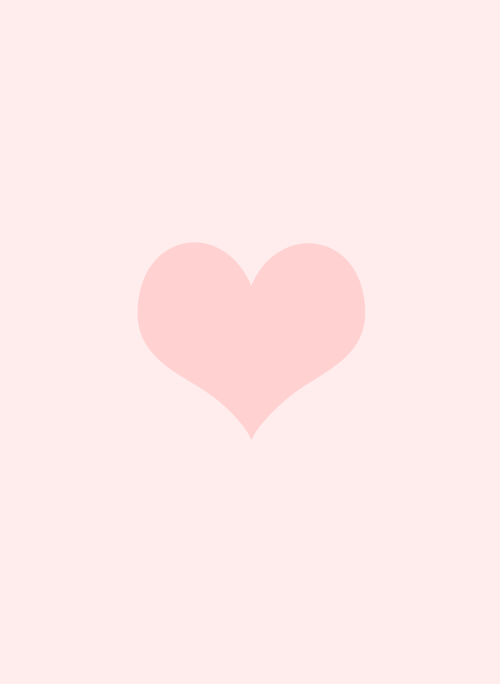――彼女への恋心を自覚したのはいつ頃だっただろうか。ある日、彼女から声をかけてくれた。俺が趣味で書いていた絵を机の横から覗き込んで彼女は言ってくれた。
「うわあ、これ葉山君が書いたの」
「うん、そうだけど」
「ちょっと見せて」
どうしよう。こんなもの書いていると知ったらきっと馬鹿にされるに決まっている。きっと馬鹿にされるんだ。
――しかし、彼女はそんなことなかった。
「これ面白いな。才能あるんじゃない?」
「そ、そうかな」
「うん、きっと才能があるよ。イラストレーターになったら?」
「そんなことないよ。それにイラストレーターって言ってもプロになるなんて難しいし」
「いや、葉山君ならなれるって! だって天才だよ。もしプロになったら真っ先に私に教えてね。一番最初にサインをもらいに行くから」
「うん……」
「約束だよ!!」
――彼女は間違えなく特別な感情とか無かったと思う。どんな人にもこんな調子だし。でも、凄く嬉しかった。その時には好きになっていたのかもしれない。
でもいつしか彼女には恋人が出来ていた。だから俺の気持ちは一生届かないし、言うつもりもない。彼女が幸せそうならそれでいいと思っていた。それなのに――
ある日、いつも明るい彼女は泣いていた。声を殺して凄く悲しそうに。よっぽど悲しいことがあったんだろう。自分の感情を隠す事なく泣いていた。
いつもの俺なら声なんてかけなかっただろう。今まで声をかけた巻き込まれてこっちまでひどい目に合う事が多々あった。もう余計なおせっかいなんてしない。そう決めていたのに。
「大丈夫? 何かあったの?」
気が付いたら俺は声をかけていた。