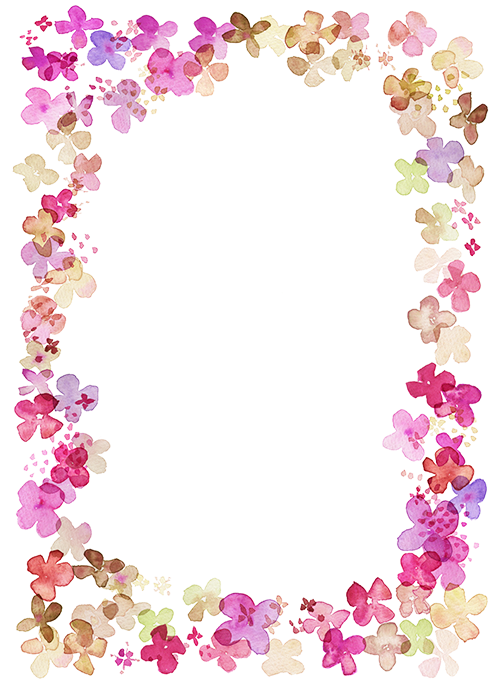公園で別れた俺は、もうひとつの約束の場所へ向かった。
ナナミの家は2階建ての一軒家だ。
隣の家の塀を登って、出っ張りに足をかける。
そして、窓の前のスペース(屋根?)を落ちないように慎重に進むと、ナナミの部屋の窓にたどり着く。
この行き方は小学生の時には頻繁にやっていたけど、さすがに高校生になってからは初めてだった。
俺は窓を開けた。
カギは掛かっていなかった。
靴を脱ぎ、暗い部屋の中へ入った。
数時間前と変わらず、座椅子に座ったままだった。
月明かりに照らされたナナミの愛しい顔が、月に連れて行かれないか…。
心配になる程に綺麗だった。
彼女のことをそっと見下ろした。
『ナナミ…。これ誕生日プレゼント。ベタかもしれないんだけど、ペンダントにした。』
『…。』
『…俺が前に言ったこと、覚えてるか?プレゼントは、喜んでほしいだけなら相手が好きな物。気持ちを伝えたいなら、ロマンチックな物。』
虚な目をしたナナミは何も言わずに、膝を抱えたままの姿で床を見ている。
プレゼントのペンダントが入っている箱を、ローテーブルの上に置いた。
そしてもうひとつ。
『これ、イクヤから。中身は分からないけどさ。渡してくれって頼まれたから。』
そう言ってもうひとつ、リボンが巻かれた小さい箱をローテーブルの上にそっと置いた。
そしてナナミに近づいてから、床に片膝をつく体勢になった。
『イクヤさ。別にナナミを嫌いなわけじゃなかったよ。むしろ好きだったよ。ただ少しだけ。3人とも不器用だっただけだ。』
『…。』
『ちなみに、イクヤがくれた花束の花言葉は、たくさんの小さな思い出…。』
『…。』
ナナミに反応はない。
それでも1人で話し続ける。
今言わないともう…。
『俺達にぴったりの花言葉だと思わないか?なんでもない、だけど大切な…。小さな思い出がたくさんある。だから、10年以上も一緒にいられたんじゃないかって。』
黙ったまま、一切動かない。
まるでナナミの時間だけが止まってしまったみたいに。
それでも口を動かし続ける。
『最後にさ…。俺、ナナミのこと…。ずっと好きだったよ。もちろん、恋愛的な意味で。』
『…!』
『だけど、付き合ってほしいなんて言わない。3人でも2人でも、もう一緒にはいられない…。好きだからこそ、一緒には…。』
『…。』
『全てを知ってしまった今、これ以上一緒にいても…。お互いに傷つけ合ってしまうだけだから。』
『…。』
『よかったら、ペンダントは大事にしてくれると嬉しいな。結構高いやつだぞ?バイトばっかりしてたからさ。金持ってるんだよ。』
『…。』
『もし…。この先、俺なんかよりも。イクヤよりもいい奴と出会えたら…。その時はペンダントは、売るか捨てるかしてくれ。』
『…。』
『じゃあな。また…、3人で会えるといいけどな。』
『…め…ちゃん…。』
ナナミが長い沈黙を破って、口を開いた。
『なん…だ…?』
声が少しだけ震えてしまった。
まだ。
まだ堪えてくれ。
目から何も出ないでくれ。
自分の太ももの辺りを全力でつねった。
『わたしね…。本当にめーちゃんの好きな人は知らなかったんだ…。でもね…。いっくんの好きな人は…。何となく気づいてて…。』
『そ、そう…。だった…のか。』
『気のせいかもって…ずっと思ってたんだけど…。昨日のことで…あ…気のせいじゃないんだって…。』
『…。』
『わたし…わがままだから…。めーちゃんなら許してくれると思って…。焦って…。告白しなきゃって…。いっくんもめーちゃんも両方ほしくて…!』
『うん…。』
『最後に壊しちゃった…。ごめんね…。わたしが1番…ひどいことをしちゃった…。』
『そんなことはないよ。俺達は全員が間違えた。』
ナナミの言うことに口を挟まないつもりだったが、これだけは否定したかった。
『やっぱり…。めーちゃんは優しいね…。わたしね…。2年くらい前から…なんとなく…もう会えなくなるんじゃないかって…気がしてて…その…。』
『うん…。』
もしかしたら、ナナミだけが最初から気付いていたのかもしれない。
ずれているのに心地よく聴こえる、不協和音みたいな、3人の違和感を。
まさか、これから会えなくなるなんて思わなかった。
こんなにも近くに居るのに。
『…うまくまとまらないや。ひとつだけ…。言いたいの。ありがとう。本当にありがとう…。ペンダント大切にするね…!』
『そう…してくれると嬉しい。』
『あとね。わたしも好きだよって、好きだよって言いたいけど…。もう遅いね…。』
俺は微笑した。
『もう言ってるじゃねーか。…でも。聞けてよかったよ。また…な。』
『うん…。また…ね…!』
ナナミの家は2階建ての一軒家だ。
隣の家の塀を登って、出っ張りに足をかける。
そして、窓の前のスペース(屋根?)を落ちないように慎重に進むと、ナナミの部屋の窓にたどり着く。
この行き方は小学生の時には頻繁にやっていたけど、さすがに高校生になってからは初めてだった。
俺は窓を開けた。
カギは掛かっていなかった。
靴を脱ぎ、暗い部屋の中へ入った。
数時間前と変わらず、座椅子に座ったままだった。
月明かりに照らされたナナミの愛しい顔が、月に連れて行かれないか…。
心配になる程に綺麗だった。
彼女のことをそっと見下ろした。
『ナナミ…。これ誕生日プレゼント。ベタかもしれないんだけど、ペンダントにした。』
『…。』
『…俺が前に言ったこと、覚えてるか?プレゼントは、喜んでほしいだけなら相手が好きな物。気持ちを伝えたいなら、ロマンチックな物。』
虚な目をしたナナミは何も言わずに、膝を抱えたままの姿で床を見ている。
プレゼントのペンダントが入っている箱を、ローテーブルの上に置いた。
そしてもうひとつ。
『これ、イクヤから。中身は分からないけどさ。渡してくれって頼まれたから。』
そう言ってもうひとつ、リボンが巻かれた小さい箱をローテーブルの上にそっと置いた。
そしてナナミに近づいてから、床に片膝をつく体勢になった。
『イクヤさ。別にナナミを嫌いなわけじゃなかったよ。むしろ好きだったよ。ただ少しだけ。3人とも不器用だっただけだ。』
『…。』
『ちなみに、イクヤがくれた花束の花言葉は、たくさんの小さな思い出…。』
『…。』
ナナミに反応はない。
それでも1人で話し続ける。
今言わないともう…。
『俺達にぴったりの花言葉だと思わないか?なんでもない、だけど大切な…。小さな思い出がたくさんある。だから、10年以上も一緒にいられたんじゃないかって。』
黙ったまま、一切動かない。
まるでナナミの時間だけが止まってしまったみたいに。
それでも口を動かし続ける。
『最後にさ…。俺、ナナミのこと…。ずっと好きだったよ。もちろん、恋愛的な意味で。』
『…!』
『だけど、付き合ってほしいなんて言わない。3人でも2人でも、もう一緒にはいられない…。好きだからこそ、一緒には…。』
『…。』
『全てを知ってしまった今、これ以上一緒にいても…。お互いに傷つけ合ってしまうだけだから。』
『…。』
『よかったら、ペンダントは大事にしてくれると嬉しいな。結構高いやつだぞ?バイトばっかりしてたからさ。金持ってるんだよ。』
『…。』
『もし…。この先、俺なんかよりも。イクヤよりもいい奴と出会えたら…。その時はペンダントは、売るか捨てるかしてくれ。』
『…。』
『じゃあな。また…、3人で会えるといいけどな。』
『…め…ちゃん…。』
ナナミが長い沈黙を破って、口を開いた。
『なん…だ…?』
声が少しだけ震えてしまった。
まだ。
まだ堪えてくれ。
目から何も出ないでくれ。
自分の太ももの辺りを全力でつねった。
『わたしね…。本当にめーちゃんの好きな人は知らなかったんだ…。でもね…。いっくんの好きな人は…。何となく気づいてて…。』
『そ、そう…。だった…のか。』
『気のせいかもって…ずっと思ってたんだけど…。昨日のことで…あ…気のせいじゃないんだって…。』
『…。』
『わたし…わがままだから…。めーちゃんなら許してくれると思って…。焦って…。告白しなきゃって…。いっくんもめーちゃんも両方ほしくて…!』
『うん…。』
『最後に壊しちゃった…。ごめんね…。わたしが1番…ひどいことをしちゃった…。』
『そんなことはないよ。俺達は全員が間違えた。』
ナナミの言うことに口を挟まないつもりだったが、これだけは否定したかった。
『やっぱり…。めーちゃんは優しいね…。わたしね…。2年くらい前から…なんとなく…もう会えなくなるんじゃないかって…気がしてて…その…。』
『うん…。』
もしかしたら、ナナミだけが最初から気付いていたのかもしれない。
ずれているのに心地よく聴こえる、不協和音みたいな、3人の違和感を。
まさか、これから会えなくなるなんて思わなかった。
こんなにも近くに居るのに。
『…うまくまとまらないや。ひとつだけ…。言いたいの。ありがとう。本当にありがとう…。ペンダント大切にするね…!』
『そう…してくれると嬉しい。』
『あとね。わたしも好きだよって、好きだよって言いたいけど…。もう遅いね…。』
俺は微笑した。
『もう言ってるじゃねーか。…でも。聞けてよかったよ。また…な。』
『うん…。また…ね…!』