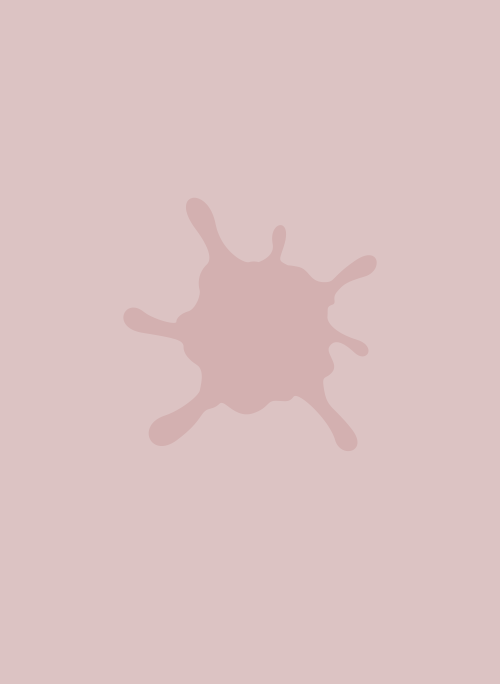驚いて、私達は揃って顔を上げた。
そこにいたのは、ルルシーの派閥の準幹部。
箱庭帝国秘境の里出身の妻を持つ、ルヴィア・クランチェスカだった。
「どうしたの、ルヴィア」
彼の、この青ざめた表情を見るに。
どうやらただ事ではなさそうだね。
呑気にトランプをしている場合…ではなかったかな。
「る、ルルシーさんが…。ルルシーさんだけじゃなくて、ルレイアさんと…ルーチェスさんも…」
青ざめた顔で震えながら、ルヴィアは喘ぐようにそう言った。
ルヴィアがこれほど狼狽えるんだから、本当にただ事じゃないんだね。
「…どうしたの?ルレイアがどうしたって?何があったの?」
ルレイアの名前を聞いて、すかさずシュノが立ち上がった。
「ま、まさか…ルレイアが、ルレイア達が暗殺者に襲われたの?」
シュノは、私が真っ先に思いついたことを口にした。
ルヴィアがこれほど慌てて、報告に来るくらいなのだ。
それくらいのことが起きていてもおかしくない。
私を暗殺する…と見せかけて、ルレイアやルルシー達の命を狙う。
充分に有り得ると思っていた。頭を潰すより、私の腕となる幹部の皆を先に始末する。
そうすれば私は、『青薔薇連合会』で孤独な王と化す。
その危険性は理解していたけれど、ルレイアやルーチェス達に護衛をつけるよう指示はしなかった。
彼らは、自分の身を自分で守れる人達だからだ。
むしろ彼らの場合、護衛をつけたとしても、むしろその護衛が足手まといになりかねない。
そう思ったから、ことさらに護衛をつけることはしなかった…。
それが今になって、裏目に出て…。
…しかし。
「いえ…。そうではなく…」
「…え?」
暗殺者に狙われた訳ではない?
それじゃあ、何が…。
「どうしたの?ルレイアに何が…ルレイアは無事なの?」
シュノは血相を変えて、ルヴィアに掴みかかった。
ルヴィアもまた血相を変えて、そして答えた。
「…無事です。ルレイアさん達は…」
「無事…なの?それじゃあ…どうしたの?ルレイアに何が…」
命は無事。それなのにこうも慌てる理由は…。
…まさか。
「ルヴィア…。落ち着いて。落ち着いて報告してくれるかな」
「は、はい…」
君がそんなに狼狽えていたら、シュノでなくても、私達も不安になるよ。
アリューシャもただならぬ気配を察知して、どうしたものかと不安そうな顔だし。
起きてしまったことは、もう事実として変えようがない。
それよりも冷静に、これからどうするかを考えるべきだ。
その為にもまず…落ち着いて報告して欲しい。
すると。
ルヴィアは一つ深呼吸をして、そして私の目をじっと見つめ。
意を決したように、その重い口を開いた。
「ルレイアさん、ルルシーさん、ルーチェスさんの三名が…サナリ派の…『ブルーローズ・ユニオン』に寝返ったそうです」
…やはり。
そういうことになってしまったか。
そこにいたのは、ルルシーの派閥の準幹部。
箱庭帝国秘境の里出身の妻を持つ、ルヴィア・クランチェスカだった。
「どうしたの、ルヴィア」
彼の、この青ざめた表情を見るに。
どうやらただ事ではなさそうだね。
呑気にトランプをしている場合…ではなかったかな。
「る、ルルシーさんが…。ルルシーさんだけじゃなくて、ルレイアさんと…ルーチェスさんも…」
青ざめた顔で震えながら、ルヴィアは喘ぐようにそう言った。
ルヴィアがこれほど狼狽えるんだから、本当にただ事じゃないんだね。
「…どうしたの?ルレイアがどうしたって?何があったの?」
ルレイアの名前を聞いて、すかさずシュノが立ち上がった。
「ま、まさか…ルレイアが、ルレイア達が暗殺者に襲われたの?」
シュノは、私が真っ先に思いついたことを口にした。
ルヴィアがこれほど慌てて、報告に来るくらいなのだ。
それくらいのことが起きていてもおかしくない。
私を暗殺する…と見せかけて、ルレイアやルルシー達の命を狙う。
充分に有り得ると思っていた。頭を潰すより、私の腕となる幹部の皆を先に始末する。
そうすれば私は、『青薔薇連合会』で孤独な王と化す。
その危険性は理解していたけれど、ルレイアやルーチェス達に護衛をつけるよう指示はしなかった。
彼らは、自分の身を自分で守れる人達だからだ。
むしろ彼らの場合、護衛をつけたとしても、むしろその護衛が足手まといになりかねない。
そう思ったから、ことさらに護衛をつけることはしなかった…。
それが今になって、裏目に出て…。
…しかし。
「いえ…。そうではなく…」
「…え?」
暗殺者に狙われた訳ではない?
それじゃあ、何が…。
「どうしたの?ルレイアに何が…ルレイアは無事なの?」
シュノは血相を変えて、ルヴィアに掴みかかった。
ルヴィアもまた血相を変えて、そして答えた。
「…無事です。ルレイアさん達は…」
「無事…なの?それじゃあ…どうしたの?ルレイアに何が…」
命は無事。それなのにこうも慌てる理由は…。
…まさか。
「ルヴィア…。落ち着いて。落ち着いて報告してくれるかな」
「は、はい…」
君がそんなに狼狽えていたら、シュノでなくても、私達も不安になるよ。
アリューシャもただならぬ気配を察知して、どうしたものかと不安そうな顔だし。
起きてしまったことは、もう事実として変えようがない。
それよりも冷静に、これからどうするかを考えるべきだ。
その為にもまず…落ち着いて報告して欲しい。
すると。
ルヴィアは一つ深呼吸をして、そして私の目をじっと見つめ。
意を決したように、その重い口を開いた。
「ルレイアさん、ルルシーさん、ルーチェスさんの三名が…サナリ派の…『ブルーローズ・ユニオン』に寝返ったそうです」
…やはり。
そういうことになってしまったか。