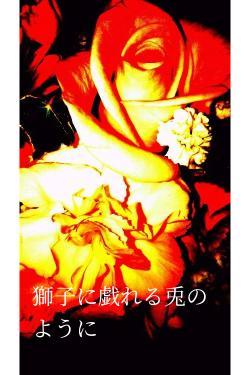―七年後―
ホワイト王国の農村。
七月、農村に唯一あるハイスクールは現在夏休みの真っ只中だった。
ルリアンは母と事実婚をしている義父と三人で借家で暮らしている。義父は移民でルリアンや母ナターリアと同じ黒髪をしている。
十七年前、レッドローズ王国に出稼ぎに行ったきり行方不明となった父タルマン・トルマリン。
そのタルマンが七年前家の前の田んぼで行き倒れとなり、泥まみれのタルマンを発見したナターリアが、リアカーに乗せて家に連れ帰ったのが、ことの始まりだった。
タルマンは記憶喪失で、自分の名前も年齢も住処もわからず、十日以上飲まず食わずで瀕死の状態だったが、顔や体つきは写真で見た父タルマンに瓜二つだったが、変な喋り方や笑い方がルリアンには違和感しかなかった。
だがナターリアはタルマンが家に戻ってきたと大喜びし、再び一緒に暮らすことになった。
(もしもこの人が本当の父なら、それは幽霊かゾンビだ。だって父タルマンは出稼ぎ先で、事故で亡くなったと聞かされていたし、すでに死亡届は提出されている。だから私は父とは認めない。あの人はあくまでも母の事実婚相手、父に激似の義父に過ぎない。)
ルリアンが生まれる前からタルマンは妊婦の母を残して出稼ぎに行っていた。だからルリアンに父の記憶は一切ない。あるのは一枚の写真だけだ。
タルマンはナターリアの献身的な看病により、元気を取り戻したが、記憶は取り戻さなかった。ただ車の運転だけは得意だったため、タルマン・トルマリンとして国に死亡届を取り下げてもらい、再び免許を再取得した。
ナターリアはホワイト王国の裕福な家庭の運転手としてタルマンを働かせてもらっていたが、記憶喪失が災いしてか、癖のある性格が災いしてか、どの雇い主にも馴染めず仕事を転々としていたが、ナターリアは借地で畑や田を耕していたため食料には困らなかった。
ある晩、いつものようにタルマンが言いにくそうにモゴモゴと口を開いた。
「ごめん……ナターリア。実はまた解雇されてしまった。新しい仕事を紹介してもらったんだが、パープル王国なんだ」
(パープル王国!? 冗談でしょう? 出稼ぎしてよ。私はハイスクールがあるんだから。)
「あ、いや、解雇ではなく、これは大変名誉なことなんだよ。私の仕事を認めて下さったあるお方のご指名で、専属運転手にならないかと言われたんだ。極秘情報のため、家族にも赴任先はまだ言えないんだよ」
「義父さん、それ荒手の詐欺じゃないの? 家みたいな貧乏な農家の主人に専属運転手の依頼だなんて。絶対に詐欺だよ」
「私もそう思ったんだが、給金は今よりも上がるし、無償で使用人の宿舎も与えてもらえるんだ。ナターリア、いい話だと思わないか? 実はパープル王国と聞いて、脳の奥がズキンと痛んでな。もしもそこに行ったら、記憶が戻る気がするんだよ」
「……記憶が? タルマンの記憶が戻るなら私は何処だって行くわ。ルリアン、あなたもそうでしょう」
(母さんはいいよ。この人を父さんだと信じているんだから。私はいまでも半信半疑、この人が父親だなんて信じない。だって父と激似しているところは髪の毛の色と眉毛だけなんだからね。もしかしたら、実は悪の組織の一味で母さんと私をパープル王国の奴隷商人にでも売り渡すつもりじゃないの?)
「義父さん、パープル王国の何処に行くの?」
「行き先は心配するな。そのお方は高貴なお方だ。私達が平静お目にかかることのできないくらい高貴なお方だ。だが、何故か私のことを知っているらしい。記憶を無くす前に出稼ぎ先で私の運転する車に乗車されたそうなんだ」
「ますます怪しいわね。義父さんが記憶喪失だとわかった上で嘘をつかれてるのよ。母さん、詐欺だよ。私達奴隷商人に売られちゃうよ。この若さで、やだよ、やだよ」
「ルリアン、父さんを信じてくれ。ナターリアも調理場で働かせて貰える事になっているんだよ。皿洗いだけどな」
「えっ! 母さんもお屋敷で働くの?」
「一緒に雇ってくれるように、条件を出したんだ」
「……なによ、もう二人で決めてるんじゃない」
(私には選択肢はないってことね。正直我が家は裕福な家庭ではない。仕事があるだけ有難いのかもしれない。職を転々とする記憶喪失の義父が高貴なお方からお声がかかるなんて胡散臭いけど。所詮、私達はヤドカリみたいに、住家を転々として暮らさなければいけないんだ。)
◇
そして翌週、必要最低限な荷物以外の家具は全て処分し、私達はワゴン車で新しい雇い主の屋敷に向かった。
――なんと、そこは……。
絵に描いたような豪華絢爛なパープル王国の宮殿だった!!
敷地内の隅に建つ使用人専用の家族用宿舎。警備の者に案内された宿舎の三階のベランダからは、王宮の立派な庭が見えた。
正門から、宮殿の玄関まで続く長い距離を歩いて行くにはルリアンにはムリだと思った。
(これは夢? 私達は王室の奴隷になるの?)
ホワイト王国の農村。
七月、農村に唯一あるハイスクールは現在夏休みの真っ只中だった。
ルリアンは母と事実婚をしている義父と三人で借家で暮らしている。義父は移民でルリアンや母ナターリアと同じ黒髪をしている。
十七年前、レッドローズ王国に出稼ぎに行ったきり行方不明となった父タルマン・トルマリン。
そのタルマンが七年前家の前の田んぼで行き倒れとなり、泥まみれのタルマンを発見したナターリアが、リアカーに乗せて家に連れ帰ったのが、ことの始まりだった。
タルマンは記憶喪失で、自分の名前も年齢も住処もわからず、十日以上飲まず食わずで瀕死の状態だったが、顔や体つきは写真で見た父タルマンに瓜二つだったが、変な喋り方や笑い方がルリアンには違和感しかなかった。
だがナターリアはタルマンが家に戻ってきたと大喜びし、再び一緒に暮らすことになった。
(もしもこの人が本当の父なら、それは幽霊かゾンビだ。だって父タルマンは出稼ぎ先で、事故で亡くなったと聞かされていたし、すでに死亡届は提出されている。だから私は父とは認めない。あの人はあくまでも母の事実婚相手、父に激似の義父に過ぎない。)
ルリアンが生まれる前からタルマンは妊婦の母を残して出稼ぎに行っていた。だからルリアンに父の記憶は一切ない。あるのは一枚の写真だけだ。
タルマンはナターリアの献身的な看病により、元気を取り戻したが、記憶は取り戻さなかった。ただ車の運転だけは得意だったため、タルマン・トルマリンとして国に死亡届を取り下げてもらい、再び免許を再取得した。
ナターリアはホワイト王国の裕福な家庭の運転手としてタルマンを働かせてもらっていたが、記憶喪失が災いしてか、癖のある性格が災いしてか、どの雇い主にも馴染めず仕事を転々としていたが、ナターリアは借地で畑や田を耕していたため食料には困らなかった。
ある晩、いつものようにタルマンが言いにくそうにモゴモゴと口を開いた。
「ごめん……ナターリア。実はまた解雇されてしまった。新しい仕事を紹介してもらったんだが、パープル王国なんだ」
(パープル王国!? 冗談でしょう? 出稼ぎしてよ。私はハイスクールがあるんだから。)
「あ、いや、解雇ではなく、これは大変名誉なことなんだよ。私の仕事を認めて下さったあるお方のご指名で、専属運転手にならないかと言われたんだ。極秘情報のため、家族にも赴任先はまだ言えないんだよ」
「義父さん、それ荒手の詐欺じゃないの? 家みたいな貧乏な農家の主人に専属運転手の依頼だなんて。絶対に詐欺だよ」
「私もそう思ったんだが、給金は今よりも上がるし、無償で使用人の宿舎も与えてもらえるんだ。ナターリア、いい話だと思わないか? 実はパープル王国と聞いて、脳の奥がズキンと痛んでな。もしもそこに行ったら、記憶が戻る気がするんだよ」
「……記憶が? タルマンの記憶が戻るなら私は何処だって行くわ。ルリアン、あなたもそうでしょう」
(母さんはいいよ。この人を父さんだと信じているんだから。私はいまでも半信半疑、この人が父親だなんて信じない。だって父と激似しているところは髪の毛の色と眉毛だけなんだからね。もしかしたら、実は悪の組織の一味で母さんと私をパープル王国の奴隷商人にでも売り渡すつもりじゃないの?)
「義父さん、パープル王国の何処に行くの?」
「行き先は心配するな。そのお方は高貴なお方だ。私達が平静お目にかかることのできないくらい高貴なお方だ。だが、何故か私のことを知っているらしい。記憶を無くす前に出稼ぎ先で私の運転する車に乗車されたそうなんだ」
「ますます怪しいわね。義父さんが記憶喪失だとわかった上で嘘をつかれてるのよ。母さん、詐欺だよ。私達奴隷商人に売られちゃうよ。この若さで、やだよ、やだよ」
「ルリアン、父さんを信じてくれ。ナターリアも調理場で働かせて貰える事になっているんだよ。皿洗いだけどな」
「えっ! 母さんもお屋敷で働くの?」
「一緒に雇ってくれるように、条件を出したんだ」
「……なによ、もう二人で決めてるんじゃない」
(私には選択肢はないってことね。正直我が家は裕福な家庭ではない。仕事があるだけ有難いのかもしれない。職を転々とする記憶喪失の義父が高貴なお方からお声がかかるなんて胡散臭いけど。所詮、私達はヤドカリみたいに、住家を転々として暮らさなければいけないんだ。)
◇
そして翌週、必要最低限な荷物以外の家具は全て処分し、私達はワゴン車で新しい雇い主の屋敷に向かった。
――なんと、そこは……。
絵に描いたような豪華絢爛なパープル王国の宮殿だった!!
敷地内の隅に建つ使用人専用の家族用宿舎。警備の者に案内された宿舎の三階のベランダからは、王宮の立派な庭が見えた。
正門から、宮殿の玄関まで続く長い距離を歩いて行くにはルリアンにはムリだと思った。
(これは夢? 私達は王室の奴隷になるの?)