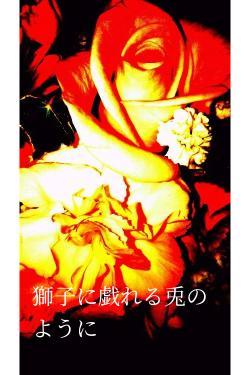気を失ってどれくらい時間が経ったのだろう。目覚めるとワゴン車のエンジン部分からは黒い煙が立ち上がっていた。
「木谷さん! 美梨、昂幸、起きろ!」
五人は大きな怪我もなく全員無事だった。
周囲の景色を見渡し、修は驚愕する。
美梨は赤いドレスを身につけ、昂幸も正装をしている。優は美しい絹のおくるみを身に纏い、木谷は林檎農園のジャンパーを着ていた。修は執事の制服だ……。
「嘘だろう……」
(一体、どっちが現実なんだ?
一体、誰が俺達をこの世界に……?)
―ここはレッドローズ王国―
修と木谷には見覚えのある、あの乙女ゲームの世界だった。
◇◇◇
―同日東京都内・某ゲーム制作会社―
「OK、これでお願いね」
「先生、チェックありがとうございました。まさかあの乙女ゲームのシリーズ2の第一章の原作ができるとは思いませんでしたが、完成したゲームを先生がプレイして下さり、キャラも活き活きしてきました。プレイヤーの一人として第二章が楽しみです」
「ありがとう。もうこんな時間だわ。そろそろ帰宅しないと、主人が心配するから」
「長時間申し訳ございません。先生が結婚され引退されたらどうしようかと思っていましたが、ご主人がこの仕事を認めて下さり、寛大な方でよかったです。引き続き宜しくお願いします」
「そうね。ここで終わるわけにはいかないもの」
彼女は手にしていたパープルの光を放つ万年筆をバックに収めた。その万年筆はking不動産に入社した年の夏に、ある事故を目撃し、その翌日事故現場の近くで拾ったものだ。赤い薔薇が描かれた美しい万年筆が突然パープルの色を放ち、彼女はその光に吸い寄せられるように手に取らずにはいられなかった。大学生の頃から小説や異世界、乙女ゲームが好きだった彼女は、以前から趣味で小説のプロットや第一章を書いていたが、それはありきたりなものであくまでも商業目的ではなかった。
だが万年筆を拾ってからは次々と構想が浮かんだ。我が儘な公爵令嬢が執事と王太子殿下のどちらを選ぶのか、純真なメイドは執事とシェフのどちらを選ぶのか。男女問わずプレイヤーの誰もが推しを選び自分でストーリーを作りあげることができる原作が書けたら面白いと思いながら、暇な時間にその万年筆で書き綴った。第一章を推敲し試しにSNSにペンネームで掲載したら、ラッキーなことにゲーム制作会社の担当者の目にとまり奇跡的に採用された。
その後、第一章の原作と同じことが偶然にも我が身に起き、元彼の身にも起きたことと酷似していることに彼女は気付いた。元彼が他の女性と浮気をしていたのだ。
その後はその元凶と信じて疑わない恋仇の素性や恋仇のその後を探偵を雇って詳細に調べ、それを元に第二章や第三章、第四章と年月を追うように次々と執筆した。それは自分が思い描いているというよりも、万年筆が勝手にキャラクターを創り出し筆を動かしているようだった。
当然、彼女は自分の推しだった執事に元彼が転移したことなんて知る由もなく、元彼への想いを執筆したかっただけ。それなのにプレイヤーは思い通りのプレイはしてくれなかった。不満は募り書き上げたのがシリーズ2だ。
彼女は紫色のスカートを翻し椅子から立ち上がる。左手の薬指にはマリッジリング。コツコツとハイヒールの音を鳴らしながら歩く姿は元OLとは思えないほど、セレブな貴婦人に変貌していた。
「木谷さん! 美梨、昂幸、起きろ!」
五人は大きな怪我もなく全員無事だった。
周囲の景色を見渡し、修は驚愕する。
美梨は赤いドレスを身につけ、昂幸も正装をしている。優は美しい絹のおくるみを身に纏い、木谷は林檎農園のジャンパーを着ていた。修は執事の制服だ……。
「嘘だろう……」
(一体、どっちが現実なんだ?
一体、誰が俺達をこの世界に……?)
―ここはレッドローズ王国―
修と木谷には見覚えのある、あの乙女ゲームの世界だった。
◇◇◇
―同日東京都内・某ゲーム制作会社―
「OK、これでお願いね」
「先生、チェックありがとうございました。まさかあの乙女ゲームのシリーズ2の第一章の原作ができるとは思いませんでしたが、完成したゲームを先生がプレイして下さり、キャラも活き活きしてきました。プレイヤーの一人として第二章が楽しみです」
「ありがとう。もうこんな時間だわ。そろそろ帰宅しないと、主人が心配するから」
「長時間申し訳ございません。先生が結婚され引退されたらどうしようかと思っていましたが、ご主人がこの仕事を認めて下さり、寛大な方でよかったです。引き続き宜しくお願いします」
「そうね。ここで終わるわけにはいかないもの」
彼女は手にしていたパープルの光を放つ万年筆をバックに収めた。その万年筆はking不動産に入社した年の夏に、ある事故を目撃し、その翌日事故現場の近くで拾ったものだ。赤い薔薇が描かれた美しい万年筆が突然パープルの色を放ち、彼女はその光に吸い寄せられるように手に取らずにはいられなかった。大学生の頃から小説や異世界、乙女ゲームが好きだった彼女は、以前から趣味で小説のプロットや第一章を書いていたが、それはありきたりなものであくまでも商業目的ではなかった。
だが万年筆を拾ってからは次々と構想が浮かんだ。我が儘な公爵令嬢が執事と王太子殿下のどちらを選ぶのか、純真なメイドは執事とシェフのどちらを選ぶのか。男女問わずプレイヤーの誰もが推しを選び自分でストーリーを作りあげることができる原作が書けたら面白いと思いながら、暇な時間にその万年筆で書き綴った。第一章を推敲し試しにSNSにペンネームで掲載したら、ラッキーなことにゲーム制作会社の担当者の目にとまり奇跡的に採用された。
その後、第一章の原作と同じことが偶然にも我が身に起き、元彼の身にも起きたことと酷似していることに彼女は気付いた。元彼が他の女性と浮気をしていたのだ。
その後はその元凶と信じて疑わない恋仇の素性や恋仇のその後を探偵を雇って詳細に調べ、それを元に第二章や第三章、第四章と年月を追うように次々と執筆した。それは自分が思い描いているというよりも、万年筆が勝手にキャラクターを創り出し筆を動かしているようだった。
当然、彼女は自分の推しだった執事に元彼が転移したことなんて知る由もなく、元彼への想いを執筆したかっただけ。それなのにプレイヤーは思い通りのプレイはしてくれなかった。不満は募り書き上げたのがシリーズ2だ。
彼女は紫色のスカートを翻し椅子から立ち上がる。左手の薬指にはマリッジリング。コツコツとハイヒールの音を鳴らしながら歩く姿は元OLとは思えないほど、セレブな貴婦人に変貌していた。