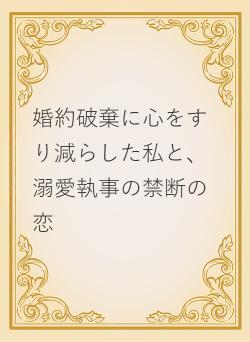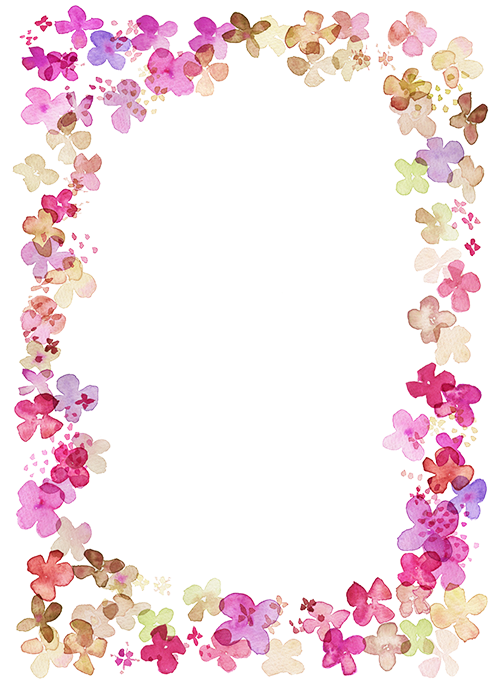「これは千載一遇のチャンスだ。お前みたいな役立たずがようやくこの家の役に立つときが来たんだ。何がなんでも呪いのことを隠して王にすり寄ってこい!」
「え、ええ。かしこまりました」
シェリーは自分を政治の道具にしか思っていない父親の言葉に気づきつつ、そして隣にいる母親がにやりと笑っていることもわかっていて、おとなしく頷いた。
(そうね、呪いで醜い身体をしている上に不幸しかもたらさない『災厄のもと』なんてこの家にいらないものね)
彼女はそっと会釈をすると、そのまま王宮へと向かう迎えの馬車に乗り込んだ。
景色はだんだんと街のにぎやかさが見えてきて、でもそのにぎやかさが今のシェリーの心には苦しかった。
(この婚約は本当にいいのかしら? 国王は呪いのことを知らないのよね? でも私にはもう帰る家もない。隠すしかないの? こうして私はまた不幸を呼び寄せるの?)
「え、ええ。かしこまりました」
シェリーは自分を政治の道具にしか思っていない父親の言葉に気づきつつ、そして隣にいる母親がにやりと笑っていることもわかっていて、おとなしく頷いた。
(そうね、呪いで醜い身体をしている上に不幸しかもたらさない『災厄のもと』なんてこの家にいらないものね)
彼女はそっと会釈をすると、そのまま王宮へと向かう迎えの馬車に乗り込んだ。
景色はだんだんと街のにぎやかさが見えてきて、でもそのにぎやかさが今のシェリーの心には苦しかった。
(この婚約は本当にいいのかしら? 国王は呪いのことを知らないのよね? でも私にはもう帰る家もない。隠すしかないの? こうして私はまた不幸を呼び寄せるの?)