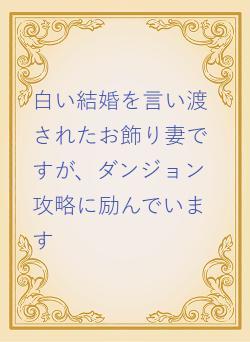今回のグラーツィ伯爵家が自作自演しようとしたと思われる誘拐未遂に関することは、マリエル様を交えて話した方がいいだろうと判断し、ライラ様をマリエル様の寝室へと案内した。
あのまま目を開いたままだったら怖すぎると思っていたが、きちんと目を瞑って眠っていた。
おそらくマリエル様も昨晩は一睡もできなかったのだろう。
ライラ様がベッドの横の椅子に腰かけ、マリエル様の武骨な手に白くて細い指を重ねた。
大きな体や手を怖がる様子は微塵もなく、むしろちょっぴり恥じらってさえいる。
「マリエル様」
彼女のその呼びかけに答えるようにマリエル様がゆっくりと瞼を持ち上げた。
視線を手元に持っていき、そこに重ねられている細い手を辿ってライラ様の顔を無言のままじっと眺めている。
マズい。もしやまた気を失うパターンか!? と身構えたけれど、その予想に反しマリエル様は柔らかく微笑んだ。
「ライラ嬢」
「はい、マリエル様……きゃっ!」
それだけではない。驚いたことにマリエル様は体を起こすと、ライラ様を抱き寄せたのだ。
「まだ夢の中か……いや、まさか、俺死んだのか?」
ライラ様の銀髪を撫でながらそんなことを呟くマリエル様が自分の主ではなかったら、今すぐ靴を脱いで頭をパコーンと殴っているところだ。
「マリエル様、幸か不幸かあなたは死んでいませんし、これは夢ではありません」
マリエル様が驚いた顔でこちらを見て、ギギギッと音がしそうなぎこちない動きで首を元に戻して腕の中で真っ赤になっているライラ様を見た。
「……っな!」
あなたいつも夢の中でこんなことをしているんですね。
そう思いながら待機していたメイドに、スカッと目が覚めるような刺激の強い飲み物を持ってくるよう指示したのだった。
あのまま目を開いたままだったら怖すぎると思っていたが、きちんと目を瞑って眠っていた。
おそらくマリエル様も昨晩は一睡もできなかったのだろう。
ライラ様がベッドの横の椅子に腰かけ、マリエル様の武骨な手に白くて細い指を重ねた。
大きな体や手を怖がる様子は微塵もなく、むしろちょっぴり恥じらってさえいる。
「マリエル様」
彼女のその呼びかけに答えるようにマリエル様がゆっくりと瞼を持ち上げた。
視線を手元に持っていき、そこに重ねられている細い手を辿ってライラ様の顔を無言のままじっと眺めている。
マズい。もしやまた気を失うパターンか!? と身構えたけれど、その予想に反しマリエル様は柔らかく微笑んだ。
「ライラ嬢」
「はい、マリエル様……きゃっ!」
それだけではない。驚いたことにマリエル様は体を起こすと、ライラ様を抱き寄せたのだ。
「まだ夢の中か……いや、まさか、俺死んだのか?」
ライラ様の銀髪を撫でながらそんなことを呟くマリエル様が自分の主ではなかったら、今すぐ靴を脱いで頭をパコーンと殴っているところだ。
「マリエル様、幸か不幸かあなたは死んでいませんし、これは夢ではありません」
マリエル様が驚いた顔でこちらを見て、ギギギッと音がしそうなぎこちない動きで首を元に戻して腕の中で真っ赤になっているライラ様を見た。
「……っな!」
あなたいつも夢の中でこんなことをしているんですね。
そう思いながら待機していたメイドに、スカッと目が覚めるような刺激の強い飲み物を持ってくるよう指示したのだった。