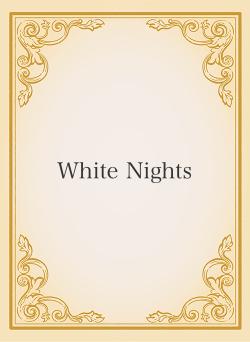隣に視線をやった。
燐も、私を見ていた。
「言っていいよ。全部」
「…」
「私、全部受け止めるよ」
「…マジで?」
「うん。大マジ」
今度もしっかりと頷いた。
燐は、困ったような笑みを浮かべてそのまま
短くなったセブンスターの切れ端をアスファルトにこすりつける。
言いたいことがあるのだろう、ということは、彼の纏う雰囲気に察しがついていた。
きっと、それを敢えて口にはしないだろうということも。
だから、初めからあまり期待はしていなかった。
…だけど。
どうしようもなく膨れ上がった懐かしさが
うまい具合に、彼の肩の力を抜いてくれたようだった。
「───ごめん」
「…」
「ごめんね、エンちゃん」
「…」
「助けられなくて、ごめん」