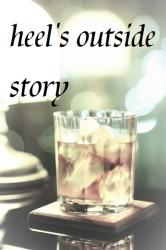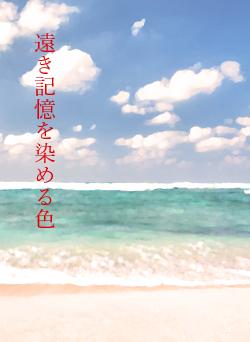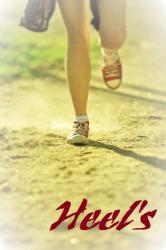閉じ子の伝説/その6
「この慣習は長く続き、何もない平穏時はこんな寒村では考えられないような恵まれた暮らしができるほど、恩賞が藩から与えられたそうなんです。それに生贄を求められるのも、十数年に一度くらいの割合だったせいもあり、村人はこれを受け入れてきたんですね。…ちなみに、それ以降も犠牲となる子は、大人が決めるのではなく、自主的に午後5時に誰かが進んで犠牲になったと伝わっています」
「…」
「…この村と藩は、天災地変から国が裂けるのを救う大義で生贄に差し出される子供たちを”閉じ子”と呼んで、代々その供養を行ってきたということです。もっともこれはあくまで、この地方の言い伝えですが…」
「…克也さん、今聞いてて、単純に夕方5時と女の子の身代わりってことが気にかかりました…」
秋川はズバリ聞いてみた。
...
「ええ。律っちゃんも、自分の体験したこととだぶらせていたでしょうね。彼女にはこう言ったんです。こういう風土が培われたこの地には、今でも閉じ子ような土地の養分になる”さだめ”を無意識の中の意識に受容させる、そんな波動みたいなものは発せられてるかもしれないって…。そして、僕自身もそんな感じを持って生まれた気がするとも言いました」
「それに対して、彼女はなんて言ってましたか?」
「…今、自分もそういう”さだめ”をぼんやりと感じていると…。そう言ってました…。実は、律っちゃんはここで生まれていないけど、そういう素養は持っていたんじゃないかって…。子供の頃、自分と同じみたいだって気はしてたんですよ、僕。まあ、今にして思えばですか…」
「要するに、例の神社で律子さんが体験したことは、この地に培われた閉じ子の風土が導いた現象であると…。彼女はこの地の拘束を生前に無意識の意識で受容した可能性が高いので、それに導かれたのではないかと…。しかし、実際はここには存在しない少年によって、地の養分と化すことは免れた。あなたはそう言った見解を律子さんに告げたんですね?」
「ええ。付け加えれば、その存在しない男の子も、つまり自己犠牲という”さだめ”を受容する意識ってのも、閉じ子の風習が深く土着したこの土地の風土に導かれたものだと思います」
秋川はここまで聞いて鳥肌が立ってきた。そんな刑事である彼を察してか、克也は自分から告げた。
「それで、そこまで僕の話を黙って聞いていた律っちゃんなんですが、僕に尋ねてきたんです。そういう自分の無意識という意識が生まれた土地と”さだめ”を交わす場所って、他にもあるのなかって…。僕は端的に答えました。ここだけじゃない、日本中のあちこちであり得ることだと…」
”克也は、ここだけじゃないと言ったのか、律子に。と言うことは…”、秋川にとって、それは極めて重要な意味を含んだ発言だった。
「この慣習は長く続き、何もない平穏時はこんな寒村では考えられないような恵まれた暮らしができるほど、恩賞が藩から与えられたそうなんです。それに生贄を求められるのも、十数年に一度くらいの割合だったせいもあり、村人はこれを受け入れてきたんですね。…ちなみに、それ以降も犠牲となる子は、大人が決めるのではなく、自主的に午後5時に誰かが進んで犠牲になったと伝わっています」
「…」
「…この村と藩は、天災地変から国が裂けるのを救う大義で生贄に差し出される子供たちを”閉じ子”と呼んで、代々その供養を行ってきたということです。もっともこれはあくまで、この地方の言い伝えですが…」
「…克也さん、今聞いてて、単純に夕方5時と女の子の身代わりってことが気にかかりました…」
秋川はズバリ聞いてみた。
...
「ええ。律っちゃんも、自分の体験したこととだぶらせていたでしょうね。彼女にはこう言ったんです。こういう風土が培われたこの地には、今でも閉じ子ような土地の養分になる”さだめ”を無意識の中の意識に受容させる、そんな波動みたいなものは発せられてるかもしれないって…。そして、僕自身もそんな感じを持って生まれた気がするとも言いました」
「それに対して、彼女はなんて言ってましたか?」
「…今、自分もそういう”さだめ”をぼんやりと感じていると…。そう言ってました…。実は、律っちゃんはここで生まれていないけど、そういう素養は持っていたんじゃないかって…。子供の頃、自分と同じみたいだって気はしてたんですよ、僕。まあ、今にして思えばですか…」
「要するに、例の神社で律子さんが体験したことは、この地に培われた閉じ子の風土が導いた現象であると…。彼女はこの地の拘束を生前に無意識の意識で受容した可能性が高いので、それに導かれたのではないかと…。しかし、実際はここには存在しない少年によって、地の養分と化すことは免れた。あなたはそう言った見解を律子さんに告げたんですね?」
「ええ。付け加えれば、その存在しない男の子も、つまり自己犠牲という”さだめ”を受容する意識ってのも、閉じ子の風習が深く土着したこの土地の風土に導かれたものだと思います」
秋川はここまで聞いて鳥肌が立ってきた。そんな刑事である彼を察してか、克也は自分から告げた。
「それで、そこまで僕の話を黙って聞いていた律っちゃんなんですが、僕に尋ねてきたんです。そういう自分の無意識という意識が生まれた土地と”さだめ”を交わす場所って、他にもあるのなかって…。僕は端的に答えました。ここだけじゃない、日本中のあちこちであり得ることだと…」
”克也は、ここだけじゃないと言ったのか、律子に。と言うことは…”、秋川にとって、それは極めて重要な意味を含んだ発言だった。