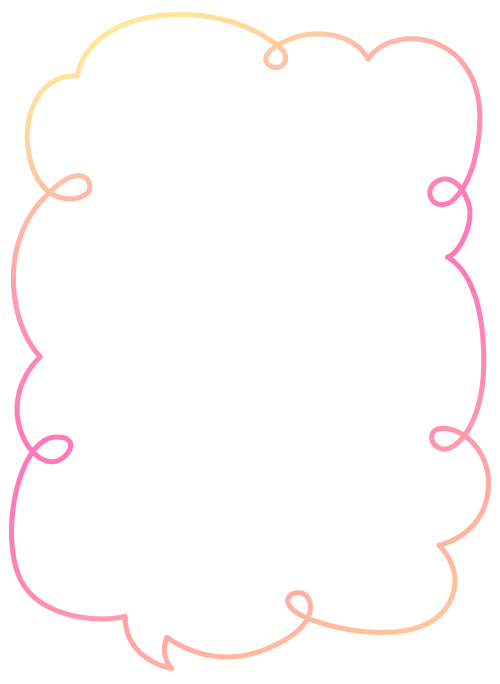翌日、小春は渡り廊下を通って南校舎の三階に来ていた。
そこに横たわる空気はぴりぴりしていて、いかにも受験生がいっぱい居ます、といった雰囲気だ。
思わず気後れしそうになるのを、握り締めたキーホルダーへの意気込みでなんとか廊下を進む。
尾上のクラスが分からないから、三年生の教室を一つずつ覗いて行った。
おどおどと覗くからいけないんだろうと思うけど、覗くたびに教室の中に居た先輩たちに変にからかわれてしまう。
セーラー服のリボンが二年生の緑色なので、それでだと思う。
それでも彼を見つけなければいけないと思った。
三つ目の教室を覗こうとしたときに、丁度廊下の前方に頭ひとつ分飛び出して歩いている人を見つけた。
笠寺だった。
「あれっ? 竹内?」
「笠寺先輩」
緊迫した雰囲気の中、朗らかな笑みにほっとして、廊下を駆け寄った。
すると、賑わう廊下の人を掻き分けて寄った笠寺の隣には彼が居た。
「あ……っ、……」
「お前……っ」
驚いたような彼は、すぐに表情を引き結んで、こちらへつかつかと歩み寄ってくると、キツイ声を飛ばしてきた。
「お前、なんでこんなとこに居るんだっ」
「だ……、だって、先輩……、こ、これ……」
『お前』と呼ばれたことにも気が付けない程、尾上の顔が怖かった。
だけど小春はなんとかそう言って、握り締めていたキーホルダーを差し出した。
笠寺の気持ちの詰まったこれを、どうしても彼に受け取って欲しくて、彼の目の前に差し出し続けた。
すると。
「おーい、尾上。何、後輩たぶらかしてんだよ」
丁度真横の教室からはやし立てるような声が飛んだ。
その声に、尾上が教室の声の主に向かって大きな声を放った。
「うるさい! そんなんじゃないぞ! ちょっと、お前、こっちに来い」
声の半分は小春に向けられたものだった。
そのままぐいぐいと強い力で腕を引かれて廊下を歩く。
笠寺も慌ててついてきてくれた。
廊下をまっすぐ歩き切って突き当たりの階段を踊り場まで下りる。
そこで漸く強く握り締められていた腕を解放してもらえて、小春は思わず腕を擦っていた。
少しぴりぴりした様子の彼に、思わず呼吸が小さくなる。
彼は腕を放すと小春に向き直って、固い声で言った。
「……俺、これのことは忘れてくれって言ったよな?」
確かに彼はそう言っていた。
でも、このキーホルダーに篭められた笠寺の気持ちを考えたら、どうしてもこれはこの人に持っていてもらいたいと思ったのだ。
「で、……でも、笠寺先輩が、折角……。……笠寺先輩の気持ち、無下にしないでください」
憧れの先輩の親友さんに先輩の気持ちを受け取ってもらいたい。
そう思ったが、目の前の人の雰囲気に、つい声が弱々しくなってしまった。
その小春の様子にか、小春の言葉にか、彼はため息をついて、そうして応えてきた。
「笠寺の気持ちなら、昨日貰った。……だから、もうそれは要らないものだし、君が捨てておいてくれたら、それでいい」
「え……、でも……」
戸惑う小春に彼は続ける。
「そんなの、気持ちなんて、物がなくたって残るもんだし、……だからホントに要らないんだ。だから、君が捨ててくれるんだったら、それが一番嬉しいんだけど」
そんな風に言われたって、そんなこと出来ない。
だって、クマにリボンを巻いた時、笠寺は本当に嬉しそうにしていたのだ。
「で……、でも、笠寺先輩は、本当に、……尾上先輩の為に、これを取ろうとしたんですよ……? それを、私が捨てるなんて、出来ません」
お願いですから受け取って下さい、ともう一度キーホルダーを差し出す。
でも、やっぱり硬いため息が漏れ聞こえて、小春はびくりと肩を竦ませてしまった。
「……本当に、笠寺とのことは、物なんてなくてもいいんだ。……でも、もし君がそのキーホルダーになにか気持ち篭めてくれるんだったら、貰ってもいい」
急に矛先を自分に向けられて、小春は一瞬何を言われているのかと思った。
ぱちりと瞬きをして、目の前の人を見ると、思いのほかまっすぐにこちらを見ていた視線にぶつかった。
「え……、と……?」
考える。
このキーホルダーは笠寺が彼の為にと考えたものだから、小春が持っているわけにはいかないと思った。
だから、これを受け取ってもらえるのなら、何とか考えなくては。
「え、と……。……じゃあ、受験、合格しますように、……とか?」
「それ、真剣に思ってるか?」
何とかひねり出した応えに、そんな風に聞かれても困る。
それなのに彼は更に続けた。