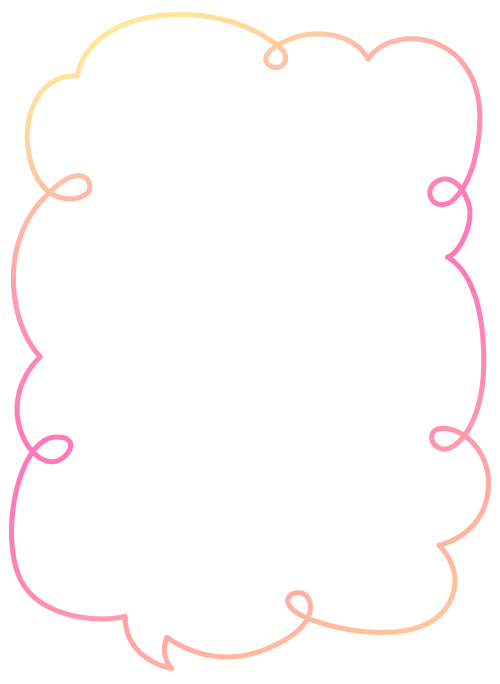話を終えて、下へ降りると言う笠寺と別れて、小春は元来た道を戻ろうとしていた。
東校舎の二階の教室に戻るには、先刻使った三階の渡り廊下を渡らないといけないので、そっちへ歩いていると、丁度通りかかった教室から声を掛けられた。
「あー、先刻尾上に告ってたコだ」
「尾上のどこが良かったの?」
そんな風にやいやいと声を掛けられてびっくりしてしまう。
言われたことに混乱しておたおたしていると、声を掛けてきた人たちが、教室から出てきて、小春の傍に寄ってきて小春を囲む。
「でも振られちゃったの? 慰めてあげようか」
からかうように言われて、かあっと頬に熱が上がった。
そんな風に見られていたなんて、とても心外だ。
「ちが……っ」
「俺たち、尾上よりも優しいぜー?」
笑って言う彼らも、教室から遠巻きに見物している人たちも、本当におもちゃのように小春のことを扱っているのが分かった。
違う、と抗議しようとしたときに、どかっと鈍い音がして、からかうようにして寄ってきた人の一人が廊下に倒れこんだ。
「いってえなぁ! なにすんだよ、尾上!」
「それはこっちの台詞だ。受験でいらいらしてるからって、なに後輩苛めて遊んでんだ」
倒れた人を殴ったと思しき尾上が、小春を背に立って彼を睨んでいる。
何か言おうとした殴られたひとのことを尾上がぎっとねめつけると、彼らは途端に口をぱくぱくさせて教室の中に逃げ込んで行った。
そして、呆気に取られている小春の腕をきつく引くと、尾上はずんずんと歩き出した。
尾上の歩幅は大きくて、引っ張られる小春は足をばたばたさせながらついていくしかない。
「せ……、先輩……」
ぎゅっと握られた手首が酷く痛い。なのに、さっき彼らが恐れたような恐ろしさを、前を行く背中からは感じなかった。
無言のまま廊下を突き当たって、渡り廊下の方へ曲がるまで、尾上は小春の腕を掴んだままだった。
普段人通りのない渡り廊下の半分まで来て、漸く手を離してくれる。
ぎゅっと握られていた分、解放されたそこの脈が大きくなったようだった。
「先輩……」
小春の呼びかけに、漸く尾上が振り向いた。
「……もう、絶対南には来んな。今のことは皆が見てる。いい笑いものにされるぞ、お前」
厳しい声で、言う。
でも、そうだとしたら、尾上はどうだと言うのだろう。
「……先輩は……? 尾上先輩だって、そうでしょう?」
「俺は、いいんだよ。身から出た錆なんだから」
……諦めたように苦笑する尾上の表情に、小春は酷く胸が痛んだ。
だって、そんな風にからかわれる元々の原因は、小春が廊下でキーホルダーを渡そうとしたからだ。
「そんな……っ。だったら、責任は私にあります……。すみません、あんなことして……」
「いいんだよ。竹内は悪くない」
竹内、と呼び捨てで呼ばれた。
その音が思いのほかやさしくてどきっとする。
「……もう、ホントに南には来るな。それから、頼むから忘れてくれ。今のことも含めて、全部」
ひたと見つめてくる真摯な視線が、歪んだ笑みを刷いた口許を裏切っている。
そんな瞳で見つめられたら、忘れろって言われたって忘れられるわけがない。
「……出来ません、そんなこと」
「なんで」
尾上がむっとしたように問うて来る。
それに真面目に向き合った。
「そんな目で見られたら、忘れられるものも忘れられません。……先輩、言葉と行動が噛み合ってないです」
「そんな目ってどんなだよ。お前に俺の何が分かるっていうの」
小春の言葉に機嫌を損ねたのか、尾上は眉間に皺を寄せている。
それでも彼を怖いとは思わなかった。
「だって、笠寺先輩が言ってました。尾上先輩は男気でやさしい人だって」
「笠寺の言うことなんて信用しなくていい」
「それに、私を助けてくれた人じゃないですか」
一度言葉を切って、そして続ける。
「私を助けてくれた人が、……そんな風に真剣に私のこと見てきたら、どうしたんだろうって考えます。忘れるなんて、無理で
す」
「無理じゃない。やってみないうちから無理とか言うな」
「無理ですよ。今だって」
「今?」
疑問をあらわにした尾上の顔に、なんだか笑いがこみ上げてくる。
きっと全くの無自覚なんだろうなあと思った。
「そうですよ。今だって、なんでそんなに必死になってるんだろうって思います。ホントに忘れて欲しかったら、最初からスルーしたらいいじゃないですか」
念押しされたら記憶に残るし、困っているところを助けられたら良い人だって思うのは当然だ。
「だから、尾上先輩の言ってることとやってること、めちゃくちゃですよ。逆に、どうしてそんなに忘れて欲しいんだろうって考えちゃいます」
「……考える?」
「そうですよ。興味出てきちゃいますよ」
意外な応えだったのか、おうむ返しに問われて、小春はそう答えていた。
そうなのだ。
だって、昨日からずっと尾上のことを考えていたのだ。キーホルダーを返すような真似をしてくれなかったら、笠寺と一緒に取ったキーホルダーのことなんていずれ忘れたかもしれないのに、わざわざ小春の目の前に現れて念押しまでして。
それからずっと考えてる。
尾上が何を考えてこんなことをしているのかを。
今だって、目の前で苦虫を噛み潰したような顔をしている尾上のことを、親近感を持って見ている。
最初に会ったときの怖かった印象なんて、もうどこかへ吹き飛んでしまっていた。
ちょっと口が笑ってしまいそうで、それは失礼かと手で隠してみた。
でも、尾上はそれを見逃してはくれなくて。
「……そんなに興味持ってくれたんだったら、もっと持ってもらおうか」
ぼそりと呟かれた言葉を、え? と聞きなおすことはできなかった。
軽く頬を支えられたかと思ったら、目の前に尾上の伏せられた目があって、やわらかいものが触れているのを認識した。
「………っ!」
一瞬でパニックになった。驚きのあまり、硬直してしまった小春のことを、尾上が間近で何者をも惹きつけて止まないような瞳で微笑って見つめてきて、そうしてもう一度言った。
「……興味、持ってろよ?」
言って再び唇が押し当てられる。
やっぱり、目を見開いたままそれを受け止めてしまった。