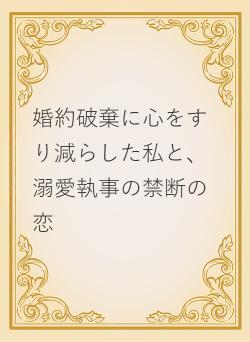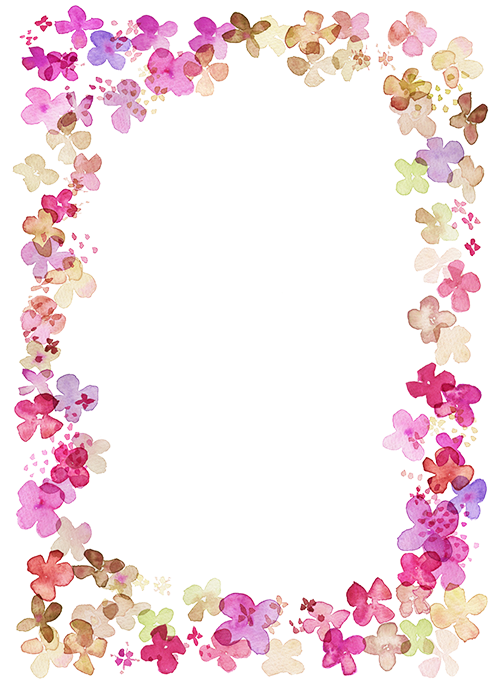書庫室にて作戦会議が開かれた数日後のある日、王妃様が廊下の向こうから来るのが見えたため、私はいつものようにカーテシーで挨拶をして王妃様が通り過ぎるのを待った。
王妃様がすれ違う瞬間にそっと扇で口元を隠しながら私に対してそっと呟いた。
「あなた、わたくしが“行ってはいけない”と言ったところに行ったそうじゃない?」
(──っ!)
すぐに書庫室のことだと思い否定しようとしたが、違和感に気づき私は落ち着きを持ったいつものおしとやかな令嬢口調で返答した。
「申し訳ございません。王妃様はわたくしに行ってはならないと仰った場所などないと思うのですが、ご気分を害されることをわたくしはしてしまったのでしょうか」
「…………ええ、そうね。行ったらいけないなんて言ったことないわよね。ごめんなさい、勘違いだったわ」
「いえ、寒くなってきたので王妃様もお体にはお気をつけくださいませ」
「ええ、ありがとう」
そう言いながら王妃様は私のもとを去っていった。
王妃様が去ったあとで唾を一つごくりと飲んだ。
私の心臓はドクドクと脈打つように鳴っており、心の中では恐怖心で溢れていた。
(そうだ。『行ってはならない』とは言われていない。おそらく私に行くなと暗示をかけさせた。記憶を取り戻したかを探って来たということはやはり王妃様は黒)
私の額に一筋の汗が流れたのを拭うと、その足で自室へと向かった。
王妃様がすれ違う瞬間にそっと扇で口元を隠しながら私に対してそっと呟いた。
「あなた、わたくしが“行ってはいけない”と言ったところに行ったそうじゃない?」
(──っ!)
すぐに書庫室のことだと思い否定しようとしたが、違和感に気づき私は落ち着きを持ったいつものおしとやかな令嬢口調で返答した。
「申し訳ございません。王妃様はわたくしに行ってはならないと仰った場所などないと思うのですが、ご気分を害されることをわたくしはしてしまったのでしょうか」
「…………ええ、そうね。行ったらいけないなんて言ったことないわよね。ごめんなさい、勘違いだったわ」
「いえ、寒くなってきたので王妃様もお体にはお気をつけくださいませ」
「ええ、ありがとう」
そう言いながら王妃様は私のもとを去っていった。
王妃様が去ったあとで唾を一つごくりと飲んだ。
私の心臓はドクドクと脈打つように鳴っており、心の中では恐怖心で溢れていた。
(そうだ。『行ってはならない』とは言われていない。おそらく私に行くなと暗示をかけさせた。記憶を取り戻したかを探って来たということはやはり王妃様は黒)
私の額に一筋の汗が流れたのを拭うと、その足で自室へと向かった。