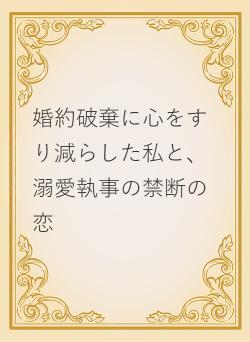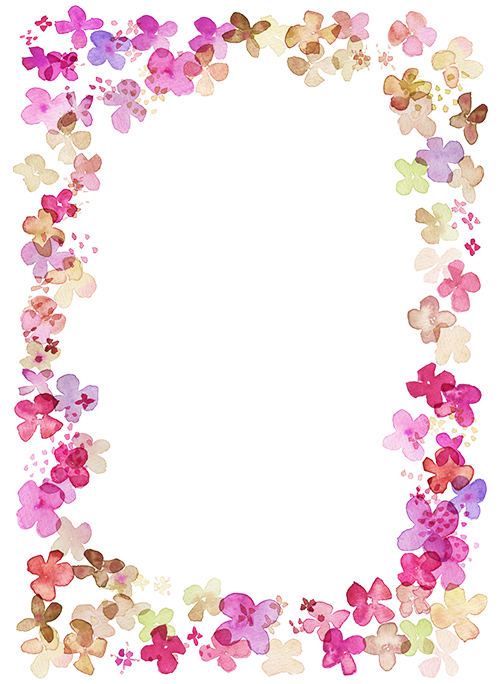そうしてわたくしの両親に誓いを立てた婚約から5年の月日が経ち、私も王太子妃教育を受けて少しずつですがエリクさまのお隣に立つ準備をしておりました。
エリクさまは漆黒の髪にグレーの瞳というそれは見目麗しい容姿をなさっているので、女性からの人気が高いのです。
さらにご公務も非常に優れた才覚を発揮されて全うされておりますゆえ、側近の方や宰相閣下からのご信頼も厚くひっきりなしに「殿下」「殿下」と呼ぶ声が王宮に響き渡ります。
そんなエリクさまですから、二人でのデートもままならず、わたくしは少し寂しい思いをしておりました。
(ご公務が忙しいのは仕方ないけれど、5日も会えないと寂しいものですね)
私はいつも通り王宮にて王太子妃教育を終えた後、立派な絵が飾られた廊下を歩いていました。
すると、向こうからシルバーの髪に碧眼の美しい第二王子ユリウス・リ・スタリー様がいらっしゃり、わたくしはカーテシーでご挨拶をします。
「今日も王太子妃教育ですか?」
「ええ、まだまだうまくできないことも多々ございます。精進しております」
「おや、ユリウスではないか。こらこら、兄の婚約者をかどわかしていたのか?」
後ろからエリクさまがやって来られ、そのお姿を見てわたくしは再びカーテシーでご挨拶をします。
「いえ、そのようなおつもりでは」
「そうか? まあいい。そういえば母上がお呼びだったぞ」
「……かしこまりました。すぐに行ってまいります」
ユリウスさまはエリクさまのそのお言葉を聞くと、さっと胸の前に手を当ててお辞儀して、私たちとすれ違って歩いて行かれました。
「リーディア。よかったら少し部屋で話をしないか?」
「そんな、お忙しいのによろしいのですか?」
「いいんだ、リーディアと久々に話がしたくてね。いいかい?」
懇願する幼子のような表情を浮かべられれば、わたくしが断ることなんてできましょうか。
お言葉に甘えてわたくしはエリクさまと共に部屋へと向かいました。
エリクさまは漆黒の髪にグレーの瞳というそれは見目麗しい容姿をなさっているので、女性からの人気が高いのです。
さらにご公務も非常に優れた才覚を発揮されて全うされておりますゆえ、側近の方や宰相閣下からのご信頼も厚くひっきりなしに「殿下」「殿下」と呼ぶ声が王宮に響き渡ります。
そんなエリクさまですから、二人でのデートもままならず、わたくしは少し寂しい思いをしておりました。
(ご公務が忙しいのは仕方ないけれど、5日も会えないと寂しいものですね)
私はいつも通り王宮にて王太子妃教育を終えた後、立派な絵が飾られた廊下を歩いていました。
すると、向こうからシルバーの髪に碧眼の美しい第二王子ユリウス・リ・スタリー様がいらっしゃり、わたくしはカーテシーでご挨拶をします。
「今日も王太子妃教育ですか?」
「ええ、まだまだうまくできないことも多々ございます。精進しております」
「おや、ユリウスではないか。こらこら、兄の婚約者をかどわかしていたのか?」
後ろからエリクさまがやって来られ、そのお姿を見てわたくしは再びカーテシーでご挨拶をします。
「いえ、そのようなおつもりでは」
「そうか? まあいい。そういえば母上がお呼びだったぞ」
「……かしこまりました。すぐに行ってまいります」
ユリウスさまはエリクさまのそのお言葉を聞くと、さっと胸の前に手を当ててお辞儀して、私たちとすれ違って歩いて行かれました。
「リーディア。よかったら少し部屋で話をしないか?」
「そんな、お忙しいのによろしいのですか?」
「いいんだ、リーディアと久々に話がしたくてね。いいかい?」
懇願する幼子のような表情を浮かべられれば、わたくしが断ることなんてできましょうか。
お言葉に甘えてわたくしはエリクさまと共に部屋へと向かいました。