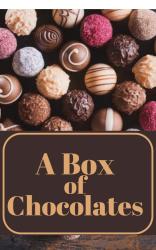蒼のてのひらの刺創の抜糸が済んだころ。
リュン君が帰国することになった。
ひと月半の間、今まで7年間知らなかったなんて嘘のように、彼は私たちとの生活にすっかり馴染んでいた。
暉と、時には父も一緒に温泉、山登り、キャンプにバーベキューと自然を満喫し、私とは料理したり買い物に行ったり本を読んだりして、日本語もだいぶうまくなっていた。子供ってすごい。
庭で流しそうめんをしたし、肉フェスや花火大会も体験して、浴衣も着た。暉と父がそれぞれリュン君を手をつなぎ、3人で楽しそうに屋台巡りしていたのはほほえましかったな。
父も「おじいちゃん」と呼ばれるのがすっかり板についたみたい。
来た時よりも荷物が増えて、帰るときには1週間分入る60Lサイズのスーツケースを買うことになった。そして一人ではなく、暉が一緒に行くことになった。
リュン君をアルルに送り届けた後、2か月ほど南ヨーロッパと北アフリカを回って仕事をしてくることにしたらしい。それからいったん帰国してまたクリスマスとお正月は北欧と東ヨーロッパとNY。また帰国して2月、3月は再びヨーロッパで春のカーニバル巡り。
夜の空港。
私は蒼と一緒にふたりを見送りに行った。
世間は夏休み。夜遅くても出発ロビーは人でごった返している。
「リュン君、寂しくなるよ」
私は小さな甥っ子をハグする。
「僕も。フェイスタイムで時々お話ししようね。それから、また絶対に来るよ。朔ちゃんも、アルルに遊びに来てね」
リュン君も私をきゅっとハグする。
「リュン、暉をよろしくな」
蒼が言うと、リュン君はふふ、と笑ってうなずいた。
「ソウも、朔ちゃんをよろしくね」
「さぁ、そろそろ行くぞ。じゃあ、あとは頼むな」
暉はリュン君を促して私たちに手を上げた。
ふたりがゲートの中に入っていく。
「たったひと月半で、もう離れるのがつらくなちゃった」
「あいつ、将来は日本に住みたいって言ってたし、そのうちまた来るよ」
蒼は手を差し出した。
「朔。行こう」
当然のように、その手に自分の手を差し出す。私ははは、と笑う。
「ここはほんとに迷子になりそうなくらいすごい人だね」
大きなスーツケースやバックパック、サーフボードを持つ人々が行きかう。まるで街中のスクランブル交差点みたい。
蒼は私を振り返って口角を上げる。
「大丈夫だよ。どんな雑踏の中でも、俺は朔をぜったに見つける自信があるから」
私は驚きで目を丸く見開く。
「なによ、初めて一緒に出掛けたときは、『見つけるのが難しそう』って言ってたくせに」
ゆっくりと歩き出し、蒼は天井を向いてあははと笑う。
「そんなのは、手をつなぐ口実だって普通わかるだろう?」
「ええ?」
「はぐれたら、電話すれば一発だよ」
私は口をへの字に曲げる。
「そういうこと? なぁんだ……」
「いや」
「うん?」
「電話が通じなくても、朔のことはちゃんと、かならず見つける」
ふーん……
なんか、こそばゆい。
見学デッキへ。
ナイトフライトの飛行機の離発着を、私たちは手すり越しに並んで眺めている。
航空灯火の青や赤、緑、オレンジのライトは、まるで地上に星が落ちたみたいでとてもきれい。
「いいなぁ。私もリュン君と一緒に行きたいな……海外なんて、何回か出張でしか行ったことがないよ」
「なんだ、あの男としか海外に行ったことがないってことか」
「仕事でしか、行ったことがないってこと!」
まだ包帯の取れていない左手を狙って叩こうとすると、素早く手首をつかまれる。
「完治してないほうの手を狙うとは、こんなひどい女だったのか?」
「そうさせる人がいるからとは思わない?」
「なんでだよ? 誰よりも大事にしてるのに」
「誰よりもからかってる、でしょ!」
「ちがう。違うってば。おいっ……」
左手でわき腹をくすぐると、蒼は身をよじって逃げようとする。
私はむきになって手を伸ばすけど、身長差と腕の長さの差でかすりもしない。
頭を鷲づかみにされてじたばたしているのを見て蒼が笑う。だから顔を伏せて泣きまねをする。
「おい、なに? 泣いてるのか? 朔?」
ふふ。チョロいのはどっちかな?
「……ひどい。もう口もききたくない」
「……」
「私はもっと、優しい人がいい。こんな意地悪なひとじゃなくて……」
「……」
「先に帰るね。じゃあ……」
うつむいたまま去ろうとすると、手をつかまれる。そこで私がこらえきれずにくっと笑いを漏らす。
「普段の仕返し」
――時が止まる。蒼は私の手をつかんだまはっとした表情のまま固まる。私は蒼に向きなおり、顔を覗き込む。
「蒼?」
蒼は私をぎゅうううと抱きしめる。しめる。締めすぎて、く、苦しい。
背中をタップする。
「いき、ができない、よ」
すこし、力が弱まる。どうした?!
「墓穴を掘った」
「え?」
「出張なんか行ったら、ほとんどの時間、一緒にいたよな。なんでそれで惚れなかった?」
「はぁ。なんで惚れないといけないの? 翔ちゃんみたいなこと言わないでよ。出張って、仕事が目的で行くんだよ?」
「あんな上司と四六時中一緒で何もないのはおかしいだろ?」
「おかしくない。えっ、まさか、蒼……」
やきもち?!
「何をにやにやと」
「上司と仕事でしか行ったことないの、海外。かわいそうでしょ? だからいつか、どこかに連れて行ってね?」
私は蒼を見上げる。
「どこに行きたい?」
ああ、機嫌が直った。
「んー、そうだね……例えば、トニさんの故郷のドゥブロヴニクとか、ギリシアのサントリーニとか、イタリアのなんだっけ、白い円筒の壁に三角屋根の村……」
「アルベロベッロ?」
「そうそう! そことか……なるべくなら、寒くないところがいいんだけど。でも第一条件は、一緒に行けるところ。それならどこでもいいかな」
「それ」
「え?」
「それ、全部行こう。いつか、絶対に」
蒼が私の髪を撫でる。私は蒼を抱きしめる。
真夏のまといつくようなまったりした夜気の中を、海風がさらさらと吹き抜けてゆく。
蒼といると私はいろいろな感情を敏感に自覚する。うれしいとか、楽しいとか、幸せだとか。不安だとかもやっととか、むかっととか。
でも私だけじゃなく、蒼もきっと同じなんだろうな。
私が誰かに感情的になって、誰かが私に感情的になる。
それって、すごいことだ。
それから私たちはしばらくデッキの光の海の中で、行ったことのない行ってみたい場所についてとりとめもなく話し合った。
頭上を離発着する、夜間飛行の機体を時折見上げながら。