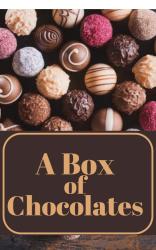私は蒼を見上げた。
「頼み?」
珍しい言い方。「命令」とか言わないんだ?
「来週末、事務所の恒例行事らしい三事務所合同の若手の親睦会みたいな食事会があるらしいんだ。それに一緒に来てほしいんだけど」
それは親世代が若いころから初めたものらしく、結構昔から定期的に行われている会らしい。
目的は人脈作りと交流と情報交換、そして腹の探り合い。各自同伴者を一人連れていける。
今回は蒼の言う「マウンティング野郎」こと同じ事務所のアソシエイトの父親の別荘でする、ケータリングのバッフェスタイルパーティ。ホストはその彼のお兄さんとのこと。
「あんたが来ないとホテルの結婚式のあとみたいに、また何かが俺のあとついてくるかもしれないだろう?」
私は半眼でじっと蒼を見る。ああ、なるほどね。そうですか、そうですよね。はいはい。
「——なんて、冗談。絶対面白くないはずだから、適当に切り上げてどこか別のところに行こう」
私は蒼の肩にもたれて思わず笑ってしまう。
「絶対面白くないところに一緒に来いって言うの?」
「来いとは言ってない。来てほしいって言ってる。一緒に来てくれれば、面白くなくても多少は耐えられるから」
「あなたって……時々、かわいいこと言うよね。リュン君みたい」
「は? 7歳児と一緒にするなんて、失礼すぎないか?」
「自分だって、暉とヒロトさんを中身は8歳って言ったくせに」
「よくそんなこと覚えてるな。それで、返事は?」
「いいよ、しかたないな」
蒼は私にハグして、私の頭の上に自分のあごを載せて空を見上げた。
「ふん、少し楽しみなったな」
「そのパーティ?」
「いや、そのあと、どこに行こうかなって。リクエストがあれば明日まで受け付けることにしよう」
「短くない⁈」
あはは、と蒼は笑う。
なんか、これって、すごく……幸せかも。心の中がいろんな色のふわふわの綿あめで、ぎゅうぎゅう詰めになっているみたい。
私も空を見上げる。ぽっかりと浮かんだ銀色の満月は、今夜の夜空の主役。
「私、小さな頃はね、自分の名前がああいう満月って意味だと思って誇らしかったんだ。でもお父さんに新月って意味だよって知らされて、すごく落ち込んだ。新月って、真っ暗で姿が見えないじゃない?」
「朔っていうのは、月が太陽と地球の間にあって、ちょうど陰になるからな。新月生まれだから教授は朔って名前を付けたんだよな? でもすべての始まりなんだから、悪くはない」
「うわ、びっくりだよ。小学生の頃、男子に名前をからかわれて泣いたときに、暉が言ったこととおんなじ!」
「知ってる。暉は朔の意味を教授に聞いたって言ってた」
「そっか。そんなことも、話してたんだ?」
「うん、だから俺は高校の頃からあんたのこと間接的に知ってたってことかな」
「それなら、半年前にあのホテルのバーで出会ったのは、スーパームーンみたいなものだったんだね」
「スーパームーン? 近点満月か」
月は地球の周りを自転していて、その軌道は楕円だから、地球から遠ざかっているときは月が小さく見えるし、一番近い軌道上の時には大きく見える。天文学では近点満月とか近点惑星直列と呼ぶらしいけど、「スーパームーン」という占いから生まれた言い方が一般的に知れ渡っている。
「高校の頃は遠いところにあったけど、半年前は近点だった。だから出会ったんじゃない? 私は私の軌道上を普通に進んでいただけ。それである時、蒼に会った。暉という共通の存在がいるから、不思議じゃなかったんだね」
太陽と地球と月との、因果律。
「うまいこと言うね。あの夜、俺の目に入ったのは朔が持っていたあのバカ高いワインだったから、あれが俺のスーパームーンだったか!」
「……ワインか。11万円のワインとの運命的な出会い、おめでとうございました」
「今、ムカついたろう? うそだよ。ワインなんかどうでもいい。本当は、あの日は俺だけの新月を見つけたんだよ」
うん?
あの時……よく思い出してみよう。
ワインをお裾分けして話しているうちに私が酔っぱらってきて、ワインをくれた上司のこととか、私が駿也と別れたばかりってこととか、糸の切れた凧のような双子の兄のこととか、実家のこととか、子供の頃のこととか、高校のこととかいろいろしゃべって……蒼はなんとなく双子の兄の話辺りから、私が暉の妹だって見当をつけたんだよね?
それで、酔っぱらった私に誘われて(一生の不覚!)、言った。
『後悔して泣いても、知らないからな』
そんなことを言ったくせに……すべては、想定されていた!
翌朝、私が逃げた(逃げたとは認めてないけど、事実ではある)あと、暉に会っていくつか確かめてますます確信を深め、数日後の暉のSNSの画像で仮装した私を見て確信したって、そういう流れでしょう?
私はずっと、蒼の描いた軌道の上を何も気づかずに進んでいただけにすぎなかった……
「腹黒……」
私のつぶやきに蒼はくすりと笑う。
「あんたに逃げられた時から、確実に手に入れられるように画策したんだ。おかげで今は、ずっとスーパームーン状態だ。そうだろう?」
こめかみに、キスが落ちてくる。
心が、こそばゆい。
「なぁ、朔」
「うん?」
「上、見て。月がきれいだな」
あ、それは。
夏目漱石の、有名な翻訳。
『月がきれいですね』
知っていて、言ってるのかな? それとも、何も意図せずに?
私は笑みを浮かべる。
どっちでも、いいや。
「ん。今まで見た中で、一番きれい」
あなたと一緒に、見ているから。
この世には、私たちだけしか存在しないみたい。
私たちと、紺色の空にぽっかりと浮かぶあの月だけ。
「そうか」
初めは、たった一度きりの関係のはずだった。
だからもう、会うことなんてないと思っていたけど。
欲望や情熱とはどういうものなのかを知らされて。
心までぐらぐらに揺らされて振り回されて、翻弄されて。
それでもいつのまにやら、私のもやもやはどこかに消え失せた。
次のスーパームーンも、マイクロムーンも、そのまた次のスーパームーンも、普通の満月も、見えない新月さえも。
この先も、何度でも。
あなたと一緒に見られたら、どんなにすてきだろう。