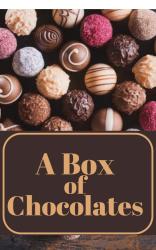白のシフォンブラウス、紺のひざ丈マーメイドスカート、紺のジャケット。5㎝ヒールのグレージュのポインテッドトウのパンプス。黒い革のトートバッグを右の肩にかけ、右手にはA4サイズの白封筒を持っている。チョコレートブラウンの緩めのミディアムロングの髪、ハイブランドのロゴ入りイヤリング。
その人は海里君ににっこりと笑んで言った。
「渋谷先生、いらっしゃいます?」
海里君は不安げに私を振り返った。蒼は屋根部屋で何か書類に目を通していると言っていた。
「失礼ですが……」
海里君が遠慮がちに尋ねる。
「わたくし、渋谷法律事務所の桐生と申します。書類のお届けに上がりました」
私は海里君にうなずいて階段を上がった。
「蒼。お客さん」
「誰?」
ソファに座り書類を読んでいた蒼は顔を上げずに言った。
「桐生さん?」
「え? ああ、わかった。これ読んだら行くよ」
先に降りていくと、海里君と女性はまだドアのところにいた。
「どうぞ、すぐに来るそうですので、こちらでお待ちください」
女性は私を一瞬のうちにスキャンしたみたい。秘書をしていて専務に同行した出先で女性からよくされていたので、そういう値踏みする視線には慣れていてすぐに感知できる。
法律事務所の人……
うわぁ……このひと、どっちなんだろう?
事務員? パラリーガル?
「おそれいります」
彼女はふ、と目を伏せて軽く会釈すると、大テーブルの脇まで優雅に歩いてきた。席を示したけど、笑顔で首を横に振る。
ちら、と彼女が私を見る。
私が見ると視線を自然に反らす。
蒼が降りてくる。女性を見るなり、眉間にぴく、としわを寄せる。
「あっ、おつかれさまです」
彼女は蒼を見ると丁寧に頭を下げた。そしてこつこつとヒールの音を響かせてフロアを横切り、蒼の前まで来ると白い封筒を差し出した。
「起案の追加資料をお持ちしました」
「それはご苦労様。でもメールもらえれば明日にでも取りに行ったのに」
→翻訳。《なんでわざわざ持ってきたんだよ?》
女性はにっこりと笑む。
「帰り道なので。こんな近くに、こんなすてきなカフェがあったんですね。私も利用させていただこうかしら」
「ご自由にどうぞ」
「今日はもう閉店なんですね。それでは失礼いたします」
ぺこり。
女性は私と海里君の脇を通るときも軽く会釈をして出て行った。
「……蒼、あの人のこと、嫌いでしょ?」
私の質問にかっ、と目を見開いて忌々しそうに蒼は低く言った。
「見たらわかるだろう⁈ ここまでわざわざ来てくれて感謝してたように見えたか?」
「あれは……どっち?」
「パラリーガル」
ああ、なるほど。私はうなずく。確かにちょっと、ただものではない感じがする。
「朔さん! また! 昨日の女の人と同類! 嫌な感じで朔さんを見てました!」
海里君がキャンキャンと吠える。
はは。ほんとに柴犬みたいでかわいい。
私が侮辱されたと思って不快に思ってくれるのも、嬉しい。
「大丈夫だよ、海里君。見られただけ。何もされてないから」
「でもあの視線は敵意です! 女の人って、きれいな外見でもああいう目をしたらすべてが台無しですよね!」
なるほど。参考になる意見だね。
ぷりぷりと怒りながら、海里君は戸締りの確認に行く。
「ちゃんと仕事はしてるみたいね」
午後11時20分。
ベッドに寝転がりなら暉のSNSを覗いてみると、さっそく高級ヴィラの写真が数枚、アップされている。
かやぶきの高い天井、そこから木製の低い大きなベッドに垂れ下がる白い蚊帳、白い石の床に籐製のソファ。開け放たれた全面ガラス戸の外には、プライベート・プールのある熱帯植物の庭。
普段から暉は、海外にいるときはほとんど連絡をよこさない。だから私は暉のSNSから消息を知る。
「ほんとに言わないでおくのか? 一昨日のこと」
隣でうつ伏せで目を閉じた蒼があくびをしながら言う。
「どうせ月曜には帰国するから、その時に言えばいいよ。入り口のドアが変わってることをまずは変に思うかもしれないね」
「帰ってきたら大変だ。話を聞いたら泣き出すかも、あいつ」
「そこはうまくごまかすとして……ん?」
私は投稿画像のいくつかに目を留める。
「なに?」
「これ……誰だろう?」
ひとつは、エメラルドグリーンの海をバックに、木製の手すりにブーゲンビリアの花を飾ったカクテルグラスを置いて、背を向けている細越の白いマキシ丈のスリップドレスの女性。よく日に焼けた艶やかな肌、バレアージュが入った長い、腰まである緩やかな赤みが勝った茶色の髪。
ふたつめは水平線に溶け込むようなデザインのプライベート・プールの縁に腰かけて、大きな夕日にしなやかな両手を広げている同一人物。
そして……水平線を目の前にかやぶき屋根の下、1mほどあけて二つ並べられた赤いバラの花でいっぱいの白い浴槽、一方には暉、もう一方には一連の女性が入り、背を向けて手をつないでいる。ふたりとも横顔で、お互いを見つめて笑っている。
今回は現地で見つけると思っていたけれど……その人は現地の女性ぽくは見えない……
「あ、それ、ホテルのオーナーの娘らしい。暉のSNSのファンで、彼女の推薦で今回の仕事を任されたって言ってた。モデルやってて、トップインフルエンサーだ。彼女が暉をモデルにして撮った写真を自分のSNSに載せて、暉は彼女の写真を載せる。これで暉のフォロワー数もまたガンガン増えるだろうな」
「そうなんだ………」
なんだか、別世界の話みたい。てか暉、セレブモデルと一緒に写っても遜色ない存在感。
一緒に行けばスパを満喫できるかもしれないなんて考えていた私は、暉を利用して名前を売ろうとする人たちとそう変わらない薄っぺらさだ。でも、わかる。これ見たらすごく行ってみたくなるもの。
「なに、しょぼくれて。あんたも行きたかったのか」
蒼が人差し指で私の額を押す。
「ん……スパは魅力的。すごく癒されそう。いいなぁ。海を眺めながらのフラワーバスやアロマオイルのマッサージ」
「暉に言って、3泊ぶんくらい分捕れ。恐怖体験したんだから、それくらいの価値はあるだろ」
「誰と行けって言うの? 翔ちゃん?」
「その辺のホテルのスパだったらそれでいいけど、バリなら彼もパートナーと行きたがるだろ。ばかじゃないの、朔」
「なによ、リゾートにひとりで行っても楽しくないよ! ……ぁ痛っ!」
デコピンが飛んできて、私は額を押さえる。