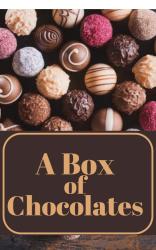「火曜から月曜まで、仕事でインドネシアに行ってくるよ。だからそれまでの間、蒼によく頼んでおいたから。何か困ったことがあったら、あいつに言いなよ」
そう言って暉は、ベストシーズンのバリ島へ出かけて行った。
いいなぁ、バリ。
今回はアメリカ系列のホテルの、新しくオープンしたヴィラを宣伝するらしい。そいうところはたいていはカップル向きだから、もしもカフェがなければ私も連れて行ってもらってスパを満喫できたかもしれない。
日本のはよくわからないけれど、海外のトラベル・インフルエンサーはよくカップルで旅をしている。手つなぎショットとかカノジョがプールサイドや雪山ロッジでくつろぐショットなんかを載せて、ロマンティックな旅を演出するのだ。
暉の場合はその時々に付き合っているカノジョとかあかねさんのような親しい友達に協力してもらったり、現地で知り合った映える美女にお願いしたりするらしい。今回は後者かな。
「あ、まただ」
屋根部屋でメールチェックをしていた私はため息とともに呟いた。ここ数日、一日に10件以上届く不審なメール。
《いつの何時に行けば、暉さんに会えますか?》
《暉さんと話したいんですけど》
《暉さんに会いたい。( そしてケータイの番号 )》
《暉さんのことが忘れられない。会いに来てくれないなら、私が会いに行くから》
「なんか、怖いよね……」
暉が出発してしまった日の夕方、事務所には戻りたくなくて裁判所から直帰にしたという蒼がうちに「帰宅」した時、それらの不審メールを見せた。
今週は忙しいからあんまり来られなそうだって、言ってなかったっけ? それとも、無理無理に来てくれたのかな?
「珍しくはないかな。あいつのSNSのファンだろう。ネットストーカー的な? SNSブロックされて、カフェのアドレスに送ってくるのかもしれない。ちょうど暉が海外でいないし、妙子さんと海里にも注意するように言って、昼間でも絶対にひとりになるなよ?」
「珍しくはないの⁈」
「ないよ。あいつのカノジョになれば年中ゴージャスなホテルを泊まり歩けると思う奴とか、自分の画像載せてもらって有名になろうと野心を持ってる奴とか。ストーカーになる奴もいる。この前のシオリの合コンで、あいつを酔いつぶしてお持ち帰りしようとした女みたいなのが、結構いるんだよ」
「そ、それは……知らなかったぁ……」
思わず、遠い目になる。だから暉がいつもしつこいくらい、自分が不在の時は蒼を頼れと言っていたその意味がやっと分かった。
「今までは離れて暮らしてたけど、一緒に住む以上、きょうだいだって知らないで誤解する奴もいるだろうからって、あんたのことを心配してるんだよ」
……なんて話していたいた翌日、私は身をもってその恐怖を体験することになる。
水曜日、午後1時。
ネットでの来店予約は3時までなかったし、予約なしで直接来店のお客も12時でちょうど途切れた。海里君は3時に来ることになっていたし、妙子さんは銀行と市役所に行く用事があったので、「3時に戻ります」という札をドアに掛け、カフェを一時的にクローズした。
入り口のドアの施錠を確認して……私は昼休みをゆったり過ごそうと、屋根部屋でランチを取って読書していた。
空はどんよりと曇っていて、いつ雨が降り出してもおかしくない模様。そいえば、もうすぐ梅雨の季節ね、と眠気に負けてあくびをしていると……
ぱりん。
うん?
ガラスが割れる音。
次に、ガチャガチャと、何かをこじ開けるような音。
うん……
「‼」
眠気がさぁぁーっと一気に引く。
あれは……
誰かが、侵入してる音⁈
ぱきぱき、ぱりん。
割れたガラスを誰かが踏んでいる。
「……ぁ」
落ち着け、私。
どくん、と心臓が激しく鼓動する。
震える指でケータイを操作して、蒼に電話をかける。
『只今、電話に出ることが――』
無情な機械音声。
ぱきぱき、ぱき。ぱきぱきぱき、ぱきん。
足音が、消える。
ガラスが散らばっていないところを歩いているのかもしれない。
「~~~~~~~!」
指先が震える。もう一度、二度、三度、蒼にかけ続ける。
「だれか! いませんかぁ?」
女性の声。
あああ。
メールの人かもしれない。とっさにそう思う。
「暉さーん? どこですかぁ?」
感情が読み取れない、一本調子の大声。なんだかすごく怖い。
「——もしもし? 朔?」
やっと、通じた! 聞き慣れた蒼の声。私は口をパクパク動かすけれど、焦っているからか怖いからか、声が出ない。
「朔? どうした?」
「そ、う、そう、だ、だれか、かふぇのどあ、こわして……だれかっ、くる!!」
「わ、わかった、今すぐ行くから! 電話切るなよ! わかったな!」
見えるはずもないのに、私はこくこくと壊れた人形のようにうなずき続ける。
「ちょっとー。だーれーかー! いませんかぁ⁈」
怒りと狂気を含んだ叫び声。
カツカツカツ。
軽いヒールの音。1階をくまなく歩きまわっている。時折、ガラスが踏み砕かれる音が混じる。
侵入者は、女性一人のようだ。ほかの足音は全くしない。
軽い足音からして、そんなに大柄ではないかもしれない。
「お、お……おんなの、ひと、よ。ひとり、しか、いないみた、い」
大きな声で言っているつもりだけど、ほとんど声になっていない。
「朔。落ち着いて。あと5分くらいがんばれ。警察にも通報したから。屋根部屋にいるのか? まだ見つかってないだろう? 隠れてろ。来たら、なんか、何でもいいから投げつけろ」
カツカツカツカツ‼
もの凄い勢いで、階段を上がってくる音がする。私は声にならない悲鳴を上げる。
「やだっ、く、る! くる! くる‼ いま、たぶん、に、かいにあがってきてる!」
「誰かぁ、いるんでしょう? こそこそこそこそ、声が聞ーこーえーてーくるーよぉぉぉ!」
こわいこわいこわいこわい!
私はデスクの下にうずくまる。2階を歩き回る足音。このままだと、本棚の陰のわかりづらい位置にある屋根部屋への階段が見つかるのも時間の問題だ。
「どーこーですかぁぁぁ? 女の声でしょぉおお? 暉さんを隠してるのぉぉぉ?」
カツカツカツカツカツ!
ぎぃぃぃぃぃ……
バタン!
「そう、そう……くる、くるよ! ああぁあがってくるっ!」
声になっていないから、私がなんて言ってるのか聞き取れないかもしれない。
デスクの下でガタガタ震えながら身を縮めていると、階段を上がってきた若い女性の、ぎらぎらと狂気に輝く目が私をとらえて嬉し気に見開かれた。
「あーあ、そんなところにいたのぉ。あなた……」
屈みこんで私を覗き込んだ彼女の目がカッ! と怒りでさらに大きく見開かれる。
「あの人の何なのぉぉぉぉ⁈」
いらだつ叫び声が私に浴びせられてくる。
私は頭を抱えて叫ぶ。叫んでいるけれど、声が出ていない。
きれいにジェルを施されてラインストーンがちりばめられたブルーの爪が目の前に伸びてくる。
「やだぁぁぁぁぁぁっ!」
――おわった。
あのツメで引き裂かれて、殺されるかもしれない。
目を、えぐられるかもしれない。
声にならない声で、叫び続ける。
こんな死にかた、絶対に嫌っ!