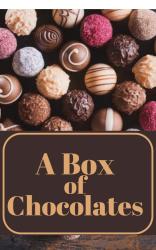「ふたりとも、これ、俺の親友の蒼。ここにもよくいると思うんで、よろしくね。蒼、こちらは朔の親友の翔君とそのパートナーのケイ君だ」
なぜ、私の友達に私の目の前で自分の友達を紹介するのか、時々、暉の行動は読めない。
でも先ほど、なんて言って蒼を二人に紹介すればいいのか悩んでいた私の些末な悩みは、これであっけなくどこかへ消え去ったので良しとしよう。
一番背後での私の安堵の表情を見た翔ちゃんとケイ君も、ほっとした面持ちでうんうんとうなずく。
三者が挨拶の言葉を交わす。初対面だけど翔ちゃんもケイ君も私からさんざん話を聞いているので、蒼のことはよく知っている。蒼も、私が半年前に酔っぱらっていろいろとしゃべっているので、翔ちゃんとそのパートナーのケイ君のことをよく知っているはず、だ。でも双方はとぼけて暉からの情報しか知らないかのようにふるまった。
そういえば、蒼は腹黒だけど、翔ちゃんも負けず劣らずの腹黒だったっけ。
海里君が階下から暉を呼ぶ。外国人のお客が来て暉を呼んでいるらしい。暉は「じゃ行ってくる、みんなごゆっくり!」と言って1階に戻る。
「じゃあ、俺はこの上でちょっと仕事してる。おふたりさん、話には聞いてたけど、会えて嬉しいよ。ごゆっくり」
蒼は、おそろしく完璧な外面に笑みを浮かべながら屋根部屋に上がっていった。
翔ちゃんは高速手招きで私を呼び寄せると、ひそひそ声で早口で言った。
「朔! 何あれ! 前にワンナイのこと聞いたとき僕、チョイス最高って言ったけど……あれは超絶最高だよ! がんばれ!」
ケイ君もうんうんとうなずく。
「朔ちゃん、逃がしちゃダメだよ!」
ははは。
1階に戻り、飲み物をとりにバリスタマシンが置いてあるキッチンカウンターへ向かう。
「ちょっとぉ、朔ちゃん! やるわね。入れ代わり立ち代わりイケメン!」
妙子さんがカウンターの内側でにやにやと笑う。
オーダーを伝えに来た海里君もにやける。
「ねえねえ両手に花の朔おねえさん、僕の悩み聞いてくださいよ。アドバイスほしいなぁー」
「ないない! アドバイスなんて無理です!」
私は自分と蒼のアメリカーノをトレイに乗せて妙子さんからフォンダンショコラを一つもらうと、急いでカウンターを去った。
屋根部屋に上がると、蒼はソファに座りラップトップをひらいたまま、イラついた様子でスマホで話していた。
「——いや、だから結構です。はい? 何のために? は? 個人携帯に連絡は今後しないでください。ちょっと、用事あるんでもう失礼します」
ぶち。
ちっ、と舌打ち。
機嫌悪そう。
コーヒーとフォンダンショコラをガラステーブルに置いて、隣に座る。
中指を親指でぐっと折り込んだ右手が私の目の前にかざされたので、すかさず自分の額を両手で覆い隠して上半身をのけぞらせた。ソファのアームに頭を預ける形で。
「やだっ、八つ当たり禁止!」
ふん、と小さく鼻で笑った蒼は、両てのひらをぽん、と私の胸の上に置いた。
……えっ?
「なんでそうなるのよ?」
「目の前にあったら、触るしかない」
「指、ゆび! 動かさない! 変態!」
がしっ、と蒼の両手首をつかむ。でもはがせない。
さわやかな恰好で何してくれるのよ?
「少なくとも、女から見れば男はみんな変態だろ?」
「ほんと、もう終わり! 誰か来る、暉が突然来るかも! だめだってば、手、くすぐったいっ」
私のシャツの裾から不埒な手が滑りこんで……わき腹をくすぐられる。わざと触《ふ》れるか触《ふ》れないかで指が一本ずつ肌の上を行き来する。
私は逃げようと必死に身をよじるけれど、組み敷かれて身動きできない。だからソファの上で笑い続けるしかない。
また、蒼のスマホが鳴る。
私はやっと解放されて身を起こす。
スマホの画面を見て蒼は面倒そうにち、と舌打ちしてからもの憂げに電話に出る。
「——はい。はい。何の用でしょうか。いいえ、遠慮しておきます。いや、あなたには関係のないことですよ。は? いや、結構です。忙しいので失礼します」
いらっとオーラを発している。嫌な電話が2連発? 聞いたことのない、イラついた低い声。
「どいつもこいつも、むかつくな」
蒼はいらっとしながらジャケットを脱いでソファの背もたれに掛け、私の膝の上に頭を置いて寝転がる。私は手にしたフォンダンショコラのお皿を落としそうになる。
(これは、甘えてるの?)
じっとフォンダンショコラを見上げて、不機嫌に引き結ばれた口があ、と開く。なんかかわいい、鳥のひなみたい。一口分を口元にもっていくと、ぱくりと食らいついた。
「歓迎会で何かあったの?」
ぴく、と右眉が動く。
「あったあった。オヤジの知人の息子で同い年のイヤミな奴がマウンティングしてきたし、事務員とパラリーガルの一人がしつこく言い寄ってくるし、おまけにあの女もやたら頻繁に電話してくるんだよ」
「えっ?」
どこから突っ込めばいいか、わからない。
「おまけにあの同窓会の追い飲みだと思ったら合コンだったやつにいた何人かが、俺の連絡先教えろってシオリにうるさいから教えてもいいかとか、うざいことだらけだ」
ええと、とりあえず、わかりそうなところから……
「あの女っていうのは……あの美人検事さん?」
「そう、あのメギツネ」
(連絡欲しそうにしてたよね)
「何の用事で頻繁に?」
蒼はふんと鼻で冷笑する。
「お誘いの連絡だろ」
「はい? でも彼女、既婚……で、新婚?」
「俺もなめられてるよな? あんたもいたのに、気にしてないってことだろう?」
ああ、なるほど。モールで会った彼女は、私を無視してたのもね。
「おまけに、イヤミ野郎はすでに勝手にライバル視してくる。プロボノやるのは何の利益のためなんだとかバカげたこと言ってきてうざい。プロボノの意味わかってんのかっつうの!」
「いるよね、そういう面倒な人って」
「事務員はやたらあちこちに色目使って高慢な女だ。そいつよりもパラリーガルのほうが何考えてるのかわからない底知れない怖さがある」
「厄介そうな人たちに、目を付けられちゃったわけね……」
「……」
はは、と苦笑すると、蒼は私をじっと観察するように下から見つめる。なんか怒ってる? 私は首をかしげた。
「?」
「あんた」
「ん?」
「イヤミ野郎はともかく、そのほかに対して、何も言いたいことないわけ?」
「え? 蒼のモテ自慢?」
「……じゃなくて。いや、もういい」
蒼は起き上がり、コーヒーを呷ってラップトップに向かい、キーを打ち始める。
なによ?
合コンの次の朝、暉が言ってたよね。
『ほとんどの女がお前を狙ってた。まあ、いつものことだったけど』って。
それに、あの美人検事の人妻は、まだ蒼を諦めていない……
もや。
もやもや、もや。
心の中にどす黒い煙が立ち込める。
何も言いたいことないわけ、ないじゃない。
私は黙々とフォンダンショコラを口に運んだ。
微かなフォークがお皿に当たる音と、蒼の打つキーの音だけが聞こえていた。