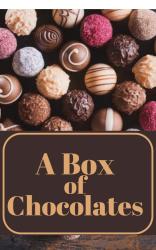黒のストレートチップ、ダークネイビーのイタリアンスタイルのスーツ、白いシャツ、ネイビーブルーのタイ。普段降ろしている前髪は自然に後ろに流している。文字盤がネイビーのシルバーステンレスベルトのスイス製の腕時計、右手の人差し指には車のスマートキーを引っかけている。
なにその、スーツのモデルみたいな登場の仕方。
「お疲れ。なに、三人とも、口開いてるよ」
はっ、と我に返る。
全員で蒼に見とれてた。
「挨拶、終わったの?」
「ああ、オヤジと飯食ってそのまま来た」
「うーわーぁ! 蒼さん、惚れる! 超絶男前!」
海里君がはしゃぐ。
「普段もすんごい男前だけど、ビジネスモードはさらに素敵ねぇ~」
妙子さんもはしゃぐ。
半年前、ホテルのバーで見かけたときは、結婚式のあとだったからフォーマルのダークスーツだったけど……
(弁護士が、そんなに色気だだ洩れでもいいの?!)
秘書だった頃に専務のスーツ姿を見慣れた私でも、動揺しちゃう。
専務は、アメリカンスタイルが多かったな。
「あれ? 蒼さん、あれは? 天秤のバッジ! つけないの?」
「んー、べつに義務じゃないからな。面倒くさいし。な、妙子さん、ちょっと朔借りるよ」
蒼は私の手をつかむと、階段を上がり始める。
「はいはい、ごゆっくり。飲み物ほしかったら言ってね。言わなければ、絶対、ぜぇぇーっったい‼ 邪魔しないから!」
ほほほ、と妙子さんがソプラノで笑う。妙子さんはもうすでに何日も前に勘付いているはず。バツが悪い。
屋根部屋に着くと、蒼は私のワークデスクの上にスマートキーを置いた(とういか投げた)。
「それ、どこの車のキー?」
「うん? ああ、しばらく乗る必要ないからって、アニキのXV乗っていいっていうから借りてきた」
蒼はスーツのボタンをはずして私の椅子にどっかりと座った。
「ちょっと、手を放してよ」
デスクのそばに立ったままの私は、まるで説教される部下みたいじゃない?
「やだ」
「はい?」
ぐい、と引っ張られ、私は蒼の膝に乗せられる。
「これ! 一回やってみたかったんだよ。秘書を膝に乗せるシャチョウごっこ!」
「もう秘書じゃないよ!」
「あのワインくれた上司には、乗せられたことあったか?」
「そんなのあるわけないでしょ! ばかっ! そんなヘンタイ妄想のために私を連れてきたの?!」
「んー、そうだと言えばそうかもしれないし、そうじゃないかもしれない」
蒼は私を抱えたままPCの電源を入れる。
PINコードは3523。
目の前でキーボードをたたく長い指を見つめる。
「私が降りたほうが見やすいでしょ?」
「いいから」
ん?
外国のサイト?
「朔、ペンとメモとって」
「あ、はい」
手を伸ばして言われたものを引き寄せる。すると蒼はなにやらメモし始める。英語だけど……専門用語が多すぎてよくわからない。ざっと画面から読み取れるのは、難民申請に関するものだということ。
「どうして難民?」
「今度、大学の先輩から頼まれてプロボノするんだ。その下調べ」
「では、あちらで広々とやられてはいかがですか? 先生」
私は窓辺の蒼の席を指さす。自分のラップトップもあるじゃない。
(今の体勢、書きづらくないの?!)
「んー、ちょっと。10分だけそのままおとなしく待ってくれ」
どうしてよ……
文句を言おうとしたとき、蒼のスマホが鳴る。蒼は画面を見てから私にも見せて人差し指を立てる。
暉からの着信だ。
「はい、なに? えっ? うん、うん。あー。そっか。わかった。うん」
通話を終えると彼は私を見て肩をすくめた。
「あいつ、今日の夕方帰るって言ったけど、明日の昼の便になるって」
「……なんで私じゃなくて、蒼に連絡してくるのよ」
「朔のことをよろしくってさ。ということで、俺は明日の午後帰ることにする」
「……いっそ、ウチに住めば?!」
「うん、それもいいな。そうすればいつでも朔と……」
「冗談だから!」
笑ってる。また笑ってる!
4時に上がりましょうということで、妙子さんと海里君が帰る。
私たちは離れを閉めて母屋に移動する。
蒼は客間に置いてある荷物から、いつもの楽な部屋着に着替える。そしてキッチンのダイニングテーブルで眼鏡をかけて調べ物の続きをしている。
その間私は夕飯を作る。
「今日私ね、女子高生を不審者から救ったの」
「は? どこで? どんな状況?」
蒼は眉をひそめて顔を上げる。
「午前中、スーパーの帰り道に、公園で。警察に電話するって言ったら、逃げて行ったわ」
「あんた、いつもは気が小さいくせにどうして」
「だって、嫌がって泣いてるのに、無理やり連れて行こうとしてたから。犯罪じゃない?」
「だとしても、誰か呼んでくるべきだったろう? 殴られたり刺されたりしたらどうするんだ? あんたも連れて行かれたかもしれないし、顔を覚えられて逆恨みに何かされるかもしれないんだ」
「……正直、そこまで考えなかった」
「猛省しろ、山野井朔。そしてこの次は迷わず通報しろ」
すごく心配しているようなので、はい、と素直にうなずいた。
「それで、助けたカメは、何かくれたのか?」
「えっ? あ、その子ね」
(女子高生をカメって。それじゃ私は浦島太郎?)
私は苦笑して続けた。
「うちのカフェを探してたって言うので、とりあえず連れてきてちょと話したの。高校時代の私みたいな子で、なんだか親しみを覚えちゃった。るなちゃんていうんだけど、これからもカフェに来てくれるって」
「なんだ、その子も月か」
「え?」
「ルナって、ラテン語で月って意味だろう? 朔と同じ、月だよ」
「ああ……ほんとだ」
るな。
月か。
妙に懐かしいし……何か縁があるのかな?