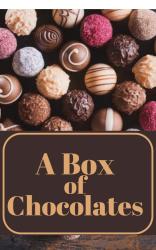――というわけで。
平日に学校おサボりの女子高生を危ないナンパ男から救った私は、女子高生が押してくれる私の自転車の後ろの荷台につかまって、彼女と一緒に道を歩いている。
「お店を探しているんです」
背は、私より少し小さい。細くてお人形のようにかわいらしい。ストレートの背中を覆うさらさらの髪、大きくて少し垂れた目は、小動物みたいに愛らしい。
「初めて降りた駅で、よくわからなくて。そうしたらさっきの人が、駅からずっとついてきたみたいで……怖かった」
「そう。何ていう何のお店? 住所がわかれば教えてあげられると思うけど」
彼女は大きな目を輝かせて私を振り返る。
「ほんとですか?! ブックカフェで、『ウト』っていうんです!」
「それは……うちだわ。でも残念。オープンは明後日なの」
私が苦笑すると、彼女はさらに大きな目を大きく開く。
「うそ……おねえさんは、ウトのかたなんですか?」
「ええ。私と兄の店」
本当は父さんの店だけど。
「私……たまたま、アキさんていうインフルエンサーのかたのSNSで知って。そんなに遠くないところだから行ってみたくて……」
「ごめんね。あ、でも、せっかく嫌な思いしてまで探そうとしてくれたから……オープン前だけど、よかったらお茶をごちそうするわ」
「いいんですか?!」
「もちろん。これからもよろしくという意味で」
女子高生の顔に喜びが広がる。かわいい。リスみたい。
「ありがとうございます! 私、木内るなっていいます」
「ウトの山野井です。よろしくね」
「おねえさん、下のお名前を訊いてもいいですか?」
「さく、っていうの。古文でついたちっていう意味の朔。男みたいでしょ」
「そんなことありません! 朔おねえさん!」
ああ。なんか、こそばゆい。こんなかわいい子に、「朔おねえさん」だなんて呼ばれて……
カフェに着いてアイスキャラメルラテをごちそうすると、るなちゃんはぽそぽそと話し始めた。
「今朝、お母さんとけんかしたんです。それで学校に行きたくなくて、お母さんの真似して電話をかけて、勝手に学校を休んで……このカフェを探そうって思ったんです」
「その制服、清水《きよみ》学園の制服だよね。そんなに遠くないけど、近くもないよね」
隣の市の、幼稚園から大学まであるお嬢さん学校の制服。緑系のチェックのプリーツスカートに丸襟ブラウス、ほそいエンジのリボンタイに濃紺のブレザー。
高校1年生になったばかりだけど、小学生の頃から通っているという。外見からして想像できるけど、るなちゃんはおとなしくてほかの子たちの中でも浮いてしまい、友達と呼べるような友達がいないらしい。なんだか、私の子供の頃に似ているかも。
彼女は本が好きで、ファンタジーを読んだり、外国の風景や建物の写真集を見るのが好きだという。だから、暉のSNSのフォロワーだそうで。
たぶん彼女は、同級生の子たちと話すよりも、大人と話していたほうが落ち着くのかもしれない。元気ではじけている女子高生ではないみたい。
お昼前になって、るなちゃんは家に帰ってまた土曜日に来ます、と言った。
ちょうど海里君が出勤してきたので、るなちゃんを駅まで送ってくれるように頼んで送り出した。塾講や家庭教師のバイトをしたことがある海里君は、その柴犬のようなキュートな外見とさわやかな笑顔で、るなちゃんをすぐになつかせた。
「ちょっと僕の恋バナ聞いてよ!」という22歳の海里君に、「私、なんのアドバイスもできませんけど」と15歳のるなちゃんは眉尻を下げる。すると海里君が「聞いてくれるだけでいいんだ」と言って、ふたりは駅へ向かった。
「なんだかかわいらしい、兄妹みたいね。若い子たちはすぐに仲良くなれていいわぁ」
妙子さんは笑った。
「海里君も年下の子の扱いがうまいみたいだね」
「そうね。年下の彼女見つければ、あの子も苦労しないのにねぇ」
私は妙子さんと顔を見合わせて苦笑した。
バイトの面接の時に言っていた海里君が好きな「ヤマネコみたいな人」とは、学部の助教で5歳年上の知的美女だという。もう2年も片思い中らしい。ふわふわと彼女にまとわりついてぎゃふんと追い払われて、そしてまた何事もなかったようにまとわりつく。それがこの2年のルーティーンだと本人はどや顔で言っていた。
「るなちゃんのこと、なんか私わかるな。私もあの頃、あんな感じだったでしょ?」
私の言葉に妙子さんは遠い目をする。
「そうねぇ。あの年頃自体危なっかしいけど、朔ちゃんはちょっとどこかにぶつかったら、簡単に粉々に砕けちゃいそうだったわね。でも今は、ちゃんと通り抜けて立派な大人に育ってくれたわ」
「妙子さんがいてくれたからだよ」
「15歳なんて、何でも楽しくてなんでもつらい時期だものね」
そうだよね。自分が何者なのかわからなくて、自分は特別じゃないって気づき始めて、自信なんか持てなくて、他人よりも劣ってる気がして。人の輪の中の中心部分に入り込むことに失敗すると、ますます内にこもってどんどん孤立していく。
そういう子は中心に居座ることに成功したキラキラした子たちに嫌われる。彼女たちは暗くて自己主張しない子たちを見ると、いらいらするのかもしれない。
海里君が戻ってきて、三人で妙子さんの賄い飯でランチにする。昨日私がいない間に届いたレジとQRコード決済システムを海里君に教わって、明後日の開店記念に配るクッキーを三人で先着30名分作る。
2時半を少し回ったころ、蒼がカフェの扉を開けた。
扉が開いた瞬間、私たちは三人とも吃驚して言葉を失った。