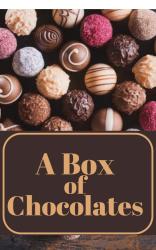ブラインドの隙間から傾いた日の光が差し込んできて、ああ、この部屋は西向きなんだなとぼんやりと考える。
ぼんやり……しか、頭が回らない。
うーん。
私はよほど、信頼がないみたい。
逃げたのは、たった一度じゃない?
上半身を起こしてめちゃくちゃなシーツのしわの上に座って視線を落としてみると、右手首をがっちりとつかまれていた。
もう驚いてもいないし、逃げる気力もないし必要もない。
身元はばれてるし、これっきりで終わりになることは、少なくともないはず……だから。
『もう逃げるなよ』
うつ伏せで眠る、きれいに整った顔。
もう二度と起こらないと思っていたことが、また起こった。
それは蒼に言わせればまったく不思議なことはなくて、起こるべくして起こったこと。
半年前のことは、もうずいぶん時が経ったし、すべてを鮮明に覚えているわけではない。何度か思い返すうちに、いろんなことが美化されたかもしれなかった。でも、それでもいいと思った。だって、一生知ることがなかったことが知れたから。
もう半年も経っているのに。
私の体は、蒼を覚えていた。
いや、「忘れられなかった」みたい。
相性は、ある。
100%、ある。
改めて、確信した。
28年の人生の中で、安定した関係を築けたのは駿也くらいしかいなかった。
私の恋愛経験なんて、本当にしょぼい。
小中学校では人見知り過ぎていつも暉の後ろに隠れていた。中2の時に暉に初めての彼女ができて少し距離を置く努力はしたけれど、その彼女が嫉妬して私をいじめてきた。暉はその子とはすぐに別れてしまったけど、私はずっと罪悪感を感じていた。
だからわざと高校は、暉の希望した学校から遠く離れた女子高を選んだ。私が人見知りなのは私の自由だけど、そのせいで暉の恋愛の邪魔をしてはいけない、いやそれ以前に、暉から自立しないといけないと強く思ったからだ。
だからと言って、高校で積極的に社交したわけでもないけど。
女子高に行ったからと言ってそれが恋愛をしない理由にならないのは重々承知だった。でも、3年間は少なくともトラブルなく平和に暮らせそうだと安心した。
大学に入り、例の先輩のことで変に警戒心が高まったせいで、私にはその後も「カレ」と呼べる存在は現れなかった。
大学2年の時、バイト先の大きな書店で、他大学の一つ下の男の子と話すようになった。年下なのに大人びていて、本の話をしていると本当に楽しかった。ほかの男の子たちとは、違う感じがした。働いているときはさりげなく手を貸してくれたり協力しあったりして、とても気が合った。ほかの気の強いバイトの子たちからも守ってくれて、極めつけは社員である店長に強引に迫られた時に助けてくれた。
彼はいつも私を「朔ちゃん」と呼んでいた。「朔ちゃんは年上だけど、年下みたい」と言ってはにかんだ笑顔を見せる。身内以外の男の子に名前で呼ばれたのは、それが初めてだった。私は彼を何て呼んでいたっけ?
彼には忘れられない人がいた。その人には、もう会えない。なぜなら、その人は交通事故で亡くなってしまったから。
私はそのことを聞いていた。だから彼は同じバイトの女の子に告白されても、誰とも付き合うことはなかった。たぶん私と一緒にいたのは、私の好意がそういうものではないことをわかっていて楽だったからだと思う。
店長はバイトの女の子たちの間では、前からいろいろと悪い噂の立っていた人だった。ある日、私は事務所に呼び出されていきなり抱き着かれた。悲鳴を上げると、心配でドアの外で待っていた彼が飛びこんできて助けてくれた。
その日に私たちは一緒にバイトをやめ、ずっと一緒に過ごして、そのまま私は彼と初めて寝た。
どうしてそうなったかはよく覚えていないけど、そうなったのはその時一回きり。別々のところで別のバイトを始めてからも時々会っていたけれど、そのあとは何もなかった。数か月後には彼がカナダに長期留学に行って、自然と連絡が途絶えた。
――それからも誰かに誘われたり口説かれたりしたことはあったけれど、数回デートして自然消滅する程度だった。駆け引きなんてできないし、相手の気持ちなんて、自分でもわからないのにわかるはずがない。もっと会いたいとか一緒にいたいとか、相手に対して興味を持つことができなかったのかもしれない。
大学を卒業しても就職してからも、結局、私は誰にも特別に興味を持つことができなかった。誰に誘われてもその先に進もうとは思えなかった。
そして25歳の時に、駿也に出会ったのだ。
交際期間2年間は、もちろん最長で唯一の記録。
「ひとめぼれした、付き合ってください」と言われたのも唯一。
何度かわしてもめげずに3か月間も口説いてきた、唯一の人。
でも、翔ちゃんに指摘されたように、情熱とか欲望とかは感じたことがなかった。
私は常に受け身だったし、時々は冷めたことも考えてはいた。
それでも、「そんなもの」だと思っていた。
付き合っている間も、別れた後も。
――半年前までは。
「ねぇ、逃げないから、放して」
そっと耳元にささやく。
私の声はもう、かすかすに掠れている。
「うん……? なんで」
切れ長の目がうっすらと開いて、ブラインドから差し込む西日に眩しそうに細められる。
「買ってきたワインを冷やして、夕飯を作るの。シャワー借りるね」
するり。
右手首が解放される。少し、ほっとする。
「リビングの、ソファの脇」
掠れた低い声がぼそぼそと聞こえる。
「え?」
「白いデカい紙の袋」
それだけ言って、また寝息が聞こえてくる。
リビングに行くと、食材やワインはすでに蒼が冷蔵しておいたみたいでほっとした。
ソファの脇にはさまざまな大きさの様々な袋がまとめて置かれていた。
「あっ。全部持ってこなくてよかったのに……」
私が生活雑貨の店で買ったバスオイルやボディミルクまで一緒に置かれている。
そして……
「えっ……なにこれ? いつの間に?」