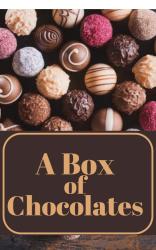「おお! できたか! さすが蒼!」
板階段を上がってきた暉がひらひらと手を振る。
蒼は私の背後から離れて、ヒモでくくった段ボールを階段近くの暉の足元まで蹴る。
「これ捨てておけ。ついでに窓際のほうに、俺専用のデスクがやっぱり必要だな」
「えっ? どうして?」
我に返った私が驚くと、蒼は肩をすくめた。
「どっちかというと本を読みに来るよりも仕事がしたいから、下の階じゃまずいだろう?」
「好きにしてくれていいよ。俺が海外に行ってる間は、朔のことをお願いしたいし」
「なんでよ。妙さんだっているし、心配ないよ」
「女ふたりじゃ心配だよ。蒼の事務所、ここからでも近いじゃん。俺がいない間は、蒼が俺の部屋に泊まってくれてもいいし。あ、女連れ込むのはナシね」
暉は腕組をして首をかしげる。
「いや、待てよ。蒼だって仕事で忙しい時があるよな。俺のSNSの前宣伝で結構反響が大きいから……やっぱり一人くらいはバイト雇うか。学生とか、いいかな」
「ちょっと、暉……」
「それより昼飯! 蒼は何が食べたい? 朔がいればメシに困ることはない! 朔はメシを生み出す金のガチョウだからな!」
「……」
なに、それ……? 妹を、「メシヲウミダスキンノガチョウ」ですって?
そんなガチョウ、いないし‼
私は眉根を寄せる。
「おい、暉」
私のこわばった表情を読んだ蒼が能天気な暉をたしなめようとするけれど、私はそれよりも先に空の500ミリのペットボトルを暉に投げつけた。
「うわっ、なに?」
暉は顔面に当たりそうだったペットボトルを反射的に腕ではじいた。
「……なによ、ひとりで勝手になんでも決めちゃって……私……私は、暉の……ごはん製造機じゃないんだから!」
「はぁ?」
暉は目を見開く。
「誰がそんなこと……」
「私のほうがっ、暉の数百万倍しっかりしてるんだからねっ! 暉のご飯作るために会社辞めたんじゃないし! お昼なんて……お昼なんて、自分で作って食べればいいよ! 私、出かけるから! 今日は友達のとこ泊めてもらうから絶対に電話してこないで! 暉なんか見たくない! ばか暉っ!」
呆然とする暉をぎゅう、と階段口で押しのけて降りていく。
わかってる。
もやっとしてたから……普段ならば受け流すどうでもいいことにイラっとしてしまったのだ。
でも暉、調子に乗りすぎだ。食べたいというものを作ってあげるのは別に嫌じゃない。でも、私は飯炊き婆《ばばあ》じゃない。ガチョウでもないし、お母さんでもない。
兄妹だからって、なんでも言っていいわけないのに。
「それは八つ当たりってやつじゃないの?」
電車に飛び乗って、乗り継いで、マンションのエントランスでピンポン攻撃をして、私は翔ちゃんちに押し掛けた。
一緒に住んでる彼氏のケイ君が、ドラマの撮影でハワイに行っているのは聞いてたから知ってた。
駅で電話したら、暇だから別にいいよと言って、お昼ご飯にとろ~りチーズ入り玉子のデミグラスソースのオムライスを作っていてくれた。ミニサラダとデザートのコーヒーゼリーまである。翔ちゃん、神。
一緒に激うまオムライスを食べながら、私は金曜の夜からの出来事を翔ちゃんに話した。
「……わかってるよ。でもなんか腹立って。知りたくもないこと、しかも自分のことじゃないのにぺらぺらと。それに、バイトのことだって勝手に決めちゃうし」
「かっこいい男がどこに行ってもモテちゃうのはしかたないでしょ。僕ももう諦めてるよ」
「翔ちゃんの場合は、彼氏じゃない。私の場合は、そういうんじゃないし……やきもちを焼く資格もない」
「ま、能天気なお兄ちゃんはおいといて。話を聞く限り、その彼はきみに惚れこんでると思うけど。初めて会った時に気楽なのがいいって言ってただけで、きみとはそうだって言われたわけじゃないんでしょう? もしもはっきりさせたいなら、本人に訊けばいいじゃん。一番正確で手っ取り早いよ」
「それができれば」
「はいはい。そうだよね」
「そもそも、ああいうタイプは、ずっと避けてきたし。私とは、正反対だし」
「ねぇ。前に僕、訊いたことあったよね。きみの女としての本能は、相手に自分だけのものでいてほしいって欲望を感じるのかどうか」
「ああ……」
「前カレと別れるまでの朔はすべて受け身で、奪われても文句もなければ未練もない感じだったよね」
――そう。確かに。
誰かに対して何かを特別に求めたことも、自分のために誰かが欲しいと思ったことも、正直言って……なかった。
それを翔ちゃんに、「冷めてる」と言われたのだ。
信頼とか尊敬とかを相手に感じることはあっても、情熱や欲望を感じたことはあるのかって、訊かれた。
「でも今、もやっとするんでしょ? 無邪気でまだまだ子供みたいな双子のお兄ちゃんに八つ当たりしちゃうくらい、いらっとするんでしょ? 朔はもう、その男のことが好きなんだよ。自分だけのものにしたいって思ってるんだよ」
私は呆然とする。
「この際、われを忘れるくらい、のめりこんでみたら? せっかく知ったんだし、一度きりでいいなんて言わないでさ。お互いに惹かれ合ってるんだから、世間一般のつきあってるとかないとかの線引きなんて、どうだっていいんじゃないかな」
どうせもう最初から順番めちゃくちゃじゃん、と翔ちゃんは笑う。
「確かに……失うものは、何もないよね」
「そうそう。好きなら、自分から必死でつなぎとめてみなよ。どうせならとことん、そうだな、憎むくらいまで好きになってみたらいいよ」
デザートのコーヒーゼリーをいただいてその結論に至った時、もやもやがなくなっていた。
それから翔ちゃんとソファで映画を見ていると、私の電話が鳴った。
画面には見たことのある電話番号。
「誰? 兄?」
翔ちゃんの問いに、私はふと笑う。
「違う。そういえば、名前まだ、登録してなかったんだ」
昨日、モールの駐車場で迷子になった時のためにと蒼が着信させた番号。
「あんたが絶対にかけるなって言ったからあいつ、俺に代わりにかけろってうるさいんだけど」
少し呆れたようなしゃべり方。私はくすっと笑って言う。
「反省してる?」
蒼も笑う。
「してるしてる。ちょっと落ち込んでるよ。仕方がないから、昼は俺がヤキソバを作って食わせた。ぺろりとたいらげた」
「蒼が作ったの? 料理できるんだ?」
「ヤキソバくらい誰でも作れるだろ。ところで、伝言だけど。ちゃんと謝るから帰ってきてほしいってさ。今夜はあいつのおごりで外で食べようって。5時に、駅前な?」
通話を終えると、翔ちゃんがにやにやしている。
「行くんだよね?」
「仕方ないな……暉も反省してるって言うし」
翔ちゃんのにやにやは苦笑に変わり、何やら小声でつぶやく。
「これはまた悲しむ人がいるなぁ……」
「え? 何て?」
「いや、何でもない。朔も元気になってよかった」
「ありがと。ランチ、ごちそうさま。ケイ君にもよろしくね」
来るときにどうしようもなくこんがらかっていたいらいらともやもやは、いつの間にか昇華していた。